気が張るものよ、ホリデー気分でのんビリーといこう
知らず知らず、無意識に
なんだかんだと聞いてしまう音楽というものがあり、
気がつけば、聞いているだけでほっとする音楽というものがある。
その二つを結ぶと、自然にMadeleine Peyrouxへと辿り着いている。
時代に関係なく、いつまでも聴きいっていたい音楽。
デビュー以来すべてのCDを
順を追って聞いてきたけれど
不思議と飽きがこないなあと。
なにより、癒されるのである。
最初なんと発音するのかさえあやふやでね…
マドレーヌ・ペイルー?なんて思ってたほどだ。
お菓子じゃないっつーのよねえ。
今はちゃんといえますよ、マデリン・ペルーさん。
最近じゃ随分貫禄がでちまったみたいだけど、
この人の醸すムード、いいですよね。
おおらかというか、地に足がついた大物感がね。
でもじっくり聞かないと、気付かないかもしれない、
それぐらいナチュラルだから。
この人の歌を聞いてからというもの
ちょっとした恋に落ちたような、
有り体にいうなれば、
魔法にかけられたような気分を味わっている。
理想の天空にあるミュージックボックスには
いつの日にもこういう曲がオンエアーされるのかなななんて思うのだ。
そんなマデリンのことに少し触れ置くとしよう。
アメリカ生まれの彼女、
名前からも判る通りフランス人の母親、
フランス領ルイジアナの首府ニューオリンズ出身の父親のもと、
13才のときに両親の離婚とともにパリに移住し、
なるほどふむふむ、どこかヨーロッパ的な、
大陸風をまとっているのはこのためなのね。
22歳で発表した『Dreamland』というアルバムで
頭角をあらわすのですが
すでに十代のころから、パリの街角でバスキングしながら
ストリートミュージシャンたちと共演し、
「早熟の天才」と呼ばれていたというから、
それなりに年季がはいっておったわけですね。
ちなみにバスキングというのが
ロンドンの地下鉄構内での演奏活動のことで、
いまじゃライセンスを取得すれば誰でも演奏ができるんだってね。
素晴らしいことだ。
そのムードはまずはノスタルジックな香りを燻らせます。
ベッシー・スミス、ファッツ・ウォーラー、
ジョセフィン・ベーカー、エディット・ピアフなど、
まるで紅茶にマドレーヌを浸す度に、
失われた時を思い起こすプルーストの小説のように
その時代や気配に浸ることができましょう。
後に21世紀のビリー・ホリデイというふれこみで
あっという間に席巻いたすわけですが、
なるほど、目をつぶってきけば、
ビリーの再来か、と思わせるのはわかります。
ただ思うに、ビリー的な“ブルームード”は薄くて、
もうすこし明朗さがある気がいたします。
そしてマンダリンのごとき、
程よいけだるい甘さが、彼女には漂っている気がしてきます。
そして聞けば聞き込むほど、
マデリン独自の魅力に吸い寄せられてゆくのです。
思うに、それはマデリンがギターを抱えて歌う、
シンガーソングライターだからでしょうね。
そういえば、あれは2006年だったか、
渋谷クアトロでライブを観て、
さらに強く確信を持つに至って
単なる歌い手というわけじゃないのがわかった。
ジャズシンガーというのでもないし、
そんな意味でノラ・ジョーンズあたりと、
比較されるのはしょうがないのかな。
『Dreamland』から約八年のブランクがあり、
この間の事は、だれもがよく存じないミステリーゾーン。
いわゆるスランプ期だとされておりますが、
わたくし的にはその間にこそ、
今のマデリンの成熟へと導いた、
いわばワインでいうところの、熟成期だったのでは、と思うのであります。
かくして、時が熟し、彼女の黄金期がやってきます。
『Careless Love』というアルバムで
全世界で100万枚を越える大ヒットを飛ばすわけですが
ここに運命的な出会いがあります。
つまりはラリー・クラインと出会いですね
ジョニ・ミッチェルの元パートナーとして知られていますが
このラリーとの出会いが、マデリンの熟成を確かなものにしたのです。
かくして酩酊は、続く『Half the Perfect World』に至っても,
冷めることがありません。
それはいったい何故でしょうか?
答えはいたって簡単です。
聴けばわかると思いますが、
何だかとっても温かいのです。
包み込んでくれる抱擁力あるぬくもりある歌。
主張のうるさくない音。
寒い冬に、のどごしを通る
温かい食事や飲み物のようなものだからです。
暗さがない、深刻さがない、
そして押し付けがましさがない、とくれば、
愛されない理由などどこにもありますまい。
だれもが手を伸ばせば、
この温もりに触れることができるのですから。
その意味では、薬漬け・アルコール依存で、
波瀾万丈を生きたビリー・ホリディとは
質が異なるタイプだということが言えましょう。
むろん、どちらが優れているなどという、
野暮な比較は申しませぬ。
ちなみにマデリンは当然のごとく、
ビリーをリスペクトしておるわけですが、
良きアメリカの大衆音楽のエッセンスを
すっかり自分のスタイルに昇華できているところが素晴らしい。
『Half the Perfect World』では、
ボブ・ディランにトム・ウエイツ、レナード・コーエンといった
アメリカンシンガーソングライターたちの名曲を
次々とカバーいたすわけですが
ハイライトはKDラングとのデュエットで
ジョニの「RIVER」でしょうか、
個人的はゲンズブールの「La Javanaise」も捨て難い、
これはデルトロの映画『シェイプオブウォーター』の
挿入歌として使用されたほど
モダンなレトロノスタルジーに溢れた名曲ですが
うーむ、とにかくどれをとっても外れがないっすもんねえ。
2009年「Bare Bone』では、
自ら全曲を手がけソングライターとしての才能を発揮、
アメリカビルボードのチャートで堂々の一位を獲得、
2011年には、ノラ・ジョーンズを手掛けた
クレイグ・ジョーンズをプロデューサーに迎え、
『Standing on the Rooftop』を発表。
2013年には『The blue room』で、レイ・チャールズの
『Modern Sounds in country and Western Music』へのオマージュを、
2016年にはイギリスの古い教会で、
ライヴ録音された『Secular Hymns』を
あのジャズの名門 Impulseからリリース。
さらに磨きをかけた世界は
世俗の賛美歌にふさわしい出来映えを見せ、
2018年いよいよ通算8作目『Anthem』では
再びラリーと組んでアメリカの情勢にモティーフに
これまで以上に洗練されたサウンドをバックに
きな臭ささとは無縁の世界感を
上質なストーリーテラーとして歌い上げている。
そんな心内を「we might as well dance」の中で、
こんな風に歌っています。
It’s easy to see the things going wrong now
It’s easy to wallow in a sad song
It’s easy to cry over all that is gone now
But I believe that we must carry on今ものごとが間違った方に向いているのは簡単にわかるし、
we might as well dance
物悲しい歌にひたるのも容易いこと。
何もかも失われてしまったことを嘆くのだって簡単。
それでも、あたしたちは前に向かっていかなきゃいけないと思ってるわ
たとえ世の中がどうであろうと、
自分は自分としての歩みに沿って歌っていく
それが信条なんでしょうね。
優しい歌声の中に秘められた力強さに乾杯。
この歌姫からは目が離せないのであります。
Half The Perfect World · Madeleine Peyroux
どのアルバムもいいんだけど、一枚あげるとすると『Half The Perfect World』かな。全世界で100万枚以上のセールスを記録した全作『Careless Love』はもちろんだけど、ここには、さらに、彼女の円熟味が増して貫禄まで滲み出してきた。
一曲目「I’m All Right」からして、プロデューサーのラリー・クラインとウォルター・ベッカーの共作ではじまり、その他カバーの選曲もアレンジも実に素晴らしい名曲が目白押し。
トム・ウエイツの「The Heart Of Saturday Night」、ジョニ・ミッチェルの「RIVER」、ゲンスブールの「 La Javanaise」など。
ジャケットもなにげに素晴らしいよなあ。





![[門戸無用]MUSIQ](https://lopyu66.com/wp-content/uploads/2020/11/misiq-1-485x300.gif)




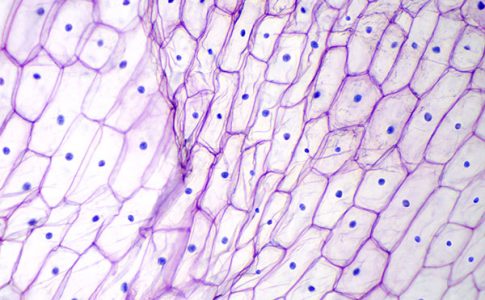


コメントを残す