猫とフクロウを愛した映像のエクリエーターに太陽の微笑みを
八十年代初頭(昭和の末期)の日本の情景は、
我が青春期そのものの舞台であり、
他者の眼差しに、ぴったり重なるのは幻想に過ぎないのだとしても
クリス・マルケルの『サン・ソレイユ』に刻印された映像を見ると、
我が内なる記憶をも呼び覚ましてくれる懐かしい思いがする。
そんなことで、猫とふくろう、
そして、何よりもこの日本を愛したフランスの映画作家の
実にユニークで、愛すべきこの不思議なドキュメンタリー映画を
この擬似的な共感をもって、このシリーズの終わりにしよう思う。
共感を擬似的と呼んだのは、
他者の眼差しを所有することができないからである。
その世界中を旅するカメラマン、サンドール・クラスナから
送られてくる手紙を受け取る女性が朗読するという設定の映像のエクリチュール、
ムソルグスキーの歌曲のタイトル『サン・ソレイユ』が
そのままあてがわれている。
「日の光もなく」・・・これが日本では、
なぜだか集合住宅の名称にしばし使われているのだから、不思議だ。
果たして、その関係者たち、および住人はその趣意をご存知だろうか?
まあ、そんな事はどうでもいいことかもしれない。
異国の文化を通し、人間の記憶に関する瞑想ともいうべき、
「生の存続の二極地」という、日本とアフリカを結んだ映像の交差する
不思議な旅行記ともいうべく作品を見ていこう。
アイスランドの三人の少女の映像から始まる冒頭。
それを「幸福の映像」と呼んでみるわけだが、
どうも他の映像にうまく馴染めそうもないと悟って、
マルケルはそこに黒い画面を挿入する。
そして、こう続ける。
「幸福がかいまみれなかったとしても、黒だけは見えるだろう」
この冒頭のカットをみて、僕は確信する、
少なくとも(表層にはびこる)嘘や欺瞞に出くわすことはないのだと。
まさに僕はこの詩的な感受性に胸踊らされてきたのである。
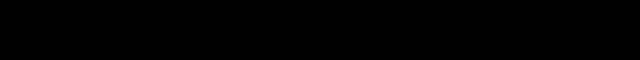
だから、僕もそれに倣って、ここに黒の一行を挿入しておこうと思う。
この至福の映画ついて、言葉を使ってうまく語りつくせる自信はないが
その意趣を汲み取れなくとも、黒のラインだけは見えるはずだと。
そうやって、函館から青函連絡船へと乗り込こんだカットに移ってゆく。
ここからの映像は、報告者たるこの旅行者の眼差しとして語られる、
いわばポエジーの発動による終わりのなき絵巻物である。
アイスランドに始まり、日本を経由した旅行者は
途中断続的にアフリカの映像を挟み込み、
あるいは、ヒッチコック『めまい』を思い出して
サンフランシスコへと巡礼する。
この時空の旅行者の想念はまるで自在だ。
その旅行者からみたテクノポリス東京は、
21世紀をすでに5分の1ほど経てしまったが、
実にノスタルジックでさえある。
のちに小津安二郎へのオマージュとして撮られることになる
ヴェンダースの『東京画』にも言えることだ。
これを見れば、『東京画』は明らかに、
この『サン・ソレイユ』を踏まえ構想されているのがわかるのだが
『サン・ソレイユ』にしても、
ロラン・バルトが書いた『表徴の帝国』を踏襲するかのように、
日本の中心が、「皇居」という空虚な空間のみならず、
胸ときめかせるものののリストとして点在し、
魅力的なざわめきとして映り込んでいるのを発見してゆく
中心探しのゲームとしての面白さがあるように思う。
しかし、この国で、中心など一向に見当たらない。
異次元の世界への眼差しは、好奇に満ちてはいるが、
西洋人からみた、この日本という国、
とりわけ東京という街に潜む謎や神秘への洞察は
単に、理屈や気の利いた言葉だけでは到底割り切れまい。
それには詩情を以て応じるほかない、ということの証なのだ。
この夥しい記号への謎解きには
催眠効果すら潜んでいるように、
言うなればポエジーの魔法がかけられている。
こうして、マルケルは、清少納言が
リストづくりへの嗜好に胸躍らせたように、
この東京で「胸をときめかせるもののリスト」として記憶を開示し
独自の物語を密かに編み上げてゆくのだ。
その視線の先、まず最初に焼き付けられたのは
招き猫発祥の地豪徳寺にやってきて、愛猫の死を悼む夫婦を前に、
その愛猫トラは死んだのではなく、旅に出たのだと投げかける。
そして彼らの思いを「時間の裂け目を縫い合わせる儀式」と呼ぶ。
しかし、映像に映り込んだ東京の、
すでに失われた時間とアイコニックな情景たちは、
我々日本人でさえ、その記憶の移ろいの中で
実直なまでの、郷愁を掻き立てられずにはいられないものばかりである。
それらは、レヴィ=ストロースが「日本の秘密と名指した」という、
「もののあはれ」の哀愁として嗅ぎ分けられた内なる声だ。
数寄屋橋交差点で演説を振るう愛国党の赤尾敏、
代々木公園に日曜ごとに踊りにやってくる竹の子族。
テレビの画面に妖怪と現れる美女夏目雅子。
モグラ叩きやパックマンといったゲーム。
ジャイアントパンダ、カンカン、ランランの死。
そういった象徴は、我々には今では遠い昔の記憶の遺品になってしまった。
旅行者の目に「電線で縫い合わされた都市」だと映るこの東京の、
その電車の中に、本を読む多くの乗客たちをみて、
外でしか本を読まないか、読んだふりをしているのかと驚きを禁じ得ない。
しかし、それは今となっては、僕ならこう切り返せるのだ。
それはあくまで、手持ち無沙汰の証であり、
貧乏性的退屈恐怖症の裏返しなのだと。
今や、電車の中で手にするものは、本や漫画、新聞などではない。
知への欲望でもない。
それらは瞬く間にスマホの普及によって、
他者と交わることのない視線と親指の戯れに
とって変わってしまったのを知っている。
文化は継承されるが、同時に喪失もする。
そして、新たな神話が形作られてゆくのだと。
途中、マルケル自身の友人である山猫駿雄なる映像作家による
タルコフスキーへの敬意と称された映像「ゾーン」を挟みこむ。
過去の映像に大胆なエフェクト処理を施した「空港闘争」の映像、
そして、マイケルの大好きな猫とフクロウをもインサートするが、
次第にエスカレートした映像は、「太平洋戦争」の特攻隊までをも処理してしまう。
が、マルケルの眼差しには、どうしても豪徳寺で見た、
あのトラという名の猫の死に哀悼の意を示す光景にフラッシュバックし、
いみじくも真珠湾攻撃の合図となった暗号「トラトラトラ」の記憶にかぶせ合わせる。
彼はいう、「自分の惑星の過去に不幸が存在したということが耐え難いのだ」と。
そして、トラのために祈りを捧げる。
「魂が安らかでありますように」と。
最後に、再びアイスランドの三人の少女の映像へと回帰する。
そこでは日本でみた初詣や成人の日のセレモニーを経たあと
「どんど焼き」の火祭りとを重ね合わせる。
「どんど焼き」とは、正月飾りや御札などを炊き上げる
言うなれば浄化の儀式であり、
マルケルの言葉を借りれば「もののあはれの最終段階」でもある。
「(無くしたり、壊したり、使い古したもの)全てとの別れが、
儀式によって崇高なものにされる」と続けるマイケルは、
この一度捨てたカットを「崇高なもの」へと押し上げるために挿入する。
しかし、映画は崇高さをいつまでも映し出しはしない。
次の手紙を待たずして、映画は終わる。
現実と虚構に挟まれた、異国の幸福の記号と記憶への弔いが終わる。
ここで、もう一度、黒い一行を挟んでおこう。
この先何も見えない世の中で、この黒い一行だけは不確かさを確かなものに変えてくれるはずだ。
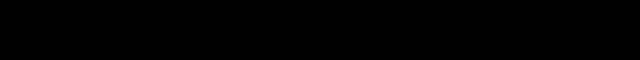
最後に、クリス・マルケルについて、少し触れておこう。
1921生まれだから、今年で生誕100年を迎えたわけだが
すでに2012年に他界している。
盟友ゴダールよりも9歳も年上の兄貴分ということになる。
その名もクリスチャン=フランソワ・ブッシュ=ヴィルヌーヴ、
大のメモ魔であることからMARKER(マルケル)と呼ばれ、
れっきとしたサルトルの薫陶を受けた門下生である。
ストップモーションによるスチールとナレーションで
「フォトロマン」と称されるジャンルを打ち立てたマルケルは
ゴダールの『アルファヴィル』、あるいは
テリー・ギリアム監督による『12モンキーズ』の原案ともなった、
SF短編映画『ラジュテ』によって、その名声を博すのだが、
主に、世界中を飛び回り、その関心を哲学的視座で捉えた作品を発表してきた、
主に、社会主義国家を中心としての、
フォトジャーナリスト、ならぬ映像ジャーナリストでもあった。
中でも特筆すべきは
このクリス・マルケルは、他でもない、日本という国への愛着を
ことごとくその映像で語ってきた稀有な映画作家なのである。
『サン・ソレイユ』の原型は、東京オリンピック最中の高度成長期
満州生まれ一人の日本人女学生の眼差しを借りた
『不思議なクミコ』中にすでに懐胎されていたが、
この『サン・ソレイユ』を経て、日本人ですら目を向けようとしない
ディープなオキナワ戦をめぐる歴史映画『レヴェル5』
あるいはヌーヴェル・ヴァーグ派にとっては、
少数派に過ぎない黒澤へのオマージュ『AK』といった作品を通し、
独自の視線を投げかけてきた。
そのスタイルは、ドキュメンタリーという枠を超え、
旅と記憶と観察と哲学によってもたらされた深い洞察を駆使し、
あらゆるジャンルを横断し、クリエーターたちに影響を与えながら
新しいジャンルを確立したといってもさしつかないだろう。
その意味では、ゴダールに引けを取らぬ、映画のイノヴェーターであり、
革命を宿した真の映画作家であった。
そんなマルケルは、インタビュー嫌いで、
プライベートも謎に包まれた存在として知られている。
クリス・マルケルの残された映像から、読み解くしかない。
しかし、今、閉塞的なこの日本の状況下で、
もっとも必要な視点というのは、
物事を内から見つめる内省的な視点ではなく、
マルケルのような視座を持って、不透明なものに
誤解を恐れず切り込んで光を当ててゆく、
そうした開かれた他者の眼差しに他ならないのだという気がしている。
少なくとも、この不思議な映画作家の映像エクリチュールは
そのことの重要性を教えてくれているのだから。
YMO:Technopolis
YMOの「Technopolis」。あの頃、この曲をリアルタイムで聴けたのは実に幸福な体験だった。仮にクリス・マルケルの映像にこの曲が紛れ込んでも全然違和感はないし、むしろ、はまってしまうことだろう。幸福の電子音を人間が弾き出しているところに、未来を感じたものだった。


![[門戸無用]MUSIQ](https://lopyu66.com/wp-content/uploads/2020/11/misiq-1-200x200.gif)










コメントを残す