寒い冬の日に、部屋で一人静かに聴いていたいコレクション
NORTH MARINE DRIVE:BEN WATT
せいか:羅針盤

透明で、シンプルで、それいてどこまでも深いアコーステイックな響きの中に一度迷い込んだら、二度と帰れなくなってしまうような、そんな深遠な音楽体験と呼びたくなるものがここにある。
フォークであれ、ネオアコであれ、ポップ・ミュージックであれ、山本精一という人の持っている、この歌ゴコロに匹敵しうる純度の高い日本の他の音楽を僕は知らない。
それはこの羅針盤や山本精一が紡ぎ出す音だけで十分とも言える。換えの利かぬオンリーワン。
ラストを飾る「COLORS」で拾われる音と色たち。
この壮大な音風景は、凍てつくほど厳しい冬の中でさえ
凛とした美しい永遠性が横たわっている僕の冬のテーマソングである。
Another Day on Earth:Brian ENO

かれこれどのぐらい飽きずにブライアン・イーノの音楽を聴き続けているのだろうか?そして諸々の哲学を教えられたであろうか?アヴァンポップな歌モノから、定番のアンビエトミュージック、そして関わったプロデュース作品に至るまで、
一貫した、音への造詣の深さのなかの実験性はいざ知らず、
体内の中に染み渡ってゆく良薬のような音の連なりに安心して聞き入っている。
2005年にリリースされた28年振りのヴォーカル・アルバムは
まだ明けやらぬ夜明け前の静けさ、透明さ、冷たさに支配された冬の気配にナチュラルに溶け込んでゆく。
HATS:The Blue Nile

冬になると必ずと言っていいほどこのアルバムを聴いている。
スコットランド出身、ブルーナイルは、いかにも伝統のイギリス文化のエッセンスをにじませながら、上質のエレクトロニクス感を嫌味なく駆使し、クールながらも、じんわりとそのエモーションを伝えてくる。
実に通好みのロマンティシズムがある音楽だ。
ウオームハートでありながら、どこか寒々した情景が浮かび上がる青の世界。多くのミュージシャンに支持され、ミュージシャンズミュージシャンでもある彼らの音作りは、佳作とはいえ、流行など無縁の世界は、ひたすら自分たちの信じる歌を作り続ける貴重な職人芸を披露している。
Somewhere Called Home:NORMA WINSTON

ノーマ・ウィンストンのECMでのリーダー・デビュー作は、レーベルでは貴重なヴォーカルアルバムだが、いわゆるジャズヴォーカルものとは趣きが違う。
ジョン・テイラーの叙情的で現代的ピアノに、トニー・コーの乾いたクラリネットの音の洗練された佇まいが北欧の静寂と光に包まれた、まさにジャケット写真そのもののような情景を伝えてくる。
数あるECMの名盤のなかには、こうした冬の景観をイメージさせるような、そんな音楽がたくさんあふれているが
このアルバムは個人的琴線に触れる、冬のクラシックモダンミュージックと呼んでいる名盤だ。
NORTH:Elvis Costello

その名も『NORTH』にはコステロのロマンティシズムを感じる。この頃から伴侶になったダイアナ・クラールの影響もあるのだろう。静謐で、ジャッジーなスタンダードな名曲ぞろいのアルバム。
バカラックとの『Painted From Memory』も外せない一枚だが、ここは一つ、地味な方を取り上げておこう。
Out of Noise:坂本龍一

教授自体の興味やこれまでの楽曲を聞けば、当然モンドな音はいくらでもあるのだが、このアルバムにはチルな要素とモンドの要素に実験性と宗教的な空気さえ漂う。
フィールドワークによる音なども取り入れながら、
コンテンポラリーなアンビエントミュージックとして
教授の活動の新たな方向性を端的に示したアルバム。
DOWN SOUTH:Steinar Raknes

ウッドベースに引けを取らない大きなガタイのスタイナー・ラクネスは、シンプルなアメリカンルーツミュージックのようなスタイルで、ベース一本で、渋い歌を聞かせてくれる世界を行脚するミュージシャン。
最初にラジオで耳にしたのは、ヨイクという民族音楽のユニットだったと思うが、その歌に聞き惚れてライブに足を運んだのも寒い冬だった。
ところが相棒がパスポートの関係で入国できず、良いくは聞けずじまい。結局スタイナーのソロを見ることになったが、
これがこれで悪くなかったのである。
Songs From the Cold Seas :Hector Zazou

ビョークから加藤登紀子まで、実に幅広いシンガー達が
エクトル・ザズーのエロクトロニカにのって
北極圏の民族音楽歌う、コンセプチュアルアルバム。
聴いているだけで、身が引き締まるような、
全編にわたりそんなひんやりした空気が張り詰めているが、
それぞれに物語性というものが聞こえてきて、
子供のように、ドキドキ、ウキウキしてしまう自分がいる。
At The Golden Circle Vol.1 : Ornette Coleman

音で冬を連想する、というようなものではないのだが、
ジャッケットに釣られて、つい聴いてしまう冬の音楽、と勝手に位置づけしている。この『At The Golden Circle Vol.1』はライブ盤であり、高揚感は、寒さに対抗するものたりうる絶対の指針だ。フリージャズに分類されるとはいえ、そんなに耳障りなものではないと思う。聴きやすい部類のフリージャズのような気がする。
これは1965年12月3日と4日の二夜にわたる、ストックホルムのギレンシルケルンジャズクラブでの演奏を収録したもの。
これをフリージャズとして聴く聴かないは自由だが、スタンダードで耳障りのいいものばかりがジャズというわけではない。
デビッド・アイゼンソンのベース、チャールス・モフェットのドラム、この北欧リズム隊がバックで、オーネットの奔放なアルトサックスを見事に支えているトリオ演奏は、豪雪の森林地帯を勇敢に管理する歩哨のようなたくましい強さとハーモニーがある。

![[門戸無用]MUSIQ](https://lopyu66.com/wp-content/uploads/2020/11/misiq-1.gif)




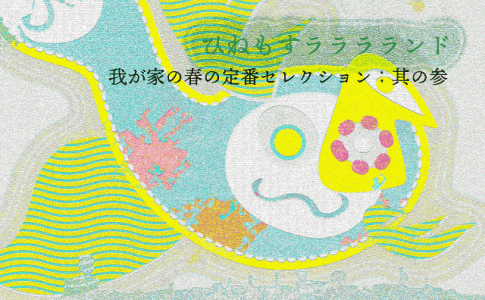






このアルバムとの付き合いも随分と長いが、いまだ飽きがこないね。何だろうか、人生の一番楽しかった時期に出会ったアルバムだったからか、いや、そんな単純な理由づけをしたくはないが、ネオアコブームの火付け役、ベンワットのデビュー作であり、トレーシー・ソーンの『A Distant Shore』とともに、
のちのEBTGへと続いてゆく彼らの原型がここにある。
永遠に聴き続けたい音楽、歌というのが、
時代の思い出、個人的な思い出がこの一枚に詰め込まれたような、懐かしく、苦く、甘く、気だるい響きとともにズキュンと胸に響くのだ。