音楽界の隠遁カラス、スコット・ウォーカーの歩みを振り返って見よう
ノエル・スコット・エンゲルこと
スコット・ウォーカーが亡くなってはや二年近く、
忘れれられた、というわけでは決してないだろうが
時の移ろいの前に、人はなすすべはない。
そこで、この巨人の軌跡を、自分なりに追っておきたい。
4ADレーベルの訃報によって、
彼が妻帯者であり、孫までいることを知って驚いたものである。
もともとひっそり孤高にそびえ立っていた山に
いまさらながら立ち入り禁止の立て札を見つけたような
そんな改まった禁断の驚きは決して似つかわしい賛辞ではないだろう。
肉や箱を叩いたりする実験的な音作りを追求する音楽家で
これほど玄人受けする人も珍しいのでは、と思う。
トム・ヨークからレディオヘッドのプロデューサー、ナイジェル・ゴドリッチ
あのボーイ・ジョージ、そしてマーク・アーモンドを始め、
イーノやボウイといったお御所すらも絶大なるリスペクトを掲げている。
その他、数えきれないオルタナティブ系アーティストたちが
スコットに魅了され、今尚多くの追悼の声を送り続けた。
記事などで逐次目にするにつけ、
その思いが自ずと増して確信に至るのだ。
個人的には初めて意識した、
マーク・アーモンドがカバーしている「JACKY」が
その入り口となったのを思い出す。
なんとドラマッチックなサウンドであることか。
オリジナルの方はさらにサウンドがにぎやかで
実にエモーショナルなオーケストラレーションが感動的ですらあった。
もっとも「JACKY」はフランスの歌手ジャック・ブレルの曲で
スコットはそれをカバーし、
それをまたマーク・アーモンドがカバーしていたわけだった。
オリジナルではなく、そのカバーに触発されるのだから
よっぽどスコットの楽曲にたまらない魅力があるのだろう、そう思った。
なによりもあの声が素晴らしい。
神々しいまでにゴージャスなクルーナーで
歌うことに終始こだわった実験的ポップシンガーとして
ひたすらアルバムを作り続けた信念の人。
ポップミュージックから前衛的、非ポップ圏のアーティストへと
転身したミュージシャンとしては
その声質まで同化して来た感のあるデヴィッド・シルヴィアンが浮かぶが、
彼もまた、その信奉者のひとりで、いつだったか
コラボレーションアルバムを制作するという話まで持ち上がったらしい。
残念ながらプロジェクトは実現しなかったようだが
実現していたら、きっと興味深いものができ上がっていたはずだ。
未発表テイクなどが残されていれば、と思うのだがどうだろう?
ウォーカー・ブラザーズを離れたソロ作品
スコット1〜4の間に成熟した音
とりわけ文学的な世界が構築されているが
スコット・ウォーカーの転機は
何と言ってもウォーカー・ブラザーズ再結成での『Nite Flights』だろう。
このアルバムはかつての人気を誇った
ウォーカー・ブラザーズのムードからは程遠い
アダルトコンテンポラリーサウンドで
のちのスコット・ウォーカーダークサイドへの
入り口とみなしていいだろう。
ちなみにこのアルバムを聴いたイーノが嫉妬したというほどで
それをボウイに紹介したことで
ボウイは、この『Nite Flights』の
タイトルチューンをカバーすることになった上に、
その後、ドキュメンタリー映画
『スコット・ウォーカー 30世紀の男』の
エグゼクティブプロデューサーとして関わることになる。
かくしてここから先に進むスコット・ウォーカーは
脱ポップミュージック、脱ポップシンガーのいばらの道を
ひたすら歩み続ける孤高の人となるのだが、
1984年にヴァージンレコードからリリースされた『Climate of Hunter』は
ソロ転身後、公の場で歌うことを放棄した
スコットの強い意志が込めれているように思う。
が、今聴くとそれ以後のさらに難解なゴシックホラーのような
サウンドストラクチャーに比べれば
それでもまだ聴きやすさを残してはいるのである。
が、そこから1995年リリースの『Tilt』から『The Drift』
『Bish Bosch』と続く三部作に至っては
もはや他の追随を許さない独自路線に拍車がかかり
これがあのウォーカー・ブラザーズで
キャーキャーと騒がれ黄色い声を浴びていた
アイドルスコット・ウォーカーか、と思わせる内容で
自ずと聴くタイミングを考えてしまうほど
晦渋な音の世界を構築するに至る。
もっとも、この時点ですでに
孤高のアーティストとしてのポジションを確立しており、
レコーディングアーティストとしての強い意思をもって
ひたすら闇の中をロウソクの炎を頼りに歩む仙人のように
まるで一本の映画や一冊の文学のような深淵で
確固たる内なる世界観が提示されていたのである。
音も難解だが、その歌詞はさらに難解を極める散文詩ばかりで
正直、和訳を読んでもさっぱりよくわからないものばかりである。
解剖学やら生物学系の用語、あるいは造語であったりと、
かつてベルイマンの『第七の封印』などに
インスパイアされていた文学的な歌詞からでさえも
さらに次元を飛び越えたこのポエジーの洪水は
ネイティブですら理解を超えるようなものが多く
英語に気おくれする国民には到底扱える代物ではない。
もっとも、そうした難解なるコンテポラリーな詩人でもあったスコットにも
相変わらず映画音楽のオファーなど、
その唯一無二なる世界への関心は続く。
1999年にはレオス・カラックス監督の『Pola X』
あるいは2016年ラディ・コーベット監督『シークレット・オブ・モンスター』や
いみじくも遺作となった2018年ブラディ・コーベット監督の『Vox Lux』まで
この特異な音楽家の深淵なる音の叫びが
どこまでも熱狂的支持者たちの心を掴んではなさないのだ。
そんなロック界の変わり種スコットだが
93年フランス映画イザベル・アジャーニ主演の
『TOXIC AFFAIR(邦題:可愛いだけじゃダメかしら)』
の主題歌と挿入歌を歌っている。
曲はクストリッツァとのコンビで知られるゴラン・ブレゴヴィチ。
このあたりでポップ路線への回帰を期待したが
スコット・ウォーカーのゆく道が今更ブレるはずもなく
かつてないほどに強固になってゆく。
その最たるものが、2014年リリースの
シアトルのドゥームメタル / ドローンバンド、
サンO)))とのコラボ『Soused』ではないかと思う。
漆黒の闇に射す一筋の光を求めて彷徨う魂の邂逅。
恐ろしいまでに狂気を秘めた音響と声による
深淵なるゴシックロマン。
誰も近づくことができない深みに達して
もはやそこには人の気配がない。
『Climate of Hunter』以来
スコットをサポートし続けてきた理解者で
プロデューサーのPeter Walshとともに作り上げた
スコット・ウォーカーの、一つの完成形がここにある。
それから5年後の訃報。
スコット・ウォーカーは自らのサウンドの深みに
どこまでも入って行って
帰ってこれなくなってしまったのかもしれない。
あまりにも深く、声の届かない世界へ。
あなたは本当に身を隠してしまった。
さようならノエル・スコット・エンゲルよ。
あなたの声はゴージャス過ぎて
決して子守唄にはならないけれど、
それでも、さすらう魂の標べとして
永遠に聴き継がれてゆくでしょう。
安らかなれ。




![[門戸無用]MUSIQ](https://lopyu66.com/wp-content/uploads/2020/11/misiq-1-485x300.gif)
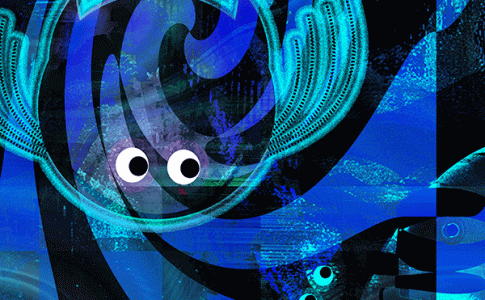







コメントを残す