蛇を睨んだど根性ガエル、この理由なき豊かさへの反抗
ショーケンについての思いをしたためる上で、
このところ、『傷天』を熱心に見返していたのだけれど、
このドラマはショーケンのショーケンによる
アウトローっぷりが見事にハマった作品ではあるものの、
“相棒”である弟分アキラ演じる水谷豊のことが
どうしたって無視できない。
そのことに無自覚な傷天ファンなどいないと思うのだが、
アキラあってのオサムであり、
オサムにとって、アキラは単なる弟分という役割だけでなく、
精神的ホモセクシャルな関係とさえ読み取れるドラマである。
つまり、それほどまでに二人の絆は深く、
だからこそ、最終回における弟分のあっけない頓死っぷりが
時を経ても大いに記憶に引っかかり続けているわけである。
まさに表裏一体の関係。
よって当然、この水谷豊という俳優を
取り上げずにはいられない流れになってしまった。
そんな前提ありき、ではあるが、
水谷豊は水谷豊で、やはり魅力のある俳優に違いはないのだ。
実を言うと、晩年のショーケンには
そのオーラも幾分薄らいでおり、全盛期ほどの関心も持てぬまま
言い方は少しシニカルかもしれないが、
「過去の人」っぽい感じで受け止めていたフシは否めない。
反対に、この水谷豊に関しては、
傷天当時の、若く、ギラギラ脂ぎった感じからは
今では随分洗練された大人の雰囲気を漂わせてはいるが
いい意味でうまく熟成され成長を遂げてきた感じが滲み出している。
そのことが一定の支持のもとに
あの「相棒」でのロングランにも通じているのだろう。
あの特命課、杉本右京という刑事のキャラクターには
そうした過去を引きずる面は薄いが、
それでも、どこかで、あの水谷豊が
チラホラ見え隠れする瞬間が時折あって嬉しいわけだが
やはり70年代に見せたあの野犬のような、
あの水谷豊像がどうにも忘れられない。
そんな水谷豊の代表作は何と言っても
長谷川和彦の『青春の殺人者』の両親殺し役
あの「じゅんちゃん」であり、
また、もう一つはNHK土曜ドラマの名作、
山田太一脚本の『男たちの旅路』のガードマン役
杉本陽平もまた、強く印象に残っているが、
この頃の水谷豊は鬱屈した若者の感性を
どこかでリンクした雰囲気の役柄が目立っており、
それがイメージを形取っているのは言うまでもない。
ちなみに、水谷豊の出世作はといえば、
何と言っても『熱中時代』における北野広大、
通称北野先生、であるが、あえてスルーする。
それを含め俳優水谷豊像なのは間違いないが、
やはり、水谷豊を語る上で、
アウトローの弟分として『傷天』で培った
野性味溢れる雰囲気をうまく引きずりながら、
核となる、生真面目な中にも抑えきれない人間的な狂気が見え隠れする、
あの時代の空気と見事合致した、
行き場のない若者としての声を
惜しみなく代弁している作品に向かってしまうのだ。
『青春の殺人者』で思い出されるのは、
父殺し、母殺しと言った重いテーマ以前に、
その居場所のなさを、将来を信じきれないあの無軌道な若者の姿を
虚無の殻に収まることなく
反クールに演じて見せた等身大の若者像である。
親に敷かれたレールを否定したい一面と
過度に甘やかされた飽食の時代の間で
矛盾と葛藤を繰り返したのは、
何も、この主人公順だけではなかったはずなのだ。
少なからず、こうした事件は場所を変え、
形を変え世間を賑わしていた時代だ。
これも多分にもれず
昭和49年に起こった「市原両親殺人事件」という実話を元に書かれた
中上健次の短編「蛇淫」を、大島組の田村孟が
ゴジこと長谷川和彦のデビュー作の為に脚本を書き、
ATGによる配給の下でキネマ旬報ベスト・ワンを獲得している。
この映画、水谷豊の魅力について書き進める前に
あらかじめ二つのことを言ってからじゃないと始まらない。
一つは度胸の座った原田美枝子の眩しい存在感。
若干17歳にして、流石に初々しいところは多々あるが、
水谷豊の恋人として、実に対等に渡り合っているあたり
なかなかの大物ぶりを発揮している。
オープニングにおける二人のたわいも無い戯れなどは
ヌーヴェル・ヴァーグ的な雰囲気がするし、
「ペニス傘もちホーデンつれて入るぞヴァギナのふるさとへ」
これを教養だとひけらかすあたりが実に小悪魔的だ。
けれども一途な愛で、
「じゅんち〜ゃん」とメス猫のように主人公を追い回すケイコが愛しい。
大胆な裸体を惜しみなく晒し、
まさに体当たりの演技が目を惹くが、当人はこれをひどく嫌って
見返すことなど一切ない作品だという。
そんな彼女には、「あの頃の君はピカピカに光って」
などと思わず口ずさんでやりたくなるが、
そこは花も恥じらうセブンティーン。
心のひだまではわからない。
原田美枝子というと、その後は順調に女優として
成長を遂げてゆくわけだが、
勝新にも随分贔屓にされたし
この同年、増村保造の『大地の子守唄』という傑作も残しており、
名実ともに実力俳優へと駆け上がってゆく萌芽が見てとれる。
今、これほどまでに肝の据わった若手女優がいるだろうか?
そう思わせる、まさに時代の申し子であった。
それと、もう一人は市川悦子である。
「家政婦は見た」どころじゃないこの真の狂気。
もう、水谷豊をほっておいてでも、この女優について、
延々書き進めていきたぐらいに凄まじい熱演を見せている。
前半、息子である水谷豊が父親である内田良平を
殺した後に始まる母親とのバトルは
この映画の骨子とも言えるなかなかのハードシーンであり、
セリフから表情、存在感においても
圧倒的な迫力で、あーだこーだとわめきたち
のたうち回る様がリアルに恐ろしい。
一挙手一投足、どことなく舞台出身の芝居という重力がのしかかるが、
その反面、何かおかしくて笑い転げるような間が
血海に佇むキャベツのようにゴロリと挿入されていたりして
そのアンバランスな気配にぐいっと引き込まれる。
まるで、二人だけの舞台を見せられているような
そんな濃密な演技はやはり市原悦子をおいて、真似できない。
これだけを見ても、この女優が只者ではないことがわかる。
そんな彼女に心奪われてしまうほどだが
だが、あえて、その思いは封印するとする。
市原悦子に関しては、追悼の意味で、
それはそれで新たにページを割くとしよう。
さて、今一度話を水谷豊に戻そう。
実話では両親殺しの息子は犯行を否定している。
実際のところ、真実は闇に葬られているが、
れっきとした40年を超えた死刑囚として、
今尚その運命を獄中で過ごしている。
つまりは冤罪の可能性を持った事件であるが
映画はそうした事実を検証しているわけではない。
あくまで、こちらは実話を下敷きにした、
別の物語に書き換えられている。
長谷川自身は何も、現実の話に食い込む形で
真実をあばき出したかったわけじゃなかったはずだ。
ちなみに、田村孟の脚本を大いに逸脱し、
中身を変えてしまった長谷川の志との間に、
当然軋轢は避けられなかったというから、
現場の不穏な空気は想像に難くない。
しかし、結果として撮り終えた作品は
デビュー作というハンディを差し置いても
実に長谷川和彦らしい「毒×痛快(一回涙)」
というような表現になっている。
いみじくも、次の『太陽を盗んだ男』から今日に至るまで
40年近くの歳月を一歩も踏み出せず、
長く引きこもりを続ける未完の映画作家が
次に自分が取りたい映画とは、という質問に応えた言葉がそれである。
親の敷いたレールの軌道に抗いつつも、
行き場もなく、また、愛着や不安定でいっぱいの鬱屈した若者。
現実を直視できず、不条理に流されてゆくのは
愚かでありながらも、どこかで共感してしまうような、
それを全て若気の至りで一括りにしたくもないが、
この水谷豊は実直に、正面から対峙してみせる。
この辺りは、やっぱり、傷天で見せた、
ショーケンに必死についてゆく子犬のような
人懐っこくも、情けなく、女々しく、
それでいてどこか憎めない、甘えん坊の青二才っぷりを
体当たりで演じてきた水谷豊ならではの野性味なんだろう。
確か、「傷天」のプロデューサーだった清水欣也は
ショーケンにジェームス・ディーン像を重ね合わせてみていたけれど、
この『青春の殺人者』を見れば
それはむしろ水谷豊の方だったのかもしれない
そう思わせるものがここにはある。
現に、長谷川和彦はその『理由なき反抗』のジェームス・ディーンを
当時の水谷豊に託したかったのだ。
そういって『傷天』の乾亨が抜擢された青春の一頁なのである。
とはいえ、劇団ひまわりの子役から始まって
俳優を生業とすることに自信が持てずに試行錯誤を繰り返しながら
不遇の時代をへて至ったこの道程を慮るに、
自分に取っては水谷豊=ジェームス・ディーンというよりは
むしろ、青臭いカエルだが
どこか根性の座ったど根性ガエルになぞらえておきたいのだ。
ちなみに、ドラマ『熱中時代』には触れなかったが、
明らかに『傷天』の影響下の元に、
70年代後半、一世風靡した松田優作主演のドラマ
『探偵物語』第5話「夜汽車で来たあいつ」に
ゲスト出演した水谷豊は、『青春の殺人者』で共演した
原田美枝子の兄役で再会を果たしている。
もっとも、ドラマゆえに、
中身はそれなりにこじんまりまとめられており、
特筆すべきものでもないが、
どちらかといえば、北野先生の延長上にある、
真面目な地方公務員が上京して、妹の足取りを追うストーリーで
むしろ、私生活でも仲の良かった
松田優作との交遊ぶりの方がメインで楽しめる。
それはそれで素の水谷豊像のような気がして微笑ましい。
ちなみに、サウンドトラックはゴダイゴが担当。
長谷川自身はビートルズの楽曲を要望したそうだが、
使用料で予算がオーバーするとのことで
ゴダイゴに食指が伸びたのだという。
このアルバムでは全て全曲英語詞で歌われているが、
それも当時の傾向としては珍しいが、
ATGにしては、極端にアヴァンギャルド寄りにもならず、
青春の面影を残した楽曲に好感は持てる。











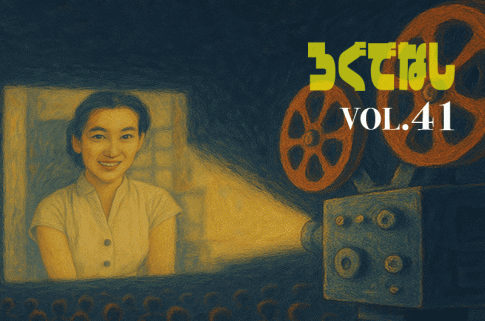

コメントを残す