前衛はどこまでポップたり得るか?
あまりに前衛すぎる音というのは、
通常の感性を持ってすれば
どこまで聴くに耐えうるのか、という指標のもとに
ただの拷問のように感じるだけのものかもしれない。
たとえば、ルー・リードに
1975年突如発表された『METAL MACHINE MUSIC』という
騒音の洪水が延々繰り返される異色作があるが、
当時、買ったばかりのレコードに針を落としても
全くのところわけがわからない。
通常とは異なるサウンドだから
物珍しく、刺激的だという思いはあったものの、
以後それを熱心に繰り返し拝聴した記憶はない。
しばらくして、売り飛ばしてしまったほどである。
つまり音楽的価値でいえば、
ノイズミュージックの先駆けといった、何か付加価値はあるにせよ、
文字通り、音を楽しむものだとしたら、
それは極めて耳には背徳的過ぎたのだ。
とはいえ、圧倒的な前衛なるものを前に、
根底にあるカオスを体感する快楽の誘惑もある。
たとえば、短い楽想を840回繰りかえせよ、と意図された
エリック・サティの『ヴェクサシオン』などに見られる、
退屈でありながらも、決して解放されることのない無限の虚無のなかで
病的なまでの脅迫的な観念に
自ら身をなげることなのかもしれない、とも思う。
そうしたものを素直に肯定し、
わざわざアヴァンギャルド礼賛を唱えるつもりはない。
が、自分としては、音のアヴァンギャルドであっても
どこかでPOPであって欲しいと思うし、
言うなればURBAN POPとしてのAVANTGARDEの可能性を
支持するものである。
アヴァンポップとしての音の膨らみにこそ期待しているのだ。
この辺りが、せいぜい我が琴線に触れてくる認識の限界でもある。
革新的で、実験的なものが、その衝撃を無視して
棚の片隅にしまいこまれたままになっているのは、本質ではない。
が、そこから日常の刺激の源泉として、
常に身近になければ神の啓示にすら届かない。
アンダーグラウンドに眠る黒いダイヤモンドたちは、
たとえ鈍くも、磨けば磨いただけ、いくらでも光る代物なのだ。
そうして、だれかがひとたび陽の目にさらすことで、
それらアヴァンギャルドは、揚々たる前線に躍り出ることになる。
そんな趣ある前衛的な音楽をここに10枚抽出してみたい。
B2-UNIT : Ryuichi Sakamoto
FLOWERS OF ROMANCE:Public Image LTD

パンクから真のオルタナへと、衝撃的な転身を見せ、世のロック信者たちを唖然とさせたジョン・ライドン。
のちの活動を今日まで追って見れば、初期活動において、
ベースのジャー・ウーブルとギターのキース・レヴィン、この限りなくフリーキーで、テクニカルにも長けた音の共犯者たちの力無くしては成立しないのがよくわかる。
そのことを見事に証明した『METAL BOX』という金字塔から、片腕ウーブルが脱退したあと、さらに進化した形で衝撃を放ったのが続く『FLOWERS OF ROMANCE』。
打楽器中心のプリミティブかつ強力なリズムをバックに、
呪詛的なヴォーカルとともにポストロックにふさわしい80年代の幕開けを告げた革新的アルバムである。
Trout Mask Replica:Captain Beefheart

先の企画カプリコーンズの偉人の一人でもあるドン・ヴァン・ヴリートこと、キャプテン・ビーフハートはあのフランク・ザッパとは高校時代の友人。そのザッパがプロデューサーとして関わったこのマジックバンドとしてのファーストアルバムが
『Trout Mask Replica』である。
サイケデリック、エクスペリメンタル、オルタナティブ・・・
カテゴリーはこの際、どうでもいいが、その方法論も、残された音も、全てがまさにビーフハートの即興的直感の元に、
既成の音楽理論を破棄した道標で、以後オルタナシーンに多大な影響をもたらしながら、今尚強烈なその個性の輝くを失ってはいない。MR.アヴァンギャルドここにあり。ジャケットのキワモノ感も秀逸だ。
Ein Buendel Faeulnis in der Grube :Holger Hiller

Palais Schaumburg時代から注目していた、ジャーマンニューウエーブの才人ホルガー・ヒラーの最大のヒット曲『JOHNEY』を収録したファーストアルバム。(徳間ジャパンからリリースされた邦題は確か『腐敗の坩堝』だったっけな)
実験的ながらもキュッチュでポップなサウンドコラージュで、
おもちゃ箱をひっくり返したような音の断片が幾重にも折り重なった奇妙なハーモニーを聴かせてくれる。昨今の、どこか観念的エレクトロニカにやや食傷気味の耳には、むしろ、新鮮で胸躍るものがあるかもしれない
Taking Tiger Mountain:Brian Eno

麗人とまで呼ばれて異彩を放っていたロキシー時代のイーノから一転、ソロになってよりエクセントリックぶりが加速した。
まだ、アンビエントへの傾斜以前のロックテイストが色濃く反映されてはいるが、東洋的なシノワズリ音階、あるいはアバンギャルドとポップの融合を試みたイーノブランドによるポップ・ミュージック確立への萌芽が見て取れる。
友人であり画家であったピーター・シュミットの指示カードであるオブリーク・ストラテジーズというカードの方法論によって方向付けられたコンセプチュアルなアルバム『Taking Tiger Mountain』は、文化大革命時の京劇からタイトルが取られているように不思議な異国情緒さえ漂わせている。
This Heat:This Heat

THIS HEAT、記念すべきファースト。
実験的といえばこれほど実験的なポップ・ミュージックもないだろう。この音の先見性、革新性。
もはや今更言葉を重ねるまでもないことだが、
今日のあらゆる実験的サウンドの基礎が、このなかにどこまでも原初的に詰まっている気がする。
これをポストパンクだのオルタナだの、なんだのと薀蓄がましく語る暇があるなら、ただひたすらその音の洗礼を浴びるべし。すべてはそうしてはじまるのだ。
Bitches Brew:Miles Davis

一見するだけでわかってしまうほどのオリジナリティ。
ドイツ出身の画家マティ・クラーワインによる黒魔術的なドローイングがマイルスの問題作『ビッチズブルー』の世界観そのものと見事に呼応している。
エレクトリック・マイルスの金字塔、と言われる名盤『ビッチズ・ブリュー』は、当然、正統派ジャズファンと称するものとは決定的に裾を分かつことになるアルバムであろう。
どちらもマイルスの一側面に過ぎないが、本物の息吹が真の革命をもたらすことには変わりはない。
木盤:あぶらだこ

数あるアヴァンギャルミュージックの中でも、もっとも形容しがたく、もっとも個性的バンドがこのあぶらだこではないかと思う。ハードコアパンクから派生したものの、変拍子、ポリリズム、独自の空間性は唯一無二の世界観を誇る。
そして聴いたことのない現代詩の叫びとしての長谷川裕倫のボーカルスタイルとの絡みは、他の追随を許さない。
まるで、人類の発祥のごとき驚愕の瞬間を突きつけてくる
その存在の前に、超克すべく未知の領域に投げ出されるのだ。
D’eau :Sakana

さかな(SAKANA)のインディーズ時代の傑作は、すずしげで透明さのなかに時折みせるその陰の部分に物語性を滲ませる。
奇妙なずれや間、ブリジット・フォンテーヌの息吹きを感じさせる白昼の狂気が静かに横たわる。
パーカッションと効果音のような音響にポコペンの面妖な歌、
ニシワキの透明なアコースティックギターが絡む。
今日の音響派を先取りするかのようなアルバムのコンセプトに
なみなみならぬ彼らの才能の片鱗がのぞく。
Soused:Scott Walker + Sunn O)))

ほぼ聴いたことも、興味すら持ったこともないヘビーメタルというジャンルにおいて、ドゥーム・メタルという響きをこのSunn O)))を通じて知ることになるのだが、ドローンや反復といった音響ノイズは、どこまでもダークでありながらアンビエントやミニマル的要素を兼ね備えており、確実に聴くものを選びながらも、ドラマチックに反応するだろう。
そんな新たな音の体験を運んでくる劇空間に、燦然と響き渡るスコット・ウォーカーがいる。
いったいこれはなんという組み合わせだろうか。
森の番人のような深淵なスコットボイスが絡めば、
この世のものとは思えない異境へ誘うことは避けられない。
まさに劇薬さながらの化学反応によって神秘体験をも引き起こす、危険で底知れぬ美しさをもったアルバムだ。




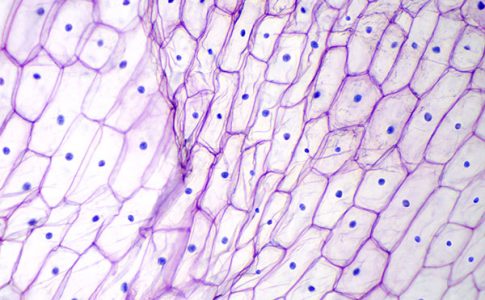






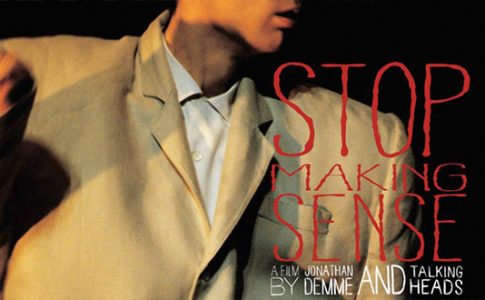

YMO関連のアルバムの中で、もっとも革新的な一枚をあげるとすれば、これになる。文句なしにこれだ。
40年経った今聴いても全然古い感じがしない。
フランスの哲学者ドゥルーズの『差異と反復』からインスパイアされたという一曲目「differencia」の物々しくも
反復される生のリズムのかっこよさに代表されるように、
ダブ、エレクトロニカ、音響派、というのちのシーン流れを
誰よりも早くキャッチし、ニューウエーヴ的要素の中で見事に解体、そして再構築し、その方向性を80年代初頭に示したこのアルバムに、坂本龍一という人の恐るべき音響人としての先駆的才能を感じるのだ。