永遠とつがった海と太陽、SAKANAをめぐる航海記
2018年限りで34年にもなる長い活動を停止してしまったSAKANA。
ぼくは少なからず、ショックを受けている。
おそらく、探せばそんな人たちはいるはずだ。
まさかこんな日が来るだなんて、思いもしなかったから。
なにしろ、SAKANAの西脇&ポコペンを、
永遠とつがった海と太陽だと思っていたから。
まさか、夜の帳が降りてしまって、
こんなにも辺りがまっくらになってしまうだなんて、想像もつかなかったよ。
だから、そんな状態でSAKANAの記事を書くのは、
ちょっと心苦しいのだけれど、
以下はもうとうの昔に書いていた記事だから、
それはそれとして、残しておきたい気持ちがあるし、
SAKANAが今後また、いつの日にか朝日が昇るようにして
にっこり復活してくれることをどこかで祈りながら、
やはり愛すべき記憶の断片としてここに、記事にしておこうと思う。
この晴天の霹靂のような出来事のなかで、
あの日マンダラ2でのラストワンマンライブに、
あたかも虫の知らせからかノコノコ出かけて、
最後の勇姿を目に焼き付けられたことだけが唯一の救いとして、
今こころの灯をともしてくれている。
こちらとしても、少しブランクがあり随分久しぶりに見たのだけど
以前のSAKANAとは何一つ変わらないSAKANAだったことに安堵した。
だからこそよりショックも大きいのだが、
彼らの勇姿を一番多く目撃してきたこのライブハウスでの最後の残像を、
いつまでも瞳に焼き付けることができたことを感謝しよう。
そこで、驚くべきか、微笑むべきか、
色々考えあぐねたけれど、結論は出そうもない。
相変わらずポコペンという人は饒舌で、
西脇氏はあくまで寡黙で、
ゲストミュージシャンの方がかえって目立ってたりしていて、
その上に、相変わらず知らない曲が盛りだくさんで、
昔なじみの曲なんてほとんど聞けなくって、
歌詞が書き変わっていたり、アレンジも変わっていたりして、
それでも淡々と演奏していて、
こういうスタンスを全てひっくるめて、
目の前のSAKANAは自分の知っているSAKANAとはなにも変わらず、
この蟻の巣みたいなマンダラ2のステージを、
いつかみた風景と同じようにして、涼しげに泳いでいたのは、
やっぱり夢ではなかったのだし、
ひとときの至福の時間と共にそんな自分がいたのだった。
思えば、SAKANA関連のCDはほぼ手元にあり、
気がつけばそれをずっと聞いてきた自分がいるし
『マッチを擦る』だとか、『水』だとか、『夏』だとかいう、
今では聞きなれないちょっとへんてこりんで不思議なCDを出していた頃から、
彼らの活動を何十年もずっと気にかけてきて、何度もライブに足を運んで、
まるで我がことのように感じて来たものとしては、
SAKANAがなくなってしまうという現実が、
たとえ抗えない事実だとしても、物理的な記憶としても、
どうにもこうにも消し去りようもない事件として残されてしまった。
今後どういう活動になっていくのかはわからないけれど、
これからもずっと聞き続ける音楽であることには変わりがなくって、
その意味では、やはり何も変わりはしないのだと
そうつぶやくのは当然のことなんだ。
正直に告白するなら、SAKANAというバンドが、
これほどまでに素敵な音楽を作り続けながら、
どうしてメジャーの時流に乗らないんだろうか?
と思ったことは一度や二度じゃない。
それは『マッチを擦る』だとか、『水』だとか、『夏』だとかいう、
今では聞けなくなってしまった、
へんてこりんなCDを出していた時からの偽らざる思いだ。
要するに、彼らは、そうした世俗的な成功とは無縁の世界で、
ただ好きな音楽や絵画を制作している人たちなんだろうな、
ということで納得していた。
そのことがいつしか当たり前の認識になっていたけど、
それはそれで間違いでなかったんじゃないかと思う。
なぜなら、あんなに奇跡的にピュアな曲を書き続けるには、
そうしたスタンスが彼らなりの最善の方法論だったんだろうから。
だから、あんなにライブに足を運び、生の歌声、生の演奏、生のMCを聞くことが、
とても貴重な時間として感じていたし、
自分をSAKANAという存在と結びつけた唯一の真実だと思っている。
そんなこともあって、活動を停止の理由はあえて知りたいとは思わない。
だってそりゃ一番残念に思っているのは、SAKANAのふたりだろうから。
ぼくはこの二人が日本の音楽シーンにけがされることなく、
長年活動して来たことを敬服しているし、
これからも忘れないだろうし、
ずっと感動を覚えている人間だと思うから。
双頭のさかな
トープラン、シープラン、実はひとりなの
「レインコート」アルバム『水』より
個人的に随分と親しんで来たこのさかなについて書く、
あるいは語るとなると、
なんだかとりとめもなくなってしまうはなぜだろう?
その長い活動履歴、豊富なディスコグラフィといった
量的な絶対性よりも、そぎ落とされた音、
想像性に飛んだことばや非凡なメロディへのこだわり、
それらに呼応するかのような
慎ましい活動や動向といった存在の本質的な部分が、
何にもまして魅力的なさかなの前には、しばしことばを失うのである。
文字通り、大海を自在に遊泳するさかなを素手で捉えようとするもどかしさ、
とはいえそれは、音を感じるという体験によって
そのつど救われることになるのだ。
あまりにも独特な、それでいて新しく耳にするものたちをひきつけてやまない
普遍的な音楽性をも身につけた今日の彼らさかなの活動は、
いわゆるロジックなんてものを無に帰してしまう。
何ゆえに、このさかながとても愛おしく思えるのだろう。
それはポコペンのライブでのとぼけたMCぶりに
一度や二度思わず笑ってしまったことのあるものなら
そしてその横で心配そうに、でもやはり静かに微笑んでいる
もうひとりのさかなの光景を知るものならば
とくに説明はいらないだろう。
いや、彼等の多産で豊かな音楽のどれかひとつを聴いただけで、
その情感は十分に伝わるにちがいない。
メロディ、音質、そして物語性をおびたことばの数々、そしてジャケットワーク。
ひとつひとつが手細工のように、
これほどまでにその人となりを伝えているのだから。
現在の活動では、様々なゲストメンバーを迎えながら、
2人編成での活動がさかなである。
一時さかなではなく『カメラ』というユニットがあり、
記憶違いでなければそのアルバム以来、
彼らのオリジナルドラマー林山人の後継として迎えられているはずの
ポップ氏のドラミングには、
さかなへの深い理解力、
すなわち愛情にみちた力強くも繊細なプレイが聴ける。
今やさかなの別の側面を確固としてささえている、
まさに唄うドラマ-だ。
とはいえ、さかなはたえずポコペン&西脇という、
この絶妙なコンビネーションで成立している。
彼らが生み出すハーモニーの豊かさを、何かに喩えることは難しい。
実のところ、これはソウル・ミュージックでしかない、
いわゆる魂の音楽だというようなことだと思ってはいたが
時間が経つにつれ、これは唯一無二の音楽で
『SAKANA』と書くか『さかな』と書くか
それぐらいの違いに過ぎないものだと理解するに至った。
それは彼らの本質が、影響を受けているはずの
リズム&ブルーズなどそのルーツ・ミュージックにあるような、
日常のなかの思いを唄とギターで
実直に伝えようとする姿勢そのものにあるからだ。
とはいうものの、いっけん何でもない表記のような、
『さかな』、という名前を想起するとき、
俄然その不思議なオーラを言い当てている、と思わずにはいられない。
無邪気さのなかに奥深さ、親しみやすさのなかに寡黙さ、シンプルさのなかに複雑さ・・・
相矛盾した要素を平然と宿している「さかな」という響きそのものに、
彼らさかなのさかなたる所以があるのだと思う。
十数年にもわたる長い音楽履歴、
その多様な音楽性と変遷模様を知っているものたちは、
おそらく、このふたりが、音楽的に随分と変化し、
成長を遂げていったという事実よりも、
当初となんら変わることのない、
ある種の瑞々しさを保持しつづけていることの奇跡に、
実はもっともくすぐられてしまうのではなかろうか?
もはや、入手するのが困難になってしまっている初期のころの名盤たち、
たとえば「マッチを擦る」「水」などというアルバムには、
今日たどりついた明確な親しみやすさなどみじんもない。
白日の狂気に満ちた実験的で自由きままな音作りが展開され、
今日の音響派たちの作業をなんらかの形で先取りしながら、
彼らのルーツミュージックの断片を随所にしのばせている。
それらは、時を経てもいっこうに色褪せることがなく、
むしろ逆説的に新鮮でありつづけるのだ。
一枚一枚、違う表情とコンセプトをもち、
彼等は、自分達の音楽をつくりあげてきた。
音楽シーンの傾向や状況に左右されることなくマイペースを崩さないその神髄は、
原点にもどったようにふたりだけの世界として構築された
傑作『Blind Moon』に集約されている。
そしてなによりも驚くべきことは、
彼らがいまだ音源化しえない曲が山のようにあって、
そのなかからでさえ、簡単にベストセレクションが編めるほど
多産な音楽家であるということだ。
だから、真の傑作は、彼等自身が未だ発表することのない、
常に懐胎する時間のなかに生まれおちてゆくはずなのだ。
この「さかな」ならではのスタンスでもって、
新たに奇跡が更新されつづけていくということを
あらかじめ知っているものたちは
この最高傑作である『Blind Moon』でさえ、
かつてのさかなの一枚、といった気持ちにさせられることだろう。
それゆえ、皮肉にも最高傑作という響きは、
どうやら意味を失ってしまうのである。
注)この記事はもう二十年以上も前に書いた記事です







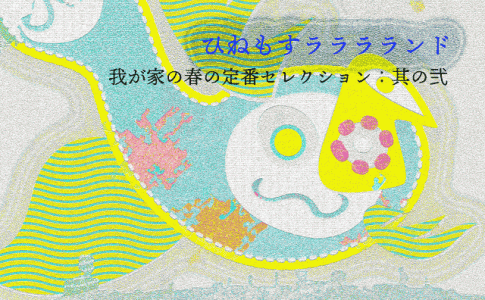
![[門戸無用]MUSIQ](https://lopyu66.com/wp-content/uploads/2020/11/misiq-1-485x300.gif)



コメントを残す