虫の知らせに耳をすませろ
ヨーロッパ発の異色スリラー『胸騒ぎ(英題:Speak No Evil)』は、
観る者の胸に生理的な不快を残すバッドエンドな
「胸糞映画(一般には今年最も不穏な映画)」として話題をさらった。
ちなみに2024年にはハリウッドで
『スピーク・ノー・イーブル 異常な家族』としてリメイクされている。
日本語のタイトル「胸騒ぎ」を見て、
上手くつけたものだと感心したものだが
とはいえ、誰かに勧めたくなるようなたぐいの映画でもないし、
かといって、みるに値しないと唾棄すべき作品だというものでもない。
この映画から、人は何を感じ、何を学習すべきか、
そんな視点をもって、この不快さにおぼれない程度の良識をもって
ここはひとつ思慮深く受け止めてみるとしよう。
むしろこの作品を、単なる不快映画として片付けるのは惜しい。
そこでクローズアップされるのが映画の意義である。
クリスチャン・タフドルップ監督が描いたのは、
現代社会に根づく“美徳”がいかに暴力と共謀しうるか、という不穏な教訓である。
デンマーク人夫婦ビャアンとルイーセが、旅先で知り合った
オランダ人夫婦パトリックとカリンの家を訪ねるという、
ごく穏やかな設定から物語は始まる。
だが、彼らがオランダの田舎に足を踏み入れた瞬間から、
どこかしら微細な違和感がじわりと忍び寄ってくる。
いわゆる、ホラー映画としての第一章へと踏みこんでゆくタイミングがそこだ。
子どもがベジタリアンなのに肉を食べさせられる、
夜中に大音量で音楽が流れる、子供に対する塩対応ぶり、
あるいは冗談が妙に攻撃的で冷笑的etc。。。
これらの違和感を、招かれしものたちが
明確に指摘することができないまま、
じわじわと悪夢の方へと向かっていく。
この映画の恐怖は、超自然的な怪異ではない。
その時点では、見えない殺人鬼でも、悪魔の化身でもない。
むしろ最も恐ろしいのは、自分が気づいている違和感を
「口に出すことができない」という社会的なマナー=倫理の金縛りに遭うことだ。
英題の”Speak No Evil”が示すように、彼らが“悪を語らぬ”ことで守ったのは
空気であり、礼儀であり、相手への気遣いだったはずである。
しかし、問題はその代償として、自らと子どもを、
取り返しのつかない地獄へと導いてしまったことにある。
ここに、日本社会との明確な接点がある。
謙譲、遠慮、和を重んじる文化は、日本人の美徳とされてきた。
しかしその裏には、「嫌われたくない」「場を乱したくない」
「他人に迷惑をかけたくない」といった思考のスパイラルが潜み、
つまりは「KY」なんていい方が流行したように、
場の空気読みの美徳へと誘われるのだ。
それがやがて、声を上げるべきときに沈黙する構造を生み出す。
職場でのパワハラ、家庭内での虐待、SNSでの炎上文化、
そして災害時の避難行動にまで、その沈黙の“美徳”が影響していることは
周知のとおりだ。
では、この“口をつぐむ倫理”はなぜ生まれるのか?
背景には、現代社会における「ポリティカル・コレクトネス」の浸透がある。
通称ポリコレは「多様性を尊重する」「相手を傷つけない」「不快にさせない」
という理念だが、その心得は確かに重要かもしれない。
しかし、それが形式化・内面化しすぎたとき、
人は「自分が少しでも間違っていたらどうしよう?」
「無礼に見えたら嫌われる」という恐怖心によって、
他者との関係においては、自己を押し殺し始めることになる。
それも大半のケースは見て見ぬふり、まさに無関心社会の形骸だ。
そのようなシチュエーションを体験したり目撃することはだれにでもあるだろう。
『胸騒ぎ』は、そうした“行きすぎたポリコレ感覚”の
成れの果てを描いた作品とすら言える。
パトリックとカリンは、決して悪魔的な言動を最初からとっているわけではない。
だからこそ、客は赴いたのだ。
むしろ彼らは、礼儀を装い、友好的で、ある種の自由さを体現している。
だがその自由は、相手の境界線を試す“越境”の連続であり、
そこに対して拒否を示さない限り、彼らはどこまでも侵食してくるのだ。
そして観客は、「なんで逃げないの?」と苛立ちながら観るうちに、ふと気づく。
「自分もあの場にいたら、何も言えずにやりすごしていただけかもしれない」と。
そこに恐怖の真理が潜む。
この構図は、同じく観客を苛立たせる映画の巨匠、
ミヒャエル・ハネケの作風とも比較される所以だろう。
『ファニーゲーム』において、ハネケは、観客を暴力の共犯にすることで、
メディアが暴力を助長している現実を批判した。
一方でタフドルップは、観客を登場人物と同じ立場に引き込み、
「あなたはこれにNOと言えるのか?」と問う。
ハネケがメタ構造と悪意を含む知性で観客を叩き起こすのに対し、
タフドルップは、感情の同化と沈黙の倫理によって観客を“凍らせる”のだ。
重要なのは、この映画を極端な状況の中のフィクションと見なして
けして安心しないことなのだ。
確かに、現実には旅行先で殺人鬼に遭遇することなど稀だろう。
仮に遭遇したとて悪夢は避けようもない。
しかし、誰かの沈黙が、誰かの加害性を助長するという構図は、
我々の日常の中に常にあるということを否定すべき事柄ではない。
部下の異変を知りながら見て見ぬふりをする上司。
誰かが排除されても声を上げられない同僚たち。
公共の場で体調を崩す人に誰も近づけない集団。
これらすべては、“礼儀”や“空気”や“ポリコレ”の名のもとに、
声を殺す構造そのものに見える。
だからこそ、この映画は不快であると同時に、極めて教育的なのだ。
倫理や礼儀といった言葉の背後に、私たちは何を見逃しているのか?
「いい人であろう」とする自分の中に、
どれだけ他人を拒絶できない弱さがあるというのか?
『胸騒ぎ』は、そんな問いを突きつける鏡であり、鋭利な刃物である。
私たちの“沈黙の美徳”に警鐘を鳴らす一作にもなることを教えられる。
終わりに近づくに従って、彼らの悪魔的な仮面がどんどんはがされ、
子供が言葉がしゃべれない理由はもちろん、
最後に、なんの罪もない人間に向かって、
神不在をいいことに石のつぶてを投げつけ、命をも奪う人間の本性が晒される。
そこには、目的も意図も、具体的な動機も何も感じられない。
校内に起こりうるいじめの構造に類似しているともいえるが、
それをあえて、言及するなら、人間が抱える闇の部分だ。
多かれ少なかれ、その因子がわれわれのどこかに潜んでいるのかもしれない。
このぞっとする悪魔的な側面の露出がそのタイミングで起きるだけだ。
だが、だれもそんな側面を、わざわざ隣人の奥底に覗き込みたくはないし、
その生け贄にもなりたくない。
ならば、最後に、こんな問いを添えてみたい。
もしあなたが“嫌な予感”を覚えたとき、声を上げられるだろうか? と。
さっさとその場から逃げ仰ると思えるだろうか?
それは、現代を生きるすべての“いい人”たちに贈られた、静かな警告なのである。
くれぐれも、空気を読むことに酔ってはならないのだ。
Wayne Shorter : Speak No Evil
映画「胸騒ぎ」と同タイトルというだけで、なんの関係もないウェイン・ショーターの『Speak No Evil』を引っ張りだそう。女性のアップとキスマークのジャケットが眩しい。1964年、クリスマス・イブの夜にニュージャージーのルディ・ヴァン・ゲルダー・スタジオには、マイルスのバンドで磨かれたカルテット、フレディ・ハバード(TP)、ハービー・ハンコック(P)、ロン・カーター(B)、エルヴィン・ジョーンズ(DR)という錚々たるメンバーが集った。
タイトル曲「Speak No Evil」。このクールネスをどう聴くべきか? メロディは跳ねず、叫ばず、ただ滑り落ちるようにクールに音が連なり、淡々と散りばめられている。が、その演奏は、どこか胸に秘めた真実を誰にも打ち明けられずに飲み込む人間のふるまいのようにも聞こえる。この“沈黙のメロディ”をバッキングで支えるハンコックのコードの陰影、抑圧されたと演奏といっていいジョーンズの淡く震えるシンバルの呼吸。推進力としてではなく、むしろ“時間の間”を演出する装置として機能すえるリズム隊の妙。ロン・カーターによるベースは、その不安定な空間にときおり、何かを諭すように、言葉を選びかねている会話のような、沈黙の背後にあるざわめきを鎮めるかのように、見事に低音をキープする。
そこに絡むショーターのテナー、ハバードのソロ。ショーター自身、この楽曲群を「神話と夢想の中間にある風景」と語ったように、一貫して、目に見えないもの、口に出せないものに対する音楽的な畏怖を抱え込み、推進してゆく。この言葉には、同時代の政治状況や人種問題、そして個人が感じる痛みと恐れへの応答とも読めるが、語れば争いが起きる、語れば真実が露わになる、だからこそ“語らない”という選択は最もラディカルなメッセージに聞こえる。沈黙は同意ではなく、怒りでも拒絶でもない。ただ“語られざるもの”としてのクールな眼差しがあるだけだ。




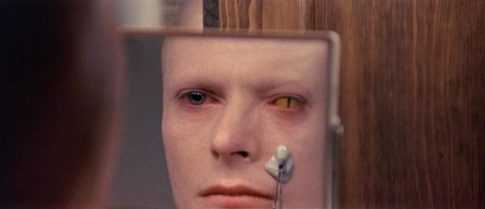



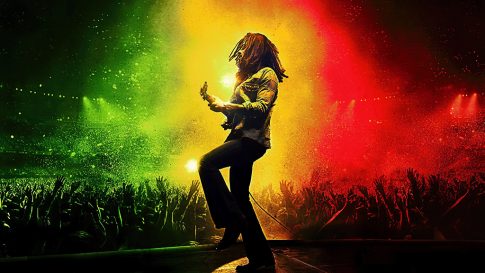




コメントを残す