水と悪意とフラメンコ
水というのは、不思議な物質だな、と思う。
透明で、無色で、流れて、1滴でも大量でも中身は変わらない。
だが時に人や街さえ飲み込む力がある。
それは集合化した水のもつ脅威というよりも
日常の奥深くに宿るひとつの魔力なのかもしれない。
一見、静かにそのブルーを基調にしたトーンの室内、
あるいは衣装、水を通して淡々と繰り広げられる家族の群像劇、
荻上直子による『波紋』を観終わったあと、
なぜだか水についてぼんやり考えてしまうのだ。
ああ、こんなにも何気ない水が、
情熱を帯び、人の生活を揺さぶるものだったのか、と。
ここに、震災で沈んだ町と家族の行方をめぐっての物語が描かれる。
『波紋』は実に巧妙に作られていると思う。
この映画には、常に「水」がキーワードとして出てくるのだが、
新興宗教の「清めの儀式」で、
特別な水として噴霧される筒井真理子扮する主婦須藤依子が
そのありがたい水を大量に買い請けて家にまで奉る。
庭に巻く水も、コップに注がれる水も、プールを満たす水も、
水は水にすぎないというのに、そこになにか意味ありげに囁くならば
実は、表情を宿した物質、それが水というものなのだと、
この映画をみればそう思えてくるのである。
ここで水という物質に、新たな生命を与えるのが宗教という名の力だ。
むろん、清めにもなれば、災いにもなる“道具”である。
あまりに人間的な感情のメタファーのようであり、
思わず笑ってしまいそうになる。
だが、声を出しては笑えない。
「笑う」といえば、
『波紋』は、おそらくブラックコメディと呼ばれるジャンルになるだろう。
それは、川島雄三の『しとやかな獣』なんかの空気感にも通じる。
あれも家族間の利害関係をめぐる巧妙なブラックコメディだった。
『波紋』もまた、悪意が随所に仕掛けられた映画である。
あざといまでに、時々聞こえてくる水面に落ちる水滴の音に
まるで見る側の感情さえコントロールされてしまう気分になる。
スーパーでクレームをつけ、商品の半額を求める男。
そこで働く依子は木野花扮する同僚と普段から愚痴を交換するが
その同僚が入院し、代わりに彼女のペットの亀を世話することになり、
その家を訪れると、日頃の皮肉へのあてこすりのように
まるでゴミ屋敷、その生活の匂いから、
あまりにも笑えない現実が目に飛び込んでくる。
あるいは、放射能の恐怖から逃げ出し戻ってきた夫は
実は、妻から逃げたのだと、
息子の口から発せられる残酷さを見せつけられる。
実のところ、ブラックコメディでありながら
声を出して笑う場面など、あまりない。
観ている間じゅう、どこかくすぐったくも、
常に、ちくりと刺される何か、身をよじるような居心地の悪さが続く。
これこそが人間というものを操る本質なのかもしれない。
ときに、はっとする瞬間さえ射し込まれている。
新興宗教の奇妙な歌と体操、いわゆる儀式はむろん、
依子が「緑命会」なる新興宗教にのめり込むのも、
ありがちといえばありがちな話だ。
弱さと言えば弱さであり、希望と言えば希望である。
その「水」の力に縋ろうとするその背景にあるのは、
震災、親の介護、夫の裏切り、更年期の孤独、息子からの疎外、
つまりは家族という器のひび割れの象徴であり、
何かを「信じていたかった」人の切実な拠り所なのだ。
面白いのは、その信仰がある種の依存の形となって、
他者を排除する盾にもなってしまうところだ。
息子の嫁が耳が聞こえないと知って、
依子が一瞬見せるあの戸惑いと距離感にそれが滲み出す。
あの瞬間の表情に、彼女の「信じたい世界」がいかに脆く、
自己中心的だったかが表れていて、思わず息をのむ。
宗教は救いでありながら、矛盾さえ正当化するものなのだ。
けれど、荻上はそこをあえて糾弾するようなことはない。
まさに、フィクションとして、ブラックジョークとして、
ひたすら悪意の着地点へとじわり向かってゆく。
そんな人間の矛盾や滑稽さを、すっとカメラの視線で包み込む。
だが、滑稽すぎて痛ましいき皮肉には、ちょっと泣けてくることもある。
戻ってきても余命いくばくかの癌をかかえている夫は、
結局、病に抗えないし、痛みが和らぐこともない。
せっかくパートナーを連れて戻った息子の将来の希望さえ描かれはしない。
全ての出来事が、まるで、水面に投げ込まれた小石の波紋のように、
ゆっくりとじわじわと、心の奥まで広がっていく。
波紋の上で、ばらばらの家族の内情を晒しあうシーンとして繰り広げられるのだ。
そこで、最後は情熱を宿した水が、再び依子のなかで生命を誇示し始める。
死んだ夫の棺を、枯山水の庭で運び手が思わず落としてしまう。
いみじくも、水を用いずにその意匠だけを具現化した庭を前に、
息子の冷ややかな視線など気にすることなく、依子は大笑いする。
ここでもわれわれ観客はつられて笑うこともない。
そこで、舞台のように、晴天のなかに雨を浴びながら
喪服をまとって依子はフラメンコを踊る。
まさに狐につままれるようなシーンだが、
途中になんども聞こえてきたハンドクラッピングの音が
ここで実装をともなったドラマチックな瞬間に変わり、
静かな狂気が、情熱と解放を解き放つ一瞬となる。
つまりはハイライトシーンとしてのブラックジョークが
こうして熱を帯びて締めくくられることになる。
この映画は、最初から特別なことなど何も描いていないのかもしれない。
でも、静かな水面のように見える日常に、
水を基調にしたブルー、情熱の赤、
そして枯山水の庭、喪服、傘etc
色や物質が常に観念を想起させながら、
小さな歪みの蓄積が、物事を作用するのだと、
確かな“揺れ”をもつのだと、そのことを忘れないようにと教えてくれる。
人は、だれも完全に清らかには生きられない世界で、
なにかに縋り、なにかに癒しをもとめて、彷徨っている。
そのなかで、自分に起こった波紋を見つめることぐらいならできるのだと、
そういわんばかりである。
それはもしかしたら、誰かとまた波紋をぶつけ合うことになるかもしれない。
が、それをジョークとして片付けうる軽やかさで受け止めるか、
それを真摯に、乗り越えるハードルだと受け止めるかは自分次第。
観客はただ委ねられることになる。
ぼくはそこで、改めて水の解釈を考えてみた。
そう、昔からいうではないか?
都合の悪いことは「水に流せばいい」と。
まさに都合のよい解釈だが、それが一番自然で無難なような気がするのだ。
ただの一滴も、大多数のなかに混じった一滴も、所詮水としては同じもの。
水は所詮水にすぎない。
その水は、ずばり、この世の悪意さえ飲み込む力があるのだ。
Buika – No Habrá Nadie En El Mundo
フラメンコについて、ほぼなにも知らないし、日頃耳を傾けている音楽ではないのだが、そのエッセンスはなにかと心に残っている。伝統的なフラメンコ歌手は知らないが、フラメンコ、ジャズ、ソウル、アフリカのポリリズムなど、多様なジャンルを融合させた歌を歌うスペインのマヨルカ島出身のシンガーで、コンチャ・ブイカというアーティストは知っている。ワールドミュージックという言葉で片付けてしまうのには、もったいないぐらい、その圧倒的な表現力をもつシンガー。そのブイカの2008年の『Niña de Fuego』から、フラメンコ色の強い一曲「No Habrá Nadie En El Mundo」を贈ろう。フラメンコとはなにか? といわれてもうまく答えられないが、パッションという言葉は、まさにこの音楽の核になっている。




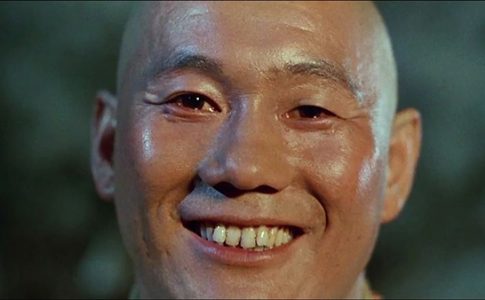








コメントを残す