静寂のなかにも声がある。
聞こえないのは、ただ小さすぎて、
日常の喧騒にかき消されているだけなのかもしれない。
耳をすませば音は確かに聞こえてくるのだが、
同時に、心で読みとるものでもあるということ。
コルム・バレード監督の長編デビュー作『コット、はじまりの夏』は、
語られざる声を、風が草原を渡るようにそっとすくい上げる。
そんな瞬間が心を打つ映画だ。
文字通り、静かな少女の詩情と視線を紡ぐ物語でありながらも
これぞ、大人の映画作りが展開されてゆく。
1981年のアイルランド。
物語は、キャサリン・クリンチ演じる9歳の少女コットの目線から始まる。
家には兄弟姉妹が溢れ、貧しさと父親の無関心が家全体に重くのしかかる。
いうなれば貧乏人の子沢山、
妊娠中の母親は生活に疲弊しきり、少女は名さえ呼ばれることもなく、
父親は実に粗野な振る舞いで、娘たちにかまう気持ちすらない。
この家の澱みのなかに、静かに息を潜めて生きているコット。
自分もまた思いを上手く伝えられない。
それは学校へいっても同じこと。
つまり、9歳の彼女には居場所がないのだ。
やがてコットは、母親の出産にあわせて
夏のあいだ親戚の家に預けられることになる。
のどかな自然に囲まれたキンセラ夫妻の家。
そこには、これまで知らなかった静けさと秩序があり
他者の空間でありながらも、自分がいてもいい場所のように思えてきた。
なによりも温もりがあった。
初めての夜、コットは家の中に満ちる音の少なさに耳を澄ます。
無駄な怒鳴り声も、舌打ちも、冷たい視線も、家族間の騒乱もない。
代わりにあるのは、湯気の立つ食事の匂いと、
薪が爆ぜる音、ドアの開け閉め、椅子を引きずる音など、
そこに誰かが“黙っている”というだけの静謐な優しさがほのかに立ち上る。
とはいえ、この家にも深い影がある。
彼女に与えられる男の子の古着。
キンセラ夫妻にはかつて子どもがいた。
その子を事故で亡くしたという過去がある。
夫妻は亡き子の代わりにコットを愛するのではなく、
亡くした愛を埋めるというのでもなく、
目の前に許された世界に、純粋に注ぎたい愛情があったのだ。
ショーンの寡黙さは、失った痛みの奥底から滲む静けさというべきか?
不器用が滲み、コットにさえも言いしれぬ壁が立ちふさがる。
それは同時に、哀しい思いを繰り返したくないという
心の叫びでもあったのだ。
少女がやって来た初日、アイリンは言葉少なに彼女を見つめ
髪を梳かし、食卓で食事を出してくれるあの仕草は、
胸に今なお生きる子への愛が、
目の前の少女に自然ととってかわった瞬間だったのかもしれない。
ジャガイモの皮を剥くコット。
牛の世話をするコット。
かけだして郵便受けの手紙を手渡すコット。
とはいえ、この映画にはおどろくほど台詞がない。
激しい感情のやりとりもない。
沈黙こそが、この物語の最も豊かな言語だ。
そして誰もが安易に「愛している」とは言わない。
しかし、少女に服を着せるときの手、皿を置くときの視線、
髪を撫でるしぐさや寝静まった夜にそっと掛けられた毛布など。
それらすべてが、「ここにいていいよ」という言葉にならない声だった。
この映画のほとんどは、アイルランド語(ゲール語)で語られる。
英語よりも柔らかくも、慣れないせいか、うまく聞き取れない。
舌にひんやりとしながらも土の匂いを含むその響きは、
ケルトの神話や苔むした石垣、そして潮風の音を思わせ、
木訥な温かみがある。
長い植民地支配のもとで奪われた母語。
そんな心からの言語で語られるとき、少女の物語は個人の境遇を越えて、
土地と民族の喪失と再生の物語へと広がっていくのを感じる。
少女がキンセラ夫妻の家で学んだのは、
英語ではなく、母語で囁かれる愛だった。
つまり、飾らず、構えず、そして自分らしく生きてゆけばいいのだと。
コットは、9歳にして、初めて知らず知らずに気を許すことを覚えたのだ。
監督は語る。
この映画が撮られたのは、抱きしめることが禁止されたCOVIDの渦中。
人と人が触れ合うことが、感染の危険となり、
誰もが物理的な接触を過度に禁じられていたときに作られている。
だからこそ、この映画のラストシーンは、
なおさら観客の心を深く撃つことになる。
ただのワンシーンではないのだと。
夏が終わり、コットを送ってきたキンセラ夫妻との別れが迫る。
コットは夢から現実に引き戻される瞬間の痛みに狼狽えながら
本能で走り出す。
キンセラ夫妻との生活で、駆け抜ける彼女の前振りが巧妙に描かれているが
ここに、躊躇いもなくショーンに抱きつくコットの顔に
ほんとうの幸せを滲ませる演出の妙がある。
実の父親は、そんなことなどわかるはずもない。
コットはそこで思わず「ダディ」とつぶやく。
この抱擁は、彼女がはじめて“父”と呼びたいと思った人への、
言葉にできない別れと感謝の表現だったのだ。
アイリンは車のなかで泣いている。
そう、「あなたはわたしの父ではないけれど、わたしが父と呼びたかった人
ショーンの腕に抱かれる一瞬、本当の想いが心の中に広がるのを感じたのだ。
そして少女はこの夏に学んだ唯一の言語をそのなかに押し込めた。
それは「ありがとう」であり、同時に「さようなら」であり、
そして「愛している」、つまりは心からの離れ難い思いの表出だった。
映画とは常々残酷なものである。
彼女はあの家には留まれないことを知っているし
現実は、血縁ほど濃いものはない。
だが彼女の胸には、ショーンの匂いが残る。
その匂いは、自分が愛されたこと、
自分が愛してもらえる存在であることを、
これからも彼女に囁き続けるだろう。
この映画が教えてくれるのは、暴力性からの逃避でもなければ
抱きしめることでの救済だ。
そして、そこから始まる物語を予見しているのだ。
触れるという行為は、ただ肉体同士の接触のことだけではない。
触れることで、その人の存在を肯定することになる。
抱きしめることで、その人の命を祝福する行為なのだ。
『コット、はじまりの夏』は、風が草原を渡るときに鳴らすような、
目には見えない音をいろいろ聴かせてくれる映画だ。
とくにドラマチックなシーンもない。
気の利いたセリフすらもない。
誰かを抱きしめたいと願うとき、
われわれはただその腕の温かさを求めるわけではない。
その奥にある、
「あなたはここにいていい」という安心を聴きたくて、
抱擁を求めるにすぎないのだ。
9歳の少女に、これほどまでに大切なものはない。
この映画のラストシーンで、少女が選んだ抱擁には、
そうした世界の真理が凝縮されているように思える。
沈黙は、決して無音ではない。
豊かな世界の目で見る音響なのだ。
それは、世界で最も優しい言語なのだと。
Dip in the Pool : Silence
映画を観て、なぜだか、甲田益也子のことを思い出していた。1983年にモデルの甲田益也子とキーボード/作曲担当の 木村達司によって結成された日本のデュオがdip in the pool。デビューはイギリスのRough Tradeだった。デビューアルバムが確か『Silence』だった。ぼくはレコードを買った記憶がある。静かな世界にもいろいろある。そこには、おしつけがましさのかけらもない甲田さんの不思議な透明感が漂う、日本的ではない異国の風景が広がっていた。『コット、はじまりの夏』をみて、なぜだか、その歌声が聴きたくなった。遠くて近い、近くて遠い夏。そんな思いが蘇る。










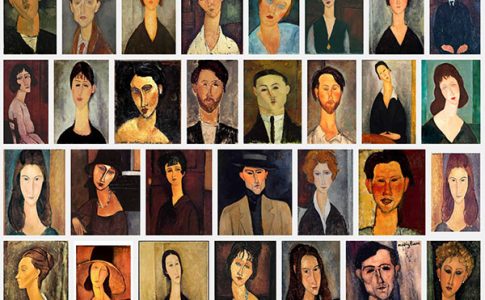


コメントを残す