航海先に立たず、お遊びはほどほどに
男の愚かさと哀しさ、女のしたたかさと執拗さの交差するフィルム。
おまけに暴力と官能とが絶妙にしのぎを削りながら
これでもかこれでもかと執拗に翻弄を繰り返す倒錯的復讐と性愛のドラマ、
そんなポランスキーの『赤い航路』にはやはりそそられるものがある。
一見すると、ブニュエルの遺作にも近い雰囲気を漂わせている。
そう、目の前の女をモノに出来ないブルジョワ男の話
『欲望の曖昧な対象』を思い浮かべているのだが、
こちら『赤い航路』の場合は、女をモノにしたは良いが
そこから複雑な悲劇を抱え込む自称作家が語る痴情である。
どちらもいい歳をした中年男が若い美女に翻弄される、
という図式は共通項ではあるが、決定的な違いが両者にはある。
政治色がらみの皮肉というかブラックジョークで満そうとするブニュエル、
一方ポランスキーの場合は、もっとドロドロとした欲望の矛先が
他者に向けられるのだ、それもかなり陰湿に。
精神的な領域にまでズカズカ出入りしてくる話として、
複雑な心理をもった人間たちを登場させ交差させ煽る。
恨み、辛みとともに、人間の背徳性をひたすら掻き立て
それを倒錯的に浮かび上がらせるのが半ば享楽であり、
次第に責任を他人に転嫁してゆくことに熱を注ぐという、
ポランスキーならではの嗜好性が如実に反映されている映画である。
ポーランド人の両親、フランスで生まれのポランスキー。
その後の映画人生における波乱万丈ぶりに関しては、
映画ファンには良く知られた話で、今更いうまでもなく
詳しくは割愛するが、ユダヤ人としての数々の迫害はいざ知らず、
最初の妻シャロン・テートの悲劇や自らの淫行事件によって、
映画界からも絶えず“目を付けられてきた”危険因子である。
なにかと話題には事欠かない訳あり監督であることは
ひとまず押さえておく必要はあろう。
どうして、こんな着想になるのか?
そうした題材を意図的に選ぶ特異な作家気質は
それゆえに一本筋の通った倒錯ぶりが半ば約束事になっており
ポランスキー作品においては醍醐味とさえいっていい。
よって皮肉るなら、チャンポランスキー、ではなく、
ハランポランスキーといった方が気が効いているだろう。
原題が「Bitter Moon」、直訳すれば「にがい月」は、
言うなれば「ハネムーン」の逆である。
『赤い航路』とは、イギリス人夫婦が豪華客船クルージングの旅に出て、
航海中におきた出来事をベースに、手っ取り早く日本流につけたのであろう。
なるほど、最後はかなり陰惨な結末を迎え、その航路が“赤く染まる”。
『反撥』や『ローズマリーの赤ちゃん』などを引き出すまでもなく
熱狂的ポランスキーファンなら、別段驚くような内容でもないが、
たとえば『テナント』を想起するまでもなく、
若きポランスキーなら、間違いなく本人が車椅子のオスカー役を演じ
その狂気に悦に入っていた気さえするのだ。
つまり、このオスカーという男には、
ポランスキー自身の内的投影ぶりが見受けられる。
一度は蜜月を過ごしたはずの二組の夫婦によって起きる事件であるのだが、
船の上で、このオスカー&ミミの変態仮面夫婦に遭遇して
どんどんと深みにハマってゆくのがナイジェル&フィオナ夫妻。
人が羨むような感じの結婚7年目のナイスカップルが
この映画では完全に“生贄”にされてしまった感じだ。
その証拠に、まじめな夫ナイジェルは、まんまとミミの毒牙にかかって
夫婦仲まで拗れてしまう。
まさに船上の悪夢である。
話はそんな悪夢のオチのために、オスカーとミミとの馴れ初めから
そして車椅子生活になってしまった過程が途中回想形式で語られてゆく。
無垢な生贄男ナイジェルに、その中身を赤裸々に語りつつ、
「私の妻を抱きたいだろう? 正直に言ってみろ」などとけしかけてくる始末。
ミミの官能性を吹き込んで、真面目なナイジェルの心理を揺さぶろうというのだ。
そんなオスカーは小説家志望だが、
世間からは相手にされない自称作家である。
その鬱積を女にうつつを抜かすことで、親の遺産でぬくぬく生きてきた
要するにクズ男なのである。
そこで出会ったのがミミであるのだが、
最初はミミの方が積極的にオスカーの性癖に応じる形で、
二人は見るに忍びないほどに、のべつ幕なしに色三昧にふける日々を過ごす。
が、オスカーの方が飽き始めると
次第にミミをぞんざいに扱ってゆくのだが、
そこは男と女の話としては、片方だけの言い分では成立しない。
最初は一方的にミミに乗り上げたオスカーも
あたかも天罰の如く、自動車事故で車椅子生活を余儀なくされると
立場は一転し、今度はミミにもてあそばれる始末で
ついに決定的なダメージを食らわされる。
ベッドがら引きずり下ろされ、その際に下半身不随になってしまったのだ。
当然、それに価するだけのことをしてきた見返りなのである。
そこからがいよいよ本題である。
その二人が豪華船で、別の、しかもみるからに幸せそうな夫婦を見定め
世にも恐ろしい官能地獄へとおとしめてゆくという展開がまた凄さまじい。
不随のオスカーは、そこであらたな生け贄ナイジェルを見出し
ミミを使ってサディスティックに追い込んでゆく、
まさに変態ポランスキーの十八番劇である。
それにしても、自身の妻エマニュエル・セニエをそのままキャスティングし
そのあらわな官能ぶりを映画という名目で見つめるポランスキーという監督は
ただものではなく、もはや変態の域を超えている。
マゾヒズムとサディズムとがどこまでも交互に入り混じり、
ポランスキーの欲望は次第にエスカレートしてゆく。
最後はミミとフィオナのレズシーンまで付け加え、
ここまでくると、性癖というよりは、犯罪スレスレの遊戯である。
普通なら、辟易しかねない描写の数々を惜しげもなく盛り込んで、
ポランスキーはあたかも官能ミステリーのようにつないで
いよいよラストシーンを迎える。
が、所詮遊びは仕掛け人自らの手で妻を殺して自害する、
集中力の切れた子供のように、あっけない幕切れで終わるのだが、
この流れの前には、ポランスキー恐るべし、としかいいようがないが、
よほど複雑な内面性が、よくぞ映画に向かったことに胸を撫で下ろす次第。
いい年をした中年男性諸君には、くれぐれもお遊びはほどほどに、
思わずそう呟やかずにいられない。
Carole King – Bitter with the Sweet
ボウイの曲で文字通り「Red Sails」という曲があるが、ここは、「赤い航海」の原題「Bitter Moon」にちなんで、キャロル・キングのシティポップ風な名曲「Bitter with the Sweet 」を取り上げてみた。この邦題が「喜びは悲しみの後に」なのだが、映画の方は喜びの後に悲しみ、というか、哀れさが襲う。あまり内容的なリンクはない。歌詞の中でYou’ve got to take the bitter with the sweet、つまり“苦みも甘さとともに受け入れて”ってことになるけれど、総じて幸せと不幸は表裏一体、というようなニュアンスにも受け取れるのかもしれない。とはいえ、わざわざ苦しみを作って受け入れるような、倒錯的な遊びはほどほどにしないと痛い目に会うってことなんだな。











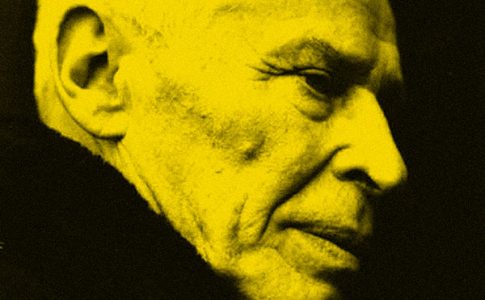

コメントを残す