主体女優の誕生
序
ここまで、勝手にわが偏愛女優小論を重ねてきたが
トリを飾るのはこの人しかいない。
若尾文子については、ここでは彼女の主演作品のなかで、
何度も言及し、ひたすらその思いを綴ってきた。
とりわけ、増村保造という映画作家の元で放った
強烈な印象を中心に、思いを傾けてはきたが、
本来、彼女は、一つのジャンル、傾向に収まりきるような女優ではない。
それこそ、舞台から、テレビドラマ、CMなどをこなす、八面六臂の活躍は
昭和の乗りをこえて御年90の大台にも突入している。
溝口健二作品では、女優道を仕込まれ、
小津や川島雄三といった名匠のもとでキャリアを重ねながら
本領たる増村作品にで合う。
『青空娘』にはじまり『最高殊勲夫人』『卍』といったものから、
以後中心にかたる日本女性にはない、強さをもった役で
印象を決定づける作品はもとより、
さらには吉村公三郎や市川崑といった監督の元では
洒脱なコメディエンヌとしての才も十二分に発揮してきた、
文字通り、日本映画の隆盛期を支えてきた大女優である。
増村作品にみる主体女優について
映画の中で、女は長いあいだ「耐えること」にはじまり
「見られる存在」そのものとして彩ってきた。
彼女たちは愛され、欲望され、守られ、あるいは犠牲になった。
しかし彼女たちが自らの意思によって存在を決定することなど、
ほとんどあったためしがなかったのだ。
とりわけ、この日本という土壌では、
女性は常に物語の内部にありながら、物語の主体として描かれはしなかった。
その構造を、日本映画の内部から破壊した女優がいる。
それが若尾文子である。
彼女は女を演じたのではないし、創造の破壊者でもない。
女が主体になる瞬間そのものを、スクリーンの中に実在させたのである。
そしてその誕生の場こそが、増村保造との映画だった。
増村は、若尾文子を通して、主体という概念を段階的に解放していく。
欲望から始まり、象徴へと至り、そして最後には、純粋な意思へと到達する。
その最初の決定的瞬間は、まず、1960年『妻は告白する』において訪れる。
雨の中、鞄で顔を隠しながら、黒い和服姿の綾子は、
あたかも幽霊の如く愛人の会社へと足を運ぶ。
彼女がすでに、この世界の秩序の内部に属していないことの徴である。
彼女は夫の死をめぐって、裁判を通過し、
社会へと復帰することが可能だったにもかかわらず、それを拒否する。
川口浩扮する愛人との生活を望むが、
それが困難だと悟ると彼女は毒を飲む。
だが、この自決は復讐でもなければ、よもや敗北でもない。
それは、誰のものにもならないという最後の選択である。
貞操の美徳を拒否し、愛人の所有物となることをも拒否する意思であり、
ここで若尾文子は、「見られる存在」から、「存在を決定する主体」へと変貌する。
彼女は理解されることを拒否し、ゆえに主体は不可解なものとして誕生したのだ。
しかし、これはほんの序章にすぎない。
主体は、まだ欲望の内部にふつふつとある。
主体の最も恐ろしい形は、日常の内部にも現れる。
『「女の小箱」より 夫が見た』の那美子は、振り返らない。
家庭の女たる彼女は、日頃の夫との倦怠、愛の限界を
敏感に察知するが放置できない。
そして、近づく愛を経験し、情熱を通過し、そして離脱するのだ。
田宮二郎演じる石塚はそんな彼女を愛し、欲望し、そのすべてを賭ける。
しかし彼の死もまた、那美子の前では愛の殉死にはならない。
それは主体の誕生のために捧げられた供物そのものだからである。
彼女は振り返らないし拒絶もしない。
すでに関係そのものが消滅しているからであり、
もはや、愛されるための存在ではなくなってしまっているのだ。
それは欲望されるために存在しているわけでもない。
彼女はただ存在するために存在している。
つまるところ、エロティシズムはここで純化され、
肉体を離れ、存在そのもののエロティシズムへと変わってゆく。
続く『清作の妻』のお兼は、その欲望をさらに純粋な形で引き受け、
個の力強い論理の地点へと導く。
愛を失いたくない彼女は眠る清作の傍らに座る。
彼はといえば、国家によって戦場へ送り返される存在である。
村はそれを祝福し、国家はそれを正義と呼ぶ。
しかし彼女は、それを虚構として見抜いているのである。
そして、その大義名分に屈しないために彼女は五寸釘を手に取る。
それは呪いの道具でありながら、同時に奪還の道具でもある。
彼女は清作の目を潰すという行為に及ぶ。
この瞬間、彼女は国家の秩序をも否定するのだ。
そして、彼女は自分が属する村の視線をも一切破壊してしまう。
そう、彼女は、愛を制度の上位に置いたのだ。
彼女は犯罪者ではない。
だが、犯罪者よりもさらに大きな十字架を自ら背負うのだ。
欲望がここで、制度を無効化する働きで勝利する瞬間に
彼女はあらゆる困難を引き受けるが、
彼女は、ただ現実の側に立っただけなのだ。
だが増村保造は、主体をさらに別の地点へと導く。
『刺青』のお艶において、主体はついに人間の内部から外部へと移行している。
女郎蜘蛛の刺青を背負った瞬間、彼女は変わる。
それまで彼女は見られる存在の女だった。
しかし今や彼女は、見られることを支配する存在となってゆく。
男たちは彼女を見る。欲望する。そして所有しようとする。
しかしその欲望そのものが、すでに刺青によって肉体に誘導されているのだ。
彼女は男を誘惑しているのではない。
彼女は、欲望が発生する場そのものになって、巣を掛ける。
なぜなら、彼女は女郎蜘蛛によって、欲望を操られているかのように
男たちを食い物にし、殺しさえも厭わぬ悪女として身をさらすのだ。
男たちは、自ら進んで彼女のもとへ近づき、そして破滅する。
それもまた、敗北ではなく、単なる供物である。
敗北はむしろ入れ墨師の内にあり、その敗北感が
この内なる悪の支配者に、とどめを刺すことを促し、女は死ぬ。
主体がここで、人間の内部から、図像へと移行しているが、
主体とは、もはや意志ではなく、存在の構造そのものとなる瞬間なのだ。
こうしてみると、ハイライトは『赤い天使』の西桜だといえるだろう。
彼女は戦場にいて、絶えず死のそばにいることで覚悟は座っている。
彼女は負傷兵の身体を介護しているが、
その身体的苦痛だけでなく、性的苦痛をも引き受ける存在だ。
ゆえに、天使の冠に偽りはないのだが、むろん、それは官能ではない。
それは、人間が人間であることを最後まで維持するための行為、
それを自らの意思で助長するのである。
そして彼女は愛をも辞さない行動に出る。
軍医を愛し、しかし彼もまたモルヒネで性的不能者でありながらも殉死し
ここで、すべてが奪われる形になる。
愛も、救済も、意味も、すべてが破壊されるのだ。
それでも彼女は残る。
彼女は銃を取り、前を向く。
もはや、それは復讐ではないし怒りでもない。
それは意思だからである。
彼女は存在することを選ぶのだ。
欲望でもなく、魔性でもなく、愛ですらなく、ただ意思だけが残る。
それが天使の宿命だと理解するかのように、
もはや、彼女を縛るものは何もない。
ここで主体は完成する。
それは他者を必要としない真の主体である。
それは存在そのものとしての主体が、ここにある。
増村保造は、若尾文子を守ったり、美化したりはしない。
彼は彼女を極限へと追い込むことで、女という身体性を利用する。
彼女から愛を奪い、欲望を奪い、救済をも奪う。
そんな窮地に若尾文子は、ひとり立つ。
それでも彼女は崩れない。
彼女は存在する。
ここにおいて、映画は単なる表現ではなく、存在の証明を刻印してきた。
若尾文子という女優は、その役を演じたのではない。
彼女は主体が誕生する瞬間そのものを存在させた。
それは女優という存在の極限であり、戦場のようなものだ。
主体女優とは、役を超えて存在する者のことである。
戦士が国家に身を捧げるように、
彼女は増村の作品に、そして映画に身を任せた。
若尾文子とは、日本映画において初めて、
主体として存在した女優なのである。
椎名林檎 – 主演の女
「追い付けない」なんて云うのね 知ったこっちゃあないわ。そんな歌い出しが実に耳に刺さる椎名林檎らしい曲だ。元は2009年にPUFFYのアルバム『Bring it!』へ提供した楽曲だったが、こちらはセルフカバーアルバム『逆輸入 〜港湾局〜』に収録された曲で、アレンジがかっこいいなとおもってたら、なんと大友良英アレンジで、そのスペシャルビッグバンドがバックに入っていて、どおりでパンチが効いているなと。改めて語るまでもなく、ここで歌われているのは女の自立ではなく、存在そのもの歌だ。ただ、聴けば聴くほどに、ちょっとベクトルや温度感の違いを感じさせはするのだが、まさに、主体の女優若尾文子に贈るに恥じないインパクトがある。何が違うのかといえば、微妙な湿度の量なのかなと思う。椎名林檎の曲にはくぐもった湿度が感じられないが、同じように、存在そのものを突ききる若尾文子の存在には、大女優の品格ともいうべく、ほんのりとした陰影を帯びた湿度感を感じさせる。時代感覚も手伝って、その溝は埋まるはずはない。







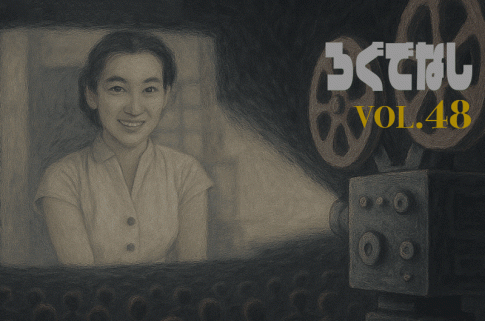




コメントを残す