男と女のダバダバダ
アヌーク・エーメは実に恋多き女だった。
4度の結婚、離婚を繰り返している。
そのなかには、『男と女』で共演をきっかけに結ばれた
サラヴァを立ち上げたSSWピエール・バルーも含まれる。
蜜月期、わずか3年の月日だが、遊吟詩人的なバルーとの恋もまた
詩的インスピレーションの賜物だったにちがいない。
ピエールはのちに「彼女は嫉妬深いところがあってね」、
そんなことをいっていて、一気に現実に引き戻された記憶があるが、
それでも、スクリーンを通して見る彼女が魅力的だったことに
なんら変わりはなく、その女心に寄り添いたくなる男たちにとっては
そのギャップこそが彼女へと恋を走らせてしまう要因なのかもしれないと思った。
多分に漏れず、ぼくもまた、そんな女優にときめいた。
そんなアヌークを振り返るとき、奇妙な違和感が残る。
彼女は常に美しく、理知的で、気品に満ちているのに
幸福な女として記憶される役がほとんど見当たらない。
悲惨さを背負うわけでもなく、哀れみを誘うわけでもないのに、
彼女が主演した映画には、幸福が「結末」として定着することがない。
その不思議な空白こそが、彼女の女優像を貫く核心でもある。
その原点に位置するのが、ジャック・ベッケルの『モンパルナスの灯』で演じた
天才画家モディリアーニの妻役ジャンヌ・エビュテルヌだ。
愛するモディの子を宿しながら、彼の死の翌日、21歳で自ら命を絶つ女。
アヌークはこの役を、激情や悲嘆で塗りつぶしはしない。
むしろ、最初からどこか「取り返しのつかなさ」を知っているかのように演じる。
その静けさは、愛が人生を救わないことがあるという冷酷な真実を、
観客の胸に沈殿させるのだ。
ここで彼女はすでに、「愛の報酬を受け取らない女」を体現していたといえる。
続くフェリーニの『甘い生活』、そして『8½』での彼女のポジションは
“幸福にならない正妻”として配置されていた。
ブルジョワの娘であっても、大監督の妻であっても、そこに救済はない。
フェリーニにとってのアヌークは、男の幻想を刺激する女ではなく、
幻想が幻想にすぎないことを冷ややかに照らしてしまう現実的な存在だった。
そこはやはり、フェリーニには所詮ジュリエッタ・マシーナがいたからだ。
一方でアヌークは映画を支配しないが、その代わり、男の世界を静かに冷却し、
物語そのものを立ち止まらせるミューズだ。
その正確さが、フェリーニ的狂騒のなかで、逆説的な孤独を際立たせていた。
そしてジャック・ドゥミによる瑞々しい処女作『ローラ』でのヒロイン。
ここでアヌークは、港町ナントに生きる“待つ女”となる。
恋人の帰還を信じ、子を育てながら生活を続けるローラ。
しかし、待つことは報われるための条件ではないのだ。
たとえ再会が訪れても、時間は巻き戻らず、幸福が保証されるわけでもない。
ドゥミは彼女に夢を与えるが、結末は与えてはくれなかった。
ローラの未来は語られず、風景の哀愁の中に溶けていく。
ここでもまた、幸福は遠景のまま漂う。
そして、彼女の存在を決定づけたのはルルーシュの『男と女』である。
「ダバダバダ」という旋律が象徴するのは、恋の始まりではなく、
恋が終わったあとの余韻だ。
夫を亡くしたアンヌは、新しい愛の可能性を前にしながら、
決して無邪気には踏み出す女ではない。
愛は始まるかもしれないが、幸福になるとは限らないというその予感を、
彼女はすでにかかえもっていたのだ。
エーメの演技は、言葉ではなく間で語られる。
まばたきの遅さ、視線の逃がし方、その一瞬一瞬に愛の慎重さが刻まれていた。
二十年後の続編、そして晩年の最終章へと至る三部作において、
愛はもはや成就の物語ではなく、時間の層として蓄積される記憶へと変わる。
身体は老い、記憶は欠けていく。
それでも「ダバダバダ」、あの旋律だけは残る。
恋ではなく、「恋を生きた人生」そのものが、映画の主題となっていたからだろう。
振り返れば、エーメは私生活においても結婚と離婚を繰り返した。
だが、それはけしてゴシップとして消費されるべきものではない。
彼女が演じてきたのは一貫して、「関係は終わっても記憶は終わらない」
そんなミューズとしての女性像だった。
幸福を掴む女ではなく、幸福が成立しないことを知ったうえで生き続ける女。
彼女の出で立ちが翳利を帯びないのはそのためだ。
だからこそ、アヌーク・エーメは幸薄く見えなかったのだと思う。
彼女は常に強く、美しく、常に理性的だった。
だがその分だけ、幸福という幻想を引き受けられなかったのかもしれない。
続編の続編、いわば半世紀後の再会ドラマ『男と女 人生最良の日々』においても
86歳のアヌークをみて、90歳のトランティニャンは
そのときめきを隠さなかった。
まるで、初めて出会ったときのように。
髪をかき上げ、そして微笑むアンヌ。
ヴェルレーヌの詩を暗唱するジャン・ルイ。
元レーサーの記憶はムスタングからアンヌの運転するシトロエン・2CVへ
二人は時間を超えてかつての場所を駆け巡る二人は
実にロマンチックだったが、ふたりの老いは
そのロマンに人生の酸いも甘いも閉じ込めた永遠性だけを滲ませた。
四度目はもうない。
それは観るものの心のなかにだけある。
色あせない恋のミューズ、永遠のミューズ、アヌーク・エーメ。
最後にもう一度口ずさもう。
ダバダバダ、ダバダバダ。
それは恋の勝利を告げる音楽ではない。
失われたものへの、届かない手紙の旋律だ。
ピエールが彼女に贈った愛の言葉だ。
アヌーク・エーメとは、その手紙を読み上げる声ではなく、
黙って封を差し出すことのできた女優だったのではないだろうか?
Nicole Croisille Et Pierre Barouh – Un Homme Et Une Femme
アヌークに捧ぐ曲としては、これ以上のものはないんじゃないかな。説明不要の名曲。ピエール・バルーの名を知らしめたニコール・クロワジールとのデュエットでのスキャット音楽。軽音楽として、単なる映画の挿入歌としてのみ語られては寂しすぎるけど、永遠に口ずさんでしまうダバダバダなのです。今聴くと、「男と女」のテーマは、けして恋を語る歌なんかではないな。いうなれば、恋が語れなかったこと自体を、記念する音楽とでもいうべきか。アヌーク・エーメの顔に漂う、あの冷えたやさしさ。近づけそうで、近づけない距離。そして幸福の手前で立ち止まる思い。そのすべてが、言葉ではなく、ダバダバダという呼吸になって流れている。だからこの曲は、時空を超えて今もなお、終わらない永遠の時を刻んでいるのだろう。



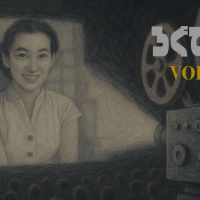









コメントを残す