永遠のアジアンビューティ、その身体性の品格について
最初にマギー・チャンを見初めたのは、ウォン・カーウァイの『欲望の翼』での
たった1分でいいから時計を見ろとレスリー・チャンに口説かれるシーン、
あのドラマチックな一分間の恋愛劇にはじまる。
あれには痺れたな。
それ以来、ウォン映画のとりこになり
処女作アンディ・ラウとの『いますぐ抱きしめたい』や
『花様年華』でのトニーレオンとの大人の恋愛模様で
ますます彼女の魅力にどっぷりはまっていった。
通常、女優の魅力を語るとき、
演技力、代表作、時代性といった言葉が並ぶものだが
このマギーについて考えるとき、
どうしてもそれらとは別の地点から語り始めたくなる。
それは彼女の立ち姿、その美しさに素直に見惚れてしまうからなのだ。
何かを語る前、何かを演じる前、ただそこに立っている身体が、
すでに映画になっているという女優。
この希有さこそが、マギー・チャンという女優の核心にあるのだ。
節度をまとう身体性の品位
ここでまず最初に語りたいのは、『花様年華』におけるマギー・チャンだ。
香港映画史のなかでも特異な到達点に作品だろう。
彼女が演じるスー・リーチェンは、終始感情を爆発させない。
愛を語らず、欲望を主張せず、ただ沈黙のなかで立ち続ける。
見るごとに違うチャイナドレスは、彼女の身体を語りながらも同時に封じ込める。
あれは衣装ではなく、倫理を可視化する装置のようなものとして彼女を包み込む。
よって、トニー・レオンとの関係は「近くて遠い」。
だがそれは恋の駆け引きではない。
一線を越えないことを、弱さでも諦念でもなく、
品格として引き受ける身体性がそれを体現しているのだ。
ここでのマギー・チャンは、香港という都市が長い時間をかけて育ててきた
「大人の美」の結晶のような佇まいで立っている。
ウォン・カーウァイ自身がそうであったように、
二人もまた上海からの移民としての共感がある。
彼女は動かないが、時間が彼女のまわりを勝手に流れていく。
そこには恋を成就させるよりも大事なものがある、といった塩梅だ。
恋が時間へと変換されていく瞬間を、彼女はその姿勢だけで示してしまうのだ。
時代、場所、そして空気。
すべてが抑制と緊張をおびながら、イメージと情感だけで戯れ合う。
それを受けて立つトニー・レオンとの関係が
ウォン・カーウァイ作品での頂点を極めるほどに成熟しているのはそのためだ。
語られすぎた美を引き受ける女優
一方、この節度ある身体性は、1930年代の中国無声映画の大スターを演じた
スタンリー・クワン監督「ロアン・リンユイ/阮玲玉」においては
まったく別の緊張を帯びていた。
いみじくも、ロアンがしばらく端役に甘んじていたように、
マギーもウォン・カーウァイに出会わなければ並の女優で終わったかもしれない。
ドキュメンタリーとフィクションが混在する構成の映画の中で、
冒頭で、マギー自身、私と一緒ねと笑う。
だが、ロアンのように、記憶に残るような女優像には固執しないと言い切る。
彼女は演じることを実にクールに見据えている女優である。
ここでマギー・チャンが演じる阮玲玉は、沈黙によって守られる存在ではなく、
むしろ、語られすぎ、書かれすぎ、消費され尽くした身体として果ててしまう。
新聞、スキャンダル、世間の視線。
彼女は立っているだけで、社会に切り刻まれていく存在だ。
それでもマギー・チャンの立ち姿は崩れはしない。
壊れるのは人生であり、尊厳ではないのだと。
『花様年華』が「語られなかった女性の尊厳」だとすれば、
『阮玲玉』は「語られすぎた女性の悲劇」を描いた映画だ。
この両極を、同じ女優が引き受けて成立させてしまう。
その事実こそ、彼女が単なるスターではなく、
映画史を背負える女優であることの証明になるだろう。
文化を脱ぐ身体
マギー・チャンを「永遠のアジアンビューティ」と呼ぶことは簡単なのだが
彼女自身は、そのラベルを内側から解体してきた女優である。
それがフランス人作家オリヴィエ・アサイヤスとの仕事で顕著になる。
アサイヤスとは、この映画を通じて、公私にわたるパートナー関係を築き、
名実共にインターナショナルな女優になった。
『イルマ・ヴェップ』では、彼女は、香港スターという記号をまとったまま、
フランス映画の現場に立った。
ラテックスのキャットスーツはセクシャルでありながら、
どこか空虚感につつまれる哀しき身体性を誇った。
彼女は「エキゾチックなアジアの女優」であることを演じつつ、
その期待を裏切ってゆくしかないのである。
同時に、彼女はその困惑をフィルムに定着させている。
美しいが、固定されない意味。
ここで彼女の身体は、文化と文化のあいだを幻影のように漂うのだ。
さらに『クリーン』では、スター性すら剥ぎ取られてしまっている。
彼女はもはや象徴ではなく、傷を負った人間としてそこに裸のまま立つしかない。
薬に溺れ、愛する子供を手放さねばならなかった母親として
彼女は自己復権を試みるのだが、それでも画面は崩れない。
だが、美の女神としては、それは許されないのだ。
彼女の美しさは若さや華やかさではなく、姿勢そのものに宿るのだと
改めてそのことを証明してみせる。
永遠のアジアンビューティ
ここでようやく、「永遠のアジアンビューティ」という言葉を再定義できる。
それは、若さを保存した身体でも、
エキゾチシズムに耐える顔立ちでもない。
マギー・チャンが特別なのは、なんなのか?
香港の倫理をまとっても成立し、上海映画史を背負っても崩れず、
ヨーロッパの視線に晒されても消えない女優魂。
つまり、彼女の美は文化に従属しない立ち姿を獲得したことにある。
彼女には、常にどこかに属しながら、完全には回収されることはない強さがある。
その「宙づり」の状態こそが、彼女をその永遠性のもとに輝かせるのだ。
マギー・チャン、だが、漢字では張曼玉。
同じアジア人として、永遠のアジアンビューティと呼びたい思いが込み上げる。
マギー・チャンとは?
『花様年華』と『阮玲玉』、そしてアサイヤス作品を貫いて見えてくるのは、
時代や文化が変わっても、立ち姿だけは更新不能な女優であるという事実だ。
彼女の映画を思い出すとき、ぼくは台詞や筋よりも先に、
まずは廊下に立つ背中、静かに佇む横顔、
何も語らず時間を引き受ける身体を思い浮かべることになる。
それは記憶の中で、決して老いることはない。
なぜなら彼女の美しさは、
消費される瞬間ではなく、耐え続ける時間のなかに宿っている存在だからだ。
彼女はけして「美しさとは何か」を更新してゆくタイプではない。
美しさが、どこまで沈黙に耐えられるかを問い続けてくる女優だ。
彼女は『クリーン』以後、アサイヤスとの関係も整理し女優業をも休業する。
2014年にはロックバンドのボーカルとして歌手デビューしているが
彼女の立ち姿は相変わらずだ。
ただ、スクリーンに佇む永遠性は、記憶の中にだけ住み続けている。
まさに、遠い日の淡い恋煩いのように、
いまなお、ぼくの記憶の周りをひたすらふわふわ漂い続けている
そんな女優なのだ。
Nat King Cole – Quizas, Quizas, Quizas
『欲望の翼』ではザビア・クガートの楽曲が、『恋する惑星』では、ママス&パパス「夢のカリフォルニア」が、そして、『花様年華』ではナット・キング・コールの「Quizas, Quizas, Quizas」が。耽美な映像主義なウォンワールドにはラテンナンバーやエキゾチックな音がよく合う。Quizásとは、「たぶん/もしかしたら」という意味の言葉だが、ここにはYesでもNoでもない、決断を先延ばしにする、もしくは感情を確定させないという映画の骨子に合致した選曲でもあるのだろう。香港という多言語・通過点の都市性に贈る、属性の曖昧さが、映像の孤独とともに、心に迫ってくる。まさに、カーワァイのセンスに脱帽するしかない。


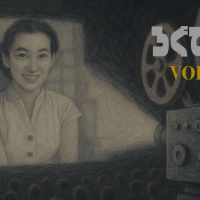










コメントを残す