あまりにも勝新的な人。こんな男、ちょっといない
自ら「勝プロダクション」を創立し、
演じる側から撮る側に方向転換を図った、
(結局演じることはやめなかったが)
勝新の記念すべき監督第一作が『顔役』である。
かねてから想像でふくらませていた、
このぶっとんだ内容との評判の映画を観たときの、
これは保存版興奮記録である。
のっけから、実録、生の賭場を、
ドキュメンタリー映画のような質感で幕をあげる演出。
その後、ラストまでのあいだ、
なにがどう起きているのかさえ定かではないまま、
気づくと映画が終わっている。
が、なんなんだこりゃ?
そう叫ばずにはいられなかった。
とんでもない映画を観てしまったという思いで、
なかなか席から離れられない。
感動に打ちひしがれたのではない。
そんな生易しいものではない、
開いた口が塞がらない、とはこの事だ。
もちろん、いまなおもその興奮がさめやらない。
『顔役』は、おそらくもって
全く何にも似ていない映画に似ている。
今となっては、監督勝新太郎は、
再発見を余儀なくされる奇才というのか、
異端な映画人のひとりであるだけではなく、
もっと映画の神様に愛でされてもよい人物として、
記憶され、検証され、語られねばならない、
そんな稀少な作家だという確信がある。
少なくとも、こんな映画に、自分はこれまで出会った事がない。
一緒にかかっていたのが勝プロ第二弾、
『新座頭市物語 折れた杖』(二本立てだった)では、
曲がりなりにも分かりやすい様式があった。
市は悪を斬るという使命からは逃れえぬ運命にあった。
が、『顔役』にいたっては、
それまで積み上げてきたものを、
すべてくつがえす、大胆な遊びのパッチワークなのだ。
花会(花札博打)だの手打ち式だの、
いわば“その道”の指導を受けたというべく、
そのものずばり、生々しい空気をフリーハンドキャメラでリアルになめる。
タイトルバックから「これはあかんやろ!」
といったある種のヤバい空気が充満していたのだ。
クローズアップの嵐、大胆な色彩と音響、そして映像へのこだわり。
なにしろ、広角の手持ちカメラの大胆な揺れが、
観るものたちへ、心地よいものを避けろと言わんばかり、
これでもかこれでもかと、終始イメージの氾濫で画面を覆い尽くす。
やりたいことをやったまでだ、といわんばかりの勝新スタイルに、
既成の映画の文法は微塵もない。
ましてやあのアクションスター勝新の、
すかっとしたエンターテイメントなど影も形も無い。
勅使河原宏のよる『燃えつきた地図』で
勝新が、はじめてアクションを捨てた、というべきか
失踪者の行方を追う興信所の探偵役という非アクションのなかで
不条理な人間関係の合間を彷徨する役を演じ、
いつもとは勝手が違う芝居に挑戦したのも覚えている。
勅使河原宏の手法に感化されたのか、
そこから勝新の野心は、究極の映画作家への道を余儀なくされる。
その後アイデアの横溢した実験的な映像を
深く追い求めていった原型がそこにある。
勝新演じる刑事立花は、座頭市がそうであったように、
正義と悪を超越しながら、ストーリーなどあってないような展開を突き進む。
ラストシーンには、言葉を失ってしまう。
荒野にうがった穴に、車ごと突入。
大淀組の組長・山形勲を埋めて足で踏みならす、
ここには正義の解決からはほど遠い、刑事ドラマの終焉がある。
ポスターには「ギャング映画」とあったが、それを信用しては痛い目に遭うだろう。
まるで映画そのものを、敵視するかのようなショットの数々。
これをして、勝新式のエンターテイメントの完成か?
なんと革新的か。
いや、おそるべきカツシン的な映画、なのだ。
『燃えつきた地図』がよく分からない映画、だとすれば
『顔役』は、分かろうとする事を放棄すべき映画、に思える。
『新座頭市物語 折れた杖』がヒーローが自意識にがんじがらめになりながら
美意識を極めるように、
『顔役』は、映画=娯楽の限界を求めれば求めるほどに遠ざかる
パラドキシカルさを恐れない実験であった。
勝新太郎という才能の視線、
そのもののドキュメンタリーであるかのような作品として作られている。
勝プロが倒産したのは、
予算の超過によるものが大きかったといわれるが、
こんな感覚に、理解が集らなかったのは、むしろ当然のように思える。
残念なことのようであり、正当な評価であるようでもある。
こんな前衛に、つきあわされたスタッフの苦労には同情する。
が、仕事を度返しして、その現場の一員たりたかったし、
その空気を吸ってみたかった。
おそらく、歴史の目撃者たりえたという充足があっただろう。
おそらく、ほとんどのものが、
いったいこれが何を目指した映画なのか、
理解する術など持ってはいなかったのは間違いあるまい。
とはいえ、早すぎた才能、行き過ぎた才能、
破滅への衝動を孕んだ『顔役』こそは
いうなれば勝新太郎の行く末を予言した
真の映画作家たる呪われた作品なのだ。
このすっきりしない思いは
八十年代のテレビドラマ『軽視-K』へと受け継がれるが
そこでもまた、勝新は繰り返す。
いや、これが自分のやりたいことだと突き進みながら、
そうして、勝手に追い込まれてゆくのが勝新なのだ。
呪われた作家の歩き方を最後まで地で行く人であった。
さりとて、あまりにも勝新的な人。
こんな男、ちょっといない。
Mark Goldenberg - Queen Of Swords
この曲はもう今から50年ぐらい前、サントリーのCMで使用されたマーク・ゴールデンバーグによる「Queen Of Swords」という曲で、どこかエキゾチックに響くのは、詩人ランボオをさかなにつくられた砂漠の商人のイメージの強烈さをいまなお、鮮明に覚えているからかもしれない。そのキャッチフレーズが「こんな男、ちょっといない」だったので、それをパクって勝新にあてはめてみた。ランボー=勝新は、ちょっと“乱暴”なものいいかもしれないが、似て遠からずといったところか?
ちなみに、この曲は『鞄を持った男』というアルバムに収録されていて、ぼくはレコード盤をもっている。ちなみにこのランボオ篇に続いて、ガウディ篇、ファーブル篇とあったのかな。どれもが素晴らしいCMだったな。マーク・ゴールデンバーグという人はジャクソン・ブラウンのバンドでギターを弾いていた人で、通りでセンスがいいのだと知ったものだった。
その詩人は底知れぬ渇きを抱えて放浪を繰り返した、
限りない無邪気さから生まれた詩、
世界中の詩人たちが青ざめたその頃、
彼は砂漠の商人、
詩なんかよりうまい酒をなどとおっしゃる、
永遠の詩人、ランボオ、
あんな男、ちょっといない、
サントリー・ローヤル
素晴らしい映像とキャッチコピーだった









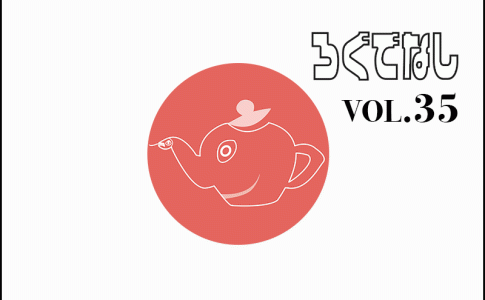



コメントを残す