ホームはいずこへ?
秋になると、昔のドラマが見たくなる。
新番組に切り替わるタイミングだからだろうか?
テレビそのものを見なくなって久しく、
最近のドラマ事情はよく知らないのだが、
昭和世代にとっては、かつてはテレビドラマは一家団欒のネタであり、
ちゃぶ台を囲んでの、ささやかな楽しみのひとつだった。
同時に、家族間でのささいなチャンネル争いのタネでもあった。
むろん、ドラマならなんでもいいというわけではない。
こちらは、今から半世紀も前のテレビドラマだというのに、
なぜか、どこかで見た風景が映し出されていて、なにかと心に刺さる。
じつに近しく、生々しく、内容は実に骨太である。
のちに流行るトレンディドラマと呼ばれるものとは一線を画す内容の、
脚本家山田太一の傑作『岸辺のアルバム』という作品について触れてみよう。
当時、リアルタイムに見ていたわけではないが
改めて見直してみて、懐かしい思いと共に、
息を呑むような、登場人物たちの表情や言葉、その空気感というものに
知らず知らずはまってゆく自分がいる。
そう、まさにこれが山田太一脚本の奥行きと巧みさであろうか?
一昔前の、まさに、見慣れた昭和の風景でありながら、
自分が当時呼吸していた空気感までが、どこかで重なってくるのだ。
同時に、当時どんな家庭にもあった、現実と理想の狭間で、
どこか胸が痛くなるような切実な想いがこみ上げ
リアルに胸を締め付ける瞬間がある。
遠くて近い、近くて遠い、何かと何かが触れ合うあの痛み。
簡単には語り尽くせない人間間の感情、そして家族の在り方。
そんなひりひりする気配が『岸辺のアルバム』にはあるのだ。
昭和一桁生まれの、今は亡き父親とは
生前ほとんど、接点のないままにすごしてきたのだが、
今となっては、懐かしく思い出すことも増えた。
文化的な共感など、なにひとつ覚えがないのだが、
なぜだか八千草薫が好きだといっていたことだけを記憶している
ドラマなんて、女子供のみるものだと高を括っていた父だったからか、
なおさらその言葉を覚えているのだ。
とはいえ、父が『岸辺のアルバム』にハマっていたわけでもなく、
おそらくは、世間の「良妻賢母」という、
マスコミが作り出した理想像だけを共有していたのだろう。
彼女の、どこがどう好きかを聞かされた記憶もないのだが、
そもそも、当時は、僕自身が八千草薫という女優にさして興味などなかった。
そんな彼女がちょうど数年前に、88歳で亡くなったのがきっかけで
この女優のことがなんとなく気になり始めたのである。
たしかに、おっとり、ふんわりした空気感をもっていることは周知の通りで、
それは彼女が出ていた数々のドラマからも十二分に伝わってくるし、
またぞろ、こちらとしても、嫌な感情を抱く筋合いもない。
特別な感情こそもっていないのだが、
たとえば、『前略おふくろ様』で演じた料亭の未亡人女将だとか
『阿修羅のごとく』(NHK の土曜劇場版)での次女役
(森田芳光による映画版では母親役を担っていた)だとか、
寺山修司の『田園に死す』での人妻役だとか、
総じて、自分が好むいくつかのドラマや映画を通じて
彼女が演じてみせたその空気感には親しみすら感じていた。
今思うと、やはり、あれがこの女優固有の
「誰からも愛される」雰囲気だったのであり、
当時、家庭を強く求める男性像からの視線を浴びた雰囲気のままに、
元祖癒やし系女優であったことが思い返される。
あの当時、良妻賢母、お嫁さんにしたい女優というキャッチフレーズが
世間には横行しており、その代表としては、
竹下景子や市毛良枝などを懐かしく思い浮かべるが、
なかでも八千草薫という人は、親近感と品格とが
同時に備わっていたという意味では格別で、実に稀有な女優だったのだと思う。
たしかに、この人の醸すオーラには、
かつてのホームドラマに不可欠なキャラクターとして重宝されていたこともあり、
そのこと自体が、当時の時代の空気感をも言い表している気さえするのだ。
そんな八千草薫の役どころのなかで、
この『岸辺のアルバム』でみせた不倫劇は、
先にも後にも、異色というか、強烈なインパクトを放っていたように思う。
なにしろ、作中でも、いつもどおりのパブリックイメージを保ち
良妻賢母たる母親、そして妻を演じながらも、
ふとかかってきた電話で知り合った見知らぬ男との逢瀬をくりかえし、
大胆にもラブホテルへと繰り出すといった、女としての艶を醸し、
堂々、ホームドラマで不倫劇を演じたというこの衝撃度は
いまふりかえっても、大胆で、信じがたいほどである。
おまけに、このドラマには、男を買うことで自我を慰める女友達、
あるいは白人留学生にレイプされ堕胎する長女、
裏で東南アジアから風俗業の女性を輸入し、
売春を斡旋する会社に勤める父親といった、
今思えば、ショッキングな背景が盛り込まれており、
子供には少し理解し難い大人の事情がベースに描かれていたのだ。
同時に、このドラマは多摩川水害という
実際に起きた事実に重ねられていることもあって、
いまだ語り草になっており、時代の空気はさておき、
さほど古臭さを感じないリアルさが突きつけられる。
山田太一が手がけたドラマのなかでも、特筆すべき作品であり、
昭和を代表する名作ドラマだということに、異論はない。
話は全15話のエピソードで構成され
多摩川べりに一軒家を構えた4人構成の中流階級家庭田島家の4人に、
それぞれ順繰りにドラマがおきてゆく。
国広富之演じる長男である繁は受験を控えた高校生である。
この長男は、この家族すべての事件、出来事に関与して
その目を通し、家族の崩壊へと一気になだれこむ。
四人のなかではもっとも情緒不安定であり
逆に、もっとも人間らしい情緒を振り翳す人間として描き出されている。
母親の不倫にだれよりも強く反応し、父親の欺瞞に口を挟み、
それゆえに中田喜子演じる二歳上の姉律子に、
いくどもたしなめられるような振る舞いで、
いつもどこか子供じみてはいるキャラクターだった。
だが、それは母親や父親の振る舞いそのものが耐えられないのではなく
自分の周囲で、欺瞞が横行しているのが耐えられない、
そんな正義感と若者特有の不安定さの狭間で
ナーバスに揺れ動くキャラクターを体現していたのである。
当然、若き反抗は成長儀礼にすぎない。
一方、昭和の不器用で融通の利かない父親を演じさせることで、
リアルな哀愁を漂わせる杉浦直樹演じる父親謙作は、
いわば仕事人間で、家族を垣間見る余裕も時間もなく
休日さえ仕事の名の下に会社に捧げ、家庭を顧みない男である。
すべてが会社のため、家族のためという名目に後押しされている人間である。
あげくには、自分を掲げた理想は、もろくも崩れ去り
社会の目をくぐった不当な取引によって
会社そのものが窮地におちいってゆくなかで、
河川の氾濫によって、個のアイデンティティである家という
“絶対”のものまで流されてしまうという結末を迎えることになる。
『岸辺のアルバム』におけるこうした家族の崩壊は、
単なる人物間の対立や事件ではなく、
山田太一が見据える社会像のなかに描き出された家族モデルとして、
家そのものの「構造物」が崩れゆくさまが
その時代のゆらぎをともなって丁寧に描かれているのだ。
その中で、八千草薫の母親役が象徴する価値観と倫理観は、
それが崩壊していく過程を、自然災害という比喩を通して表現することで、
ただの家族劇を超える深い哲学的、心理的な洞察を提供するのである。
『岸辺のアルバム』は、脚本家山田太一にとって、
日常の中に潜む心理と関係性を、
一見幸せそうな、どこにもあるような家族を通し描くことで、
そこから人生の本質を浮かび上がらせる脚本手法がとられている。
よって、ハッピーエンドでもなく、
そこからの再生すらも描き出されはしない。
「家そのものよりも、家族のアルバムを失ったことのほうが辛い」
実際に被災した家族からの言葉が作品の核になったといい、
そのなかで、妻で母親である八千草薫の不倫劇は、
その核を視覚化し、感情を直接的に伝える役割を担わせ、
家族の崩壊、倫理の揺らぎ、物理的な家の決壊の間に立たせた。
こうした危うさを、あえて女の立場から重層的に描くことで、
視聴者は単なる家庭劇に、いっそうの衝撃を受け、
より普遍的な人生の真実に触れることになったのだ。
家というものが、男のロマンでも、父権の甲斐性でもなく、
家族そのものの象徴であるということを描き出したという意味で、
昭和のテレビドラマ史に燦然と輝ける傑作になったのである。
Will You Dance: Janis Ian
ドラマのオープニングに流れる、ジャニス・イアンの「Will You Dance」。フォーク・ロックのスタイルを色濃く反映した楽曲だが、一見希望や愛を象徴するこの旋律は、物語の展開と重なることで、逆に皮肉な響きを帯びてゆく。社会の矛盾や人間関係の複雑さを表現する内容が歌われている歌詞には、上流階級の贅沢な生活を象徴する「caviar and roses(キャビアとバラ)」や「light fantastic in the morning(朝の幻想的な光)」といった表現の一方で、「how romantic to be whoring(売春がどれほどロマンチックか)」や「boring though it may be(退屈かもしれないが)」といった皮肉な表現もあり、社会の偽善や人々の虚飾を批判する内容がドラマの核心とリンクしていることがわかる。
また、「who’ll survive if you and I should fall(もし私たちが倒れたら、誰が生き残るのか)」という問いからは、本来、夫婦や家族が人生の旅路を共に歩む象徴である曲が、母親の裏切りによって途切れた信頼のリズムの中で、虚ろに響くが、同時に「Take a chance on romancel(ロマンスに挑戦しよう)という皮肉も覗く。『岸辺のアルバム』は、この音楽の皮肉な対比を通じて、家族の倫理の揺らぎと心理的崩壊の哀しさを一層際立たせたのだ。ドラマにおける音楽の重要性もまた、名作には必須である事を証明する選曲だといえよう。







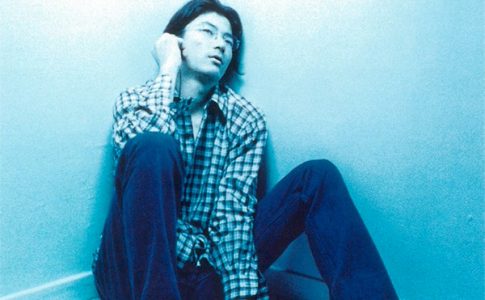
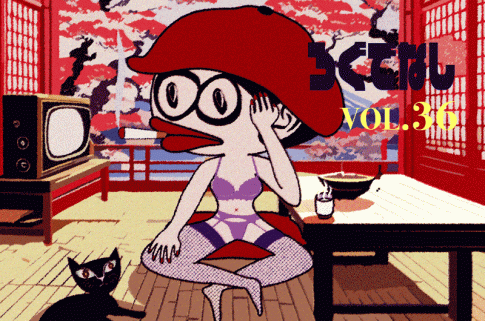




コメントを残す