行け柳田!
『碁盤斬り』と聞いて、最初勝新の座頭市を思い浮かべていた。
なにしろ、あの分厚い碁盤を真っ二つに斬るなんざ
安易な芸当ではない。
居合の達人たる市にしても、よく考えれば、ほぼ漫画の世界である。
もちろん、そこがザッツエンターテイメントとしての華でもあるのだが。
その一方で、この白石和彌監督の『碁盤斬り』は、
江戸情緒を漂わせ、武士道たる死の美学をちらつかせながら、
硬質で静謐な映像に、怒りにも似た倫理的な問いながらに、
異色の時代劇へと押し上げることに成功している。
主演元SMAPの草彅剛が、ここでは脱アイドルの完了形として、
演技における沈黙と間の巧みさ、
言葉を選ぶように語る誠実な声によって、
「語り」の本質を体現しているかのようにみえる。
そこは、ただの演技巧者というより、
どこか“語り部”のような存在として、浪人を体現している。
それは、語られざる誇りと、語りえぬ悔しさ両方を滲ませ臨む
男の美学、すなわち武士の覚悟そのものである。
碁盤という網の目に移し、静かに白黒をつけんとする姿勢は
最後、格之進が振り下ろした刀の結末として
だからこそ、いっそう清々しさを禁じ得なかったのである。
本作は、『凪待ち』に続いて2度目のコンビである、
自らも囲碁ファンであるという加藤正人のオリジナル脚本で
白石監督が渾身の演出で初の時代劇として仕上げたものであるが、
その背後にはもうひとつの影、
すなわち、古典落語『柳田格之進』があらかじめ下地にあっての物語だ。
映画と落語は、確かに物語の骨格を共有している。
濡れ衣、冤罪から、汚された浪人としての名誉回復、父娘の絆、
そして命をかけた魂の清廉の証明。
しかしその表現の方法と語りの重心は、どこか異なる方角を向いていた。
落語における『柳田格之進』は、庶民の倫理と人情譚そのものである。
一方で、草薙が演じた浪人の格之進は、誠実で実直な男、
ゆえの苦しみ、ゆえに身を焦がす。
娘との清貧な暮らしのなかでも、義を重んじ、冤罪をも正しく晴らそうとする。
娘が自ら吉原に身を売ってまでも、父を救おうとする共闘の姿に、
われわれ観客は胸を打たれはするが
最後には晴れて冤罪が解け、父娘はめでたく心一つになることで、
その晴れやかさと涙、そしてほのかな和みさえ混ざるラストの転調に
これぞ落語的ヒューマニズムの結晶をみる。
だが映画『碁盤斬り』の格之進の核はことほか重い。
彼の沈黙は、語られぬ痛みに湛えているといった風情が漂うのだ。
語らなかったがゆえに失われた名誉を命懸けで回復し、
そして誰にもわかってもらえなかった誇りを守り抜く。
武士という誇りゆえに背負う十字架と格調。
時代劇における武士道という様式が、
ここでは一種の“倫理の劇場”、“倫理の悲劇”にもなっている。
武士道とは、ただ死をもって潔く清算すればいいというわけではない。
それは「語るべきこと」を、義に沿って
死という臨場感をもって臨む礼節なのだと証明したかったのだ。
ここで強調されるべきは、「囲碁」というゲームそのものが、
本作においては単なる背景ではなく、
格之進の内面を映す鏡となっているという点だろう。
ひとつ残念なのは、この映画においては
囲碁そのものを知らないものにとって、
その理解が十分に行き届かない点にある。
囲碁とは、静かな盤上で繰り広げられる沈黙裡の駆け引きであり、
相手を打ち負かすというより、自分の地と場を整えながら、
いかに美しく終局へ向かうかを競うゲームであるのだと解釈すれば、
格之進の生き方は、まさにこの囲碁の精神そのものであり、
そこに乱れることなく、じっくりと布石を打ち、
目先の勝利よりも、まずは己が信ずる形を築いていくことにある。
まさに、武士道にも相通じる美学を通して、
彼が守り抜いたものは、実は名誉などではなく、
盤面の美学、すなわち“生き方の道”に他ならない。
そもそも、囲碁の美は、結果よりもその過程にあると格之進は考える。
たとえ敗れたとしても、美しい碁形を残した者こそ尊ばれるのだ。
格之進もまた、自らの命を懸けて語り、また沈黙し、
最後の一手を静かに置く。
ときには、勝負を放棄してまでも美学を貫こうとする。
その姿は、棋士として、人として、凜として美しい。
彼は復讐に勝負をかける際も、その思いは崩さないし、勝ち誇りもしない。
敵はその思いの前に自滅するほかないのだ。
落語では、冤罪の理由そのものより
少しの誤解、ちょっとした手違いによって物語が展開する。
ただ、格之進の正義は、単に「筋が通っている」だけでは済まない。
いくら武士としての気構え、倫理を説いても、信用は勝ち取れない。
その現実が敵をもつくり、身内さえも苦しませているのだ。
守るべきはプライドか、それとも美学かにゆれる。
彼の不器用なまでの実直さは、
囲碁の精神をもって常に布石を打つしかできないのだ。
このような背景のなかで、今回、草彅剛という俳優の存在は特筆に値する。
彼の代表作『ミッドナイトスワン』においても、
静かな激情を湛えた人物を演じていたが、この『碁盤斬り』における彼は
さらに一段深く、“沈黙を語る”演技に徹している。
目線、手の震え、呼吸、わずかな声の揺れ。
それらが観客に語るのは、言葉にできなかったものすべてだ。
この草彅の持つ“どこか現代的な佇まい”も見逃せない。
時代劇においては異質に見えるその質感が、
逆に本作ではリアリティを高める要因にもなっている。
現代の観客が感情移入するための“橋”として、そこに自らの存在意義を示す。
この『碁盤斬り』のクライマックスは、言わずもがな、碁盤斬りの場面である。
碁盤の前に正座し、覚悟を決め首を揃える主人と奉公人二人に
それまでの憤りの矛先を、彼らではなく、碁盤へと向ける。
草彅のキャリアの中でも屈指の名場面といえるだろう。
それは声高に叫ぶでもなく、自らの怒りにさえ決着をつける、
痛切な生き様へと昇華された一刀である。
彼は人情から、碁盤を斬ったのではなく、
あくまで、己れの審美を全うしたのだ。
観客は、彼の声と呼吸のあいだに、静かに胸を打たれるだろう。
これぞ映画におけるオチである。
ゆえに、『碁盤斬り』は落語噺に敬意を払いながらも、
それを新しい地平へと押し広げた作品だといえるだろう。
勧善懲悪ではない、赦しの物語。
名誉回復から、失われかけた誇りへの弔いへ。
笑いでは包みきれない、生きることの誠実さにある重みを説く碁盤斬り。
落語では、晴れて住み慣れた彦根藩に復職し、
江戸留守居役として幸せに暮らす話だが、
ここでは最後に娘絹と弥吉の婚姻を見届けて、姿を消す格之進。
はたして、彼はヒーローとして去ったのか?
それとも巡礼者、あるいは世捨て人としてなのか?
もし落語が話芸によって「語り継ぐ物語」だとするならば
この映画は沈黙をもって理を説く、
「一度しか語りえぬ切実で不器用ゆえの譲れぬ体験」
とでも呼べばいいのだろうか?
いうなれば、前者は他人軸、後者は自分軸の物語である。
そして草彅剛の格之進像は、語ることで語りえぬものまでを浮かび上がらせた。
文字通り“声の遺言者”として、その縁に立っていたのは間違いない。
草彅剛という個性が、今までこちらが思っていたイメージからは
ちょっとばかし隔たって前を歩いていたのだ。
その風格によって、改めて、『碁盤斬り』での話の格調が
保たれたのだといっていい。
それはちょっとした新鮮な驚きであった。
古今亭志ん朝:柳田格之進
古今亭志ん朝の『柳田格之進』は、武士の誇りと庶民の情とが交差する名品として、また、語りの美と沈黙の倫理を凝縮した一席として、
まさに「落語でしかできない人間描写の粋」を感じさせる。
これを聞けば、映画『碁盤斬り』が、この語りを受け継ぎつつ、さらに「沈黙のままでは済まされない時代」への応答として、“語るべき死”を提示した作品であることがより深く理解できるだろう。
矢野顕子:行け柳田
たかが浪人、されど武士。映画での柳田様はその面目を携え、無事面目を保った。が、もう少しユーモアの振り幅があれば、と思わないでもない。そこで、この曲をあえてぶつけてみた。ジャケットからして、ものすごいインパクトがある。矢野顕子の『いろはにこんぺいとう』に収録のこの「行け柳田」、今聞くと、これは単にジャンアンツへの応援歌だということに気付いた。自分は巨人ファンでもないし、むしろアンチの方だが、そんなことはこの際どうでもいい。ちなみに、この柳田とは、「巨人史上最強の五番打者」、マムシと呼ばれた柳田真宏のことである。音楽的には、ドラムで林立夫のドラム以外、矢野顕子の天才的プレイがお披露目されている。イントロや間奏のモノフォニック・シンセの音色の素晴らしさ。これがのちにYMOのワールドツアーに参加することになるキーボーディストの技なのかと思うと、なんとも感慨深いものがある。







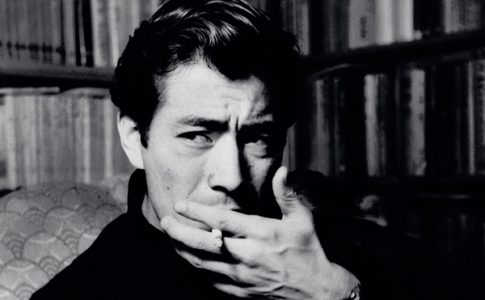





コメントを残す