天上のささやき
静寂の中を、何かがふと通り抜ける。
風か、精霊か、はたまた錯覚か?
ときおり、誰かに呼ばれたような気持ちがする。
孤独を感じるものなら、誰だって経験することではないか?
それは耳ではなく、心の奥に触れてくるなにか。
誰かが見ている、誰かが寄り添っている、そんな思い。
それは良い意味で、ひとを孤独の淵からひきあげてくれる光である。
けれどその誰かとは、この世の存在であるとはかぎらない。
入江悠の映画『あんのこと』を観たとき、
街を彷徨う一人の女の子の後ろ姿に言い知れぬ孤独を感じた。
シャブ、売春、不登校、彼女の闇はことのほか深い。
ぼくはその“誰か”の視点でこの映画を受け止めたいと思った。
それはヴェンダースの『ベルリン・天使の詩』のような、
誰にも知られず、触れられず、完全な他者として
ただ見つめることしかできない天使の視座として、
あんという女の子を見届けようと思った。
でも結局、ぼくらは何もできないということを知るだけである。
この世界では、それは絶望という言葉に置き換えられる。
この映画は、実在したひとりの若い女性の自死事件をもとにしている。
その本質は、事件の再現や社会制度の告発なんかじゃない。
ひとりの女性が、名もなき日々の中で、なぜこの世を去るに至ったのか?
そのとき、彼女にとって、社会は同映っていたのか、
その静かな問いを、観る者の内側に投げかけてくる映画なのだ。
あん、それは彼女の名前であり、
同時に「誰かのこと」という匿名性を孕んだ言葉でもある。
彼女は、家はあるが、帰るべく家がなかった。
母と祖母、名ばかりの家族はあるが、そこに温もりなど感じられない。
エゴイズムと長年の心のスレで、とっくの昔に愛を見失っている母親。
自分の娘を“ママ”と呼ぶ異常さに、幼児性と支配性を漂わせながら、
その暴力は、肉体と精神を同時に病ませるに十分なまでに非道で、
あんの人生は、今でいうこの毒親の犠牲者といえばそれまでだ。
彼女は、その魔の手から逃れようと、助けを求める言葉も持たず、
ただこの世界に在りながら、何かより所を切実に求めて彷徨っていた。
だがその思いは、社会の制度や人の善意の手のひらから、
ことごとくこぼれ落ちていってしまう。
この社会が支配する重力は、弱いものたちが簡単に跳ね返せるものではない。
ひとはそれを無責任に同情という名の偽善にすり替えるだけだ。
そんな河合優実演じるあんを助けようとする者もいた。
それが佐藤二朗の多々羅である。
彼はただの刑事だが、少し常軌を逸した男である。
言動や態度は粗野きわまりなく、取り調べにヨガを持ち出す。
確かに、胡散臭い。
確かに、信用できないところが満載である。
が、彼は“傷ついたものを救いたい”という個人的な祈りを胸に、
彼女に寄り添おうとしたのもまた間違いない。
そんな怪しい灯りにでも、心は動く。
仕事探しに躍起になり、電話をかけ、顔を見に行き、心を砕く。
だが、制度という枠組みの中では、それ以上のことは許されない。
ゆえに、差し出した手は途中で空を掴む。
その指先に触れることはなく、あんはふたたび深い闇を彷徨うのだ。
もう一人、彼女を見つめる者がいた。
外側から社会の構造にメスを入れようとする者。
稲垣吾郎演じる桐野というジャーナリストだ。
こちらはその多々羅の悪い噂を嗅ぎつけ取材を重ねる、
いわば、ふたりの間に立つ存在だ。
彼のまなざしは冷静で、正義感に満ちている。
愛もある。
あんのことも“ひとつの社会問題”として見つめ、
力になろうとするが、そこにあんという個人の痛みが
どこまで切実に響いていたかは定かではない。
しかし、桐野の正義から多々羅はすべてを失い、
それが彼女の死に直結したのかもしれないと胸をいためる桐野。
制度の内側から寄り添おうとはしたが、己の欲望にも負けた多々羅。
結局、どちらもあんを救うことはできなかった。
その無力さの痛みが、この映画全体を沈痛に包みこんでいる。
この構造は、奇しくもコロナ時代のわれわれ自身の姿とも重なる。
パンデミックは、社会のつながりを断ち切り、支援の網目を広げてしまった。
「誰かのこと」への関心は、感染への恐れや経済的逼迫の中で後回しにされ、
孤独が日常的なものとなった。
この映画では、そのあたりの事情がなまなましく関与している。
『あんのこと』が刺さるのは、まさにその孤独を正面から描いているからだが、
助けを求める声があれど、その声は、マスクの下に、閉ざされた社会に、
そして制度の外側に、置き去りにされていたように思える。
この現実は、つねに理想からずれてゆくものとして扱われるのだ。
映画の中で、あんは叫ばない。叫べない。
崩れもしないし、 ただ、淡々と存在し生きているように振る舞う。
それはメンタルが強いから、ではなく、人に委ねる方法を知らないだけだ。
精一杯のフリなのだ。
しかし、まだ人間としての優しさ、感情は残っている。
だからこそ、アカの他人に無理矢理に託された幼児をなんとか守ろうとする。
同時にそれは弱さに睨まれてしまう。
そんな思いが仇になる。
このやるせなさ、むなしさ。
その神なき“静けさ”が観る者にとっては耳をつんざくように響くのだ。
同時に心も、焼かれた日記のようにボロボロになってゆく。
天使の視点とは、まさにその沈黙を聴く耳を持つことである。
現実から目を背けない意思をもつことである。
声にならない悲鳴を、誰かが聞いていればと、
心あるものなら、そう思わずにはいられないだろう。
この映画は、誰かに肩入れすることなく、
また、だれかを悪人として糾弾する作品ではない。
そこに、あんという存在を、静かに浮かび上がらせることしかできないという
監督の強固な視線がある。
感情移入すればするほどに、痛ましさが一人歩きすることを知っているのだ。
それはけして「お涙ちょうだい」の安っぽいヒューマンドラマではない。
視点はむしろ冷静で、抑制されていることで、
その冷静さこそが、観る者を自分自身へと向かわせることになるのだ。
自分はどの視点でこの映画を見ているのか?
多々羅か? 桐野か? それとも、ただ見ているだけの天使か?
あんを救えなかったのは誰か?
立ち止まってそれを考えるとき、
映画は観る者ひとりひとりに問いを投げかけてくる。
社会はどれだけ制度を整えても、
他人の心の空洞を埋めることはできないのだと。
そして、ラストシーン、ハヤトとその母親が視界から遠ざかってゆくとき、
まるで、あんの眼差しと沈黙が密かに注がれているのを覚えた。
ここでの『天上のささやき』とは、
あんという女性の名もなき命に寄り添った、声なき鎮魂である。
天使の視点なぞ、何も解決しないと思いだろうか?
無責任な共感だと?
だが、見ること、感じること、忘れないこと。
それだけが、あの空虚さを埋める唯一の手段なのかもしれないと
僕個人は思うのだ。
『あんのこと』は、決して過去の事件をなぞる映画ではない。
それは、私たちがこれからの時代にどう生き、
誰に手を差し伸べ、どの声を聞くべきかを問い続ける、魂のドキュメントである。
ポストコロナの世界において、
この映画は一つのささやきとして響いてくるだろう。
それは、誰かの天使になれたかもしれない、という
この見つめるだけの優しさに、ただ溺れないために。
せめて、彼女の日記ぐらいは守ってあげたかった。
それぐらいはできたはずなのだ。
自分自身の記録として、僕はここにその思いを記しておきたいのだ。
Angels Laid Him Away (Louis Collins) :Lucinda Williams
ミシシッピ・ジョン・ハートの「Louis Collins」という、歌は殺人事件で亡くなったルイス・コリンズという男の悲劇を語る古いブルース・バラッドを、ルシンダ・ウィリアムズがカバーした、「Angels Laid Him Away」。この曲は、『アヴァロン・ブルース:ミシシッピ・ジョン・ハートの音楽へのトリビュート』アルバムに入っていた曲で、前から好きだったのだが、歌詞にあるように、南部ゴスペルに通じる「埋葬と救済の儀礼歌」であり、「天使たちは彼を置き去りにした」という部分が、ブルースでよく使われる定番のフレーズは、オリジナルに敬意を払いながら、このフレーズを曲名に据え、より神話的で聖歌のような響きを与えているように思う。そこには、悲劇を超えた慈愛と祈りという側面を感じることができる。この曲を、天使の視座として、映画「あんのこと」に贈りたいと思う。





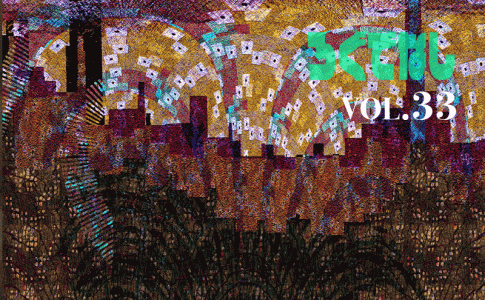



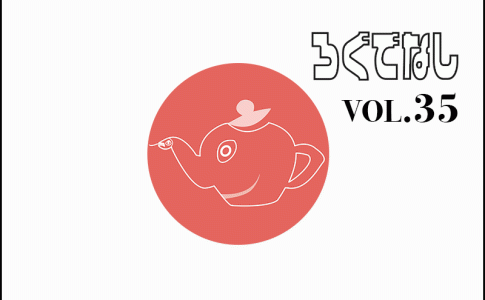



コメントを残す