シネマと歩む二人三脚
コロナ騒動で、実質、自宅が公私共々活動の場になった、
というこの世の中の変化は、リモートという言葉が定着することで、
実に大きな可能性を広げたことには違いない。
それまでの、オフィスに出かけて、その分の時間を消費することさえも、
労働の一部に組み込まれていた、という現実をあばきだした。
とはいえ、全く誰とも会わない、接触さえ禁じられる日々が続き、
まるで実態のない生活を手放しで喜べない世代や考え方もあっただろう。
その意味では、価値観の変化と一言で片付けるにはまだ早く、
その問題から、その短縮された時間、
いうなれば与えれし時間をどう過ごすか?
という根源的な問いへと変換されることになるだろう。
そこで、ひとまず僕は、映画鑑賞という行為を重ね合わせみた。
つまり、映画を見ることもまた、所詮時間の消費にすぎぬのだ。
一時間半なり、二時間という時間を奪われることになるのは、
オフィスワーカーにとっての通勤時間問題と同じ意味を持つ。
仮に、映画に注ぎ込んだ時間に価値を見出せなければ、
単なる時間の無駄だと思うが、その時間こそが、
かけがえのない重みを持つことだってあるはずだ。
映画という娯楽の楽しみ方、感じ方は人それぞれである。
それは隙間時間をどう過ごすか、という意味でも、
映画の見方においても通じてしまうだろう。
そこで、見たい映画をわざわざ街の映画館に足を運んでみるか、
それとも、気楽にホームシアターと化したマイルールで味わうか、
同じ一本の映画に対する向き合い方も、かなり違ったものになるに違いない。
コロナ禍においては、色々な制限が課されていたこともあり、
映画館へ足を運ぶ機会も意欲も、ずいぶん減ってはいたが、
最近では、気分的にも大きなスクリーンで集中してみる映画体験へと
積極的に回帰している自分がいる。
とはいえ、映画を見たい、手軽に見たいという欲望が無くならないが故に、
ストリーミングに頼るという生活もまた、なくなる事はない。
作品を何度も気軽に見直すことができるし、
どこでもかからないような、貴重な作品さえも手が届く。
何より、映画を愛するものにとって、有難いまでの仕組みが多く提供されている。
いずれにせよ、1本の映画作品の価値は、
形態や見方を変えても変わるわけではない。
その本質を見落としてしまえば、
単なる時間の消費に過ぎなくってしまうということだ。
ぼくらはそうやって自由を脅かされた反面、
自由の可能性を広げることができた。
ただし、今となっては
その持て余す時間をどう過ごすのかを試されたという気さえする。
ポストパンデミックで生じた社会の変化は、すでに始まっているし、
それを人々が認識するころには世の中もさらに変わっていることだろう。
そして、だれもが浦島太郎状態になって、はたと気づくのだ。
やりたいことをやれているだろうか?
心に従っているだろうか?
それがあなたのやりたいことなのかと。
いまからだって遅くないはずだ。
映画は社会を反映し、見るものまでをも投影する。
自分を見つめる貴重な時間にもなるだろう。
ただし、見ることが目的になるわけじゃない。
作品を通して、自分が解放される空間をもとめて
それこそがスクリーンの楽園が、自身の未来への扉を開くかもしれないのだ。
Hell You Talmbout – David Byrne’s American Utopia
コロナ渦で見た一本の映画、スパイク・リーによるDavid Byrneの『American Utopia』も印象的な一本なのだが、このなかの一曲「Hell You Talmbout」は、ショーのハイライトでもあり、観客に「Say their name(その名を呼べ)」と繰り返し伝える中、亡くなった方々の写真が大写しにされる、視覚的にも強いインパクトをもったナンバーで、今もずっと心に残っている 。元々はジャネール・モネイ が2015年に発表した、ゴスペル調のプロテストチューンで、人々に警察や人種的暴力によって命を奪われたアフリカ系アメリカ人の名前を「声に出して」記憶し続けようと呼びかけるプロテストソングだ。そんな曲をバーン本人は「最も感動させられる政治的な歌の一つ」と語り、ジャネールにカバーの許可を直談判してまで歌っているのだ。「声を上げること」の重み、「あなたは忘れずにいます」という共感と連帯を生み出すこのグルーブこそ、ポストパンデミックにふさわしい一曲だと思う。
特集:シネマと歩む二人三脚、映画鑑賞特集
- トイレとカセットと木漏れ日のルーティン美学・・・ヴィム・ヴェンダース『PERFECT DAYS』をめぐって
- 愛しのヘルシンキ暮色よ、おかえりなさい・・・アキ・カウリスマキ『枯れ葉』をめぐって
- 血よりも濃い黒の物語・・・ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ『トリとロキタ』をめぐって
- 瞳をとじて、奇跡を見る・・・ヴィクトル・エリセ『瞳をとじて』をめぐって
- 怒り、嘆くより、慈悲深く、そして寛容に・・・クリスチャン・カリオン『パリタクシー』をめぐって
- 走れ、クワイエットガール・・・コルム・バレード『コット、はじまりの夏』をめぐって
- 天上のささやき・・・入江悠『あんのこと』をめぐって
- 水と悪意とフラメンコ・・・荻上直子『波紋』をめぐって
- 常識なんぞ糞食らえ、回し蹴りと笑いで挑む反抗の美学・・・ニダ・マンズール『ポライト・ソサエティ』をめぐって
- 解剖するは我にあり・・・ジュスティーヌ・トリエ『落下の解剖学』をめぐって
- ピンクの黄昏に咲く、哀愁の幽玄譚・・・荒井晴彦『花腐し』をめぐって
- 行け柳田!・・・白石和彌『碁盤斬り』をめぐって
- 虫の知らせに耳をすませろ・・・クリスチャン・タフドルップ『胸騒ぎ』をめぐって
- 蛇の道はヘビー・・・黒沢清『蛇の道』をめぐって
- 記憶の袖に、紫煙の向こう側の風景がみえる・・・5月『宮松と山下』をめぐって
- 十人十色、水で描かれた物語・・・岸善幸『正欲』をめぐって
- 熱烈ジャンプで学ぶ、異色の知覚ロードムービー・・・ヨルゴス・ランティモス『哀れなるものたち』をめぐって
- 視覚の刺客、ウェスティバルムービーショー・・・ウェス・アンダーソン『アステロイド・シティ』をめぐって
- 月にも触れる窓辺の優しさ・・・三宅唱『夜明けのすべて』をめぐって
- 関心にふれる黒の旋律、白の戦慄・・・ジョナサン・グレイザー『関心領域』をめぐって

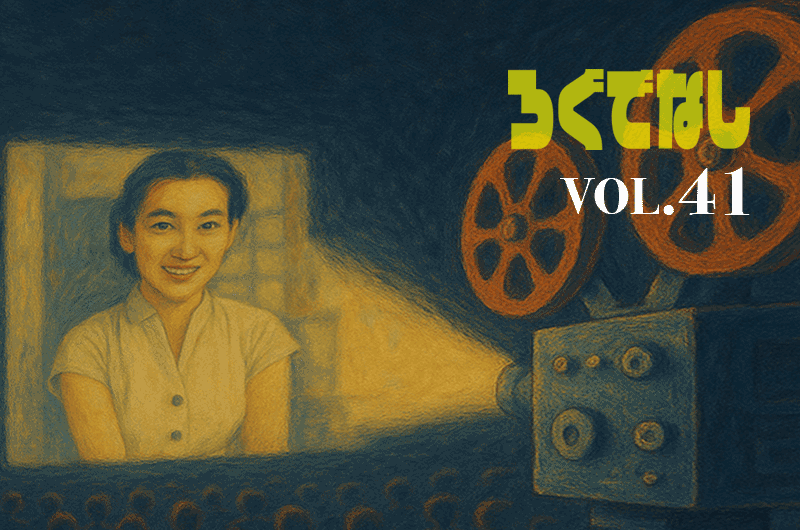











コメントを残す