師に交われば垢抜ける?
黒澤作品のなかでも、人気、評価の高い1本である『赤ひげ』は
この年(1965年)の日本映画の興行収入ランキングで堂々第1位を記録している。
モノクロ作品にもかかわらず、髭を赤く染めてまで挑んだという
世界のミフネ演ずる赤ひげ先生を筆頭に、
藤原釜足、志村喬、左卜全、土屋嘉男、山崎努など
馴染みの黒澤組俳優たちがしっかり脇を固め、
そこへ若き医師役に若大将こと加山雄三を中心に
その両親には、ちょっとした顔出し程度とはいえ
田中絹代に笠智衆まで贅沢にあてがわれている。
大根で頭を殴られるほどの強欲非道な淫売屋女将に杉村春子、
小津や溝口作品では見ることにない体当たりの狂女に香川京子など、
黒澤作品には珍しく、色とりどりの女たちによる映画でもある。
豪華絢爛、これら俳優たちの熱演ぶりはいうまでもなく
それを支える脚本には二年の年月をかけ
セット美術や照明、それを活かす撮影技術の確かさなどが合わさって
撮影期間は一年と半年を費やした大作となっている。
おかげでその質感は、現代では再現の及ばないレベルに達している。
光と影が強調される画力からは
ドイツ表現主義的な気配が漂ってくる。
モノクロゆえ、その目力の強度に圧倒されるほどだ。
そんな重厚なまでのモノクロームの群像時代劇は
3時間の長丁場とはいえ、途中に「休憩」を入れるほどだが
決して長さを感じさせないほどに惹き込まれること必至である。
見事な構成力に脱帽だ。
激しいアクションだの、スリリングな展開だの、
あるいは哲学的、内省的で、ハッとするようなサスペンス調に傾くでもなく、
ここにはそういったエンタメ要素をダイレクトな感情表現で補いながら、
生きる人間の強さみたいなものに焦点があてられ
見るものを退屈させる要素がない。
黒澤映画の本質は、どこを切り取ったとて、所詮人間賛歌そのものにあるのだ。
それは時に執拗で、かつオーバーにのしかかるってくる。
が、人間とは何か? 生きることとは何か?を
真剣に追求するがあまり、熱き想いが強く滲んだ画になるのだ。
そこを逃げず離れず、直接的表現で
どんどん掘り進めてゆく監督であることはいうまでもない。
それが世界に認識されている巨匠黒澤たる所以だ。
出来としては『用心棒』『七人の侍』『生きる』など
いずれの映画史に名を刻む傑作にも引けを取らない名作と言える。
その『赤ひげ』に滲むある種のセンチメンタリズムでさえも
間違っても御涙頂戴ものではない。
この半世紀を経ても、その辺りは一向に安っぽくはなっていない。
当然のことだろう。
それは人間の普遍的テーマが掲げられ、
圧巻のヒューマンドラマとは、こういう映画のことを言うのだと言わんばかりである。
そんな赤ひげは、名医と言うよりは一人の人格者と言うべきか?
いや、そこはどう見ても聖人の域にあろう。
医学の知識は無論、人の心を読む力にも長けている。
それをやたらめったら見せびらかさない。
おごりもなく、うわついたところもない。
やることなすことが的確である。
こうして見れば見るほど非の打ちどころなき人格者風情が伝わってくる。
が、そのあたり、決して過剰にも誇張にも扱わず、
美化させないための気配りに余念がないのは
監督と主役だけが交わせる長年のコンビの息のなせる技なのかもしれない。
身内には不躾で、変わり者を貫くが、
権力者からはしっかりゼニをせしめ、
貧しき虐げられし人々に還元する赤ひげ。
邪悪なるものには果敢に立ち向かい、時に乱暴に天罰を下すことを厭わず。
それを医師としてはちとやりすぎだ、
俺にはこんな一面があるんだなどと自嘲し
斬って返す懐の広ささえ合わせもっているひと角の人物なのである。
悪を憎んで人を憎まずの精神が貫かれ、
何より、他者に対する思いの篤さに打たれるばかりである。
最後には、保本は婚姻が決まった晴れの場で
この診療所で、この人の元でずっと働きたいなどというセリフを吐くに至るが、
それゆえに、苦労もまた永続的なものだとと伴侶への覚悟を告げる姿に
当初のおごりも不満も迷いも微塵もない。
が、どうにも照れくさいと素直になれない人間赤ひげとの交流には
あたかも安直なヒューマニズムに陥らぬよう
上手く用意されたカムフラージュにすぎない。
照れ隠しの赤髭がなんとも愛おしいが、
観客に、不本意な横槍を挟めぬような確かな説得力がそこにはある。
ぶれなき人間の振る舞いをひとつひとつ丁寧に積み重ねた結果、
まさに、日本映画のみならず
ヒューマンドラマの最高峰に位置する映画の高みへと到達しているのだ。
のちに舞台化、ドラマ化が後を絶えないのも納得である。
そんな江戸の民意の理想を掲げたテーマが描き出された
新出去定と言う名物医師をめぐる3時間の物語は
山本周五郎の原作『赤ひげ診療譚』から、それぞれ
「狂女の話」「駆込み訴え」「むじな長屋」「徒労に賭ける」「鶯ばか」「氷の下の芽」と
原作の話を上手く持ち出し嵌め込みながらも、
「徒労に賭ける」で、淫売屋で梅毒を患っている少女おとよを救い出し
診療所で見せる「鶯ばか」に出てくる貧しい盗人の少年長次との交流では
ドストエフスキーの『虐げられた人びと』に負いながらの物語を
オリジナルとして膨らませている。
遺憾無く名子役ぶりを発揮する図師佳孝演じる貧しき男の子長坊が
小ネズミと呼ばれるまでに、まかないから粥を鍋から盗み出すのだが、
事情を知るおとよはそれを見て見ぬふりをして、内輪から非難されるシーン。
この数分にわたる見事なワンシーン・ワンショットの長い芝居が
黒澤が得意とした「マルチカム撮影法」によって生き生きと捉えられている。
現場でもその臨場感ゆえに涙を誘ったというから、
まさにハイライトと言っていいだろう。
その後一家心中の煽りで毒を呑んだ男の子の命乞いをするために
女たちが井戸に向かって男の子の名前を呼ぶシーンなどは
いかにも黒澤らしいヒューマニズムの典型だと言えるが、
こうして物語が好評を博した内容のおかげで、
ますます持ってこの赤ひげ伝説を盛り立て
物語が一人歩きするのはヒット作の常である。
こうした「赤ひげ先生」のモデルとされる小川笙船と言う町医者は
確かに実在するにはするが、
実のところ、笙船は小石川御薬園内に養生所が設立されたときの発案者に過ぎず
“暴れん坊将軍”で知られる時の八代将軍吉宗が
当時、流行っていた疫病と大飢饉危機に対する施策として目安箱を設置し、
この笙船からの意見書を汲み上げ、
性急に小石川養生所が設立されるに至ったという経緯があり
笙船の肩書きは、あくまで幕府の肝煎り、現代でいうその医院長の役目に過ぎず
のちにはその肝煎りも息子へと譲り、
養生所は小川氏の世襲により運営されたのだと言う。
つまり、映画におけるこの名物赤ひげ先生は、
文字通り、想像を膨らませたキャラクターにすぎないというのである。
そうした背景はさておくも
ここに、蘭学を学んだ一人の若い医師がやってくることではじまるが
そこに傲慢不遜、自分勝手な思いしかない。
最初は色々ブーブーと不平不満を垂れ反抗するところから
徐々に、人格者赤ひげの魅力の前にひれ伏すことになり
次第に己の愚かさに気づき
精神的成長を遂げてゆくという話である。
そんな若い医師をあの加山雄三が演じているが
黒澤映画においては、この若大将は『椿三十郎』同様に、
いつも三船演じるキャラの前に、常にその浅はかな心を諌められ、
何かと人生そのものを教え乞うといった主従関係が描きだされる。
医学を学問として体得した若い保本と
実態の伴った経験値として医学を繰る老練な赤ひげ。
オムニバス形式で、様々な複数のドラマが盛り込まれるが
まずは隔離された香川京子の狂女が脱走し
もう少しで殺されかけるところに、赤ひげの手が入って救われた保本は
次に女の手術の生々しい現実に失神したかと思えば
死に瀕した男の診察すら的を射ず対処できず、知識不足を実感する始末。
赤ひげの外来に金魚の糞よろしく後をついていっては、
その実直な超越的振る舞いの感化を徐々に受けてゆく。
岡場所から連れ帰ったおとよの世話を言いつかるもうまくはいかない。
だが、赤ひげなら、そんな手を焼く患者に対する振る舞いにおいても
保本にはない、寛容さと愛ある眼差しで
うまく処方してみせられてはぐうの音もでない
結局、何をやってもこの人には敵わないし
己の小ささに打ちのめされるばかりである。
そんなふたりの主従関係が、
いつしか、心を通わせ、信頼と尊敬によってより強固な絆となる。
この黒澤流のハッピーエンドで迎えるエンディングは実に晴れやかに見える。
が、ここで黒澤と三船の関係も、ついにその糸が切れるのである。
1948年、『酔いどれ天使』で黒澤映画デビューを果たして以来
この『赤ひげ』で16本目を数えるも
かえすがえすも皮肉なエンディングに思えてくる。
そう思えば、息子大の若き医師に
存分に褒め称えられての照れ隠しを見せた赤ひげの表情に
黒澤作品への精いっぱいの惜別の念を汲み取ったとて
あながち的外れでもなかろう。
Doctor Robert :The Beatles
ビートルズの『Revolver』に収録されている「Doctor Robert」は、赤ひげ先生のような人情家というわけでもないし、映画のような、貧しいものの救世主という医者でない。確かに、このロバート先生ときたら、病人をみるみるうちに元気できるそんなドリンクを出してくれるらしい。そんなちょっと危険な匂いが立ち込める人物である。この人物はロバート・フレイマンという実在した医師という説が有力で、公的な立場の裏側で、ドラッグを流していた危ない医師だったらしい。そんなドクターのことをわざわざ曲にするのだから、ポールもジョンも相当のタマである。もっとも、ポール自身は「ドラッグで身体を治してくれる空想上のドクター」ということにしているようだから、それ以上のことはつっこまないでおこう。他にも諸説があるが、ここでは割愛する。そう、日本でいえば、ロバート秋山の憑依芸みたいな感じで受け止めておくのがいいのかもしれないな。




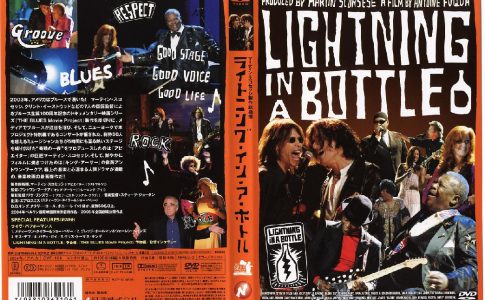
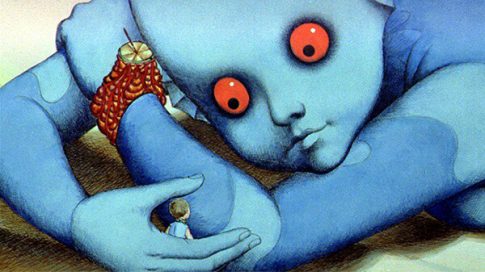
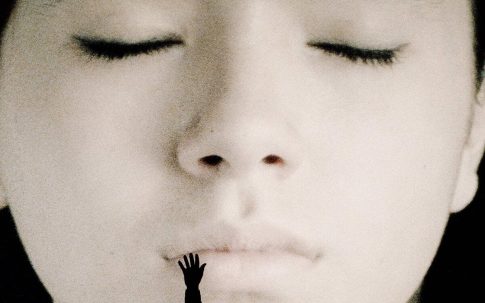




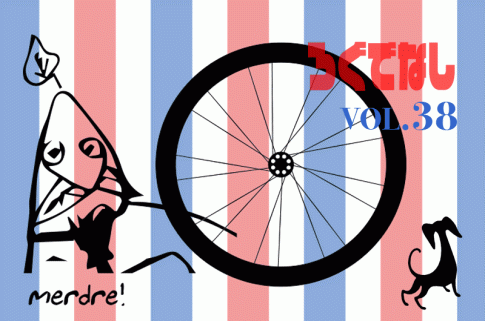

コメントを残す