愛しき反射界的シネマ狂人に乾杯
ふと、日本に真のコメディアンたるものが
存在するのか、ということを考えてみるのだが、
(むかしはそれなりにいた気がするが)すぐに浮かんでは来ない。
コロナ渦中に感染からあっという間に亡くなり、
多くの悲しみをさそった志村けんなんかはどうだったのか?
少なくとも、生前研究熱心で、チャップリンやキートンの世界にも精通し
それを芸にも取り込んでいたというが、仮に、映画や舞台だけで、
いくら真面目に芸に邁進していたとしても、真のコメディアンとして
日本の喜劇王として、その座に君臨できたとは思えない。
やはり、子供を中心に爆発的に心を掴んだ
時代のお茶の間スターとしての威光だけが、一人歩きしていた感が強いのだ。
むろん、それはそれで、彼の功績を否定するものではない。
そには、日本という国におけるお笑い感性の問題も多分に影響しているのだ。
そこで、ぼくはジャック・タチのことを考えてみた。
タチは、映画を通してコメディ要素を演じてみせる俳優かつ監督である。
おそらく、志村けんとはどこか重なるようでいて、
実は全く重ならない領域にいるのがタチじゃなかろうかと思う。
つまり、タチは生粋の映画人であり
日本的なお笑いとユーモア感覚とは似て非なるもの、
同じ土俵で語るべきではないように思われる。
ただ、志村けんもタチも、実のところ、まったく生活感というか
プライベート空間を想起させずひたすら笑いを追求したという意味では
どこか根底でつながっているという不思議な共同体意識を見出すことは可能だ。
つまりは、笑い、笑わせることで得る快感。
しかし、もはやこれは比較でもなんでもない。
いまや、「ぼくの叔父さん」ことユロ氏は
ぼくらのジャック・タチ、あるいはユロ氏として、世界中に多くのファンを獲得し
フランス映画の至宝として、その愛されキャラは映画史に燦然と君臨している。
ユロ氏は、ただ笑いだけを追求したわけではないし、
パントマイム出身のタチが映画で見せた芸は、
あくまで、ストイックに磨き上げられたユーモア精神の
芸術的昇華の形なのである。
そんなタチが亡くなった時、志村けんほどに、
その存在を惜しまれた、などという話は、
たとえフランスからでもきこえてこない。
それは一部のディレッタントの妄想なのだ。
タチはあまりに芸術的すぎたからだ。
おまけに、タチはけして幸福な映画作家として生涯を終えたわけではなかった。
とりわけ、自ら「遺言」だといい放った
長編4作目である『プレイタイム』でのその象徴たる事実を忘れてはいけない。
全財産を投げ打って、丸2年の撮影期間とフランス映画史上最大の制作費
約1540万ユーロをかけての集大成として、打って出た一世一代の超大作だったが、
トリュフォーやゴダール、そしてアンドレ・バザン
一部の熱狂的支持と評価こそあったわけだが、興行としては失敗。
タチはあえなく破産の憂き目に遭う。
没後の評価といえば、今や確固たる地位を築いてはいるものの、
肝心の主役はスクリーンのなかの幻影だ。
まさに、早すぎた才能は、当時の大衆からは
諸手をあげ称賛されていたわけではなかったのである。
タチがスクリーンから姿を消してから
おくればせながら、真の価値を発見したものたちによって守られてきたにすぎない。
その影響の大きさはいうにしれず、ロイ・アンダーソンをはじめとする、
現代の映画作家たちにもその意思は脈々と受け継がれているわけだが、
あの飄々とした、人を幸せにする映画とは別に、
哀しい事実として、そうした矛盾はどこかでひっかかってくる。
タチの名声を確かなものにしたのは、あの『ぼくの伯父さん』だ。
文明の利器をやんわり皮肉を込めて冷笑してみせながらも、
少年のように、ひとり、現実とは無関係に、
言葉など介さず、ひたすら優雅で愛すべきものごしで
すべての挙動に笑いをもりこんで、人々の心を鷲掴みにしたユロ氏。
そこから、約10年をへて映画作家としての真の名声は、
この『プレイタイム』によって確立されたといってもいいだろう。
通称タチヴィルとして、パリ郊外のヴァンセンヌに2500平方メートルもの大セットを組み、
パリの超高層ビル、道路、空港、オフィスなどモダンな建築物に夢を託した。
それらは、今日の建築以上にモダニズムを想起させるといった
一種、アンビバレントな空気に満ちた未来空間なのだ。
このスケールの大きさが『プレイタイム』の豪華さを彩っている最大の要素だが、
タチのこだわりは、それだけでは満足しない。
70mmの高画質、度重なる撮り直しと資金繰りによる頓挫に負けぬ情熱で
出演するありとあらゆる俳優たちに個別に演出をつけ、
目に入るものすべてに命を吹き込むという贅沢なわがままをも駆使してみせた。
そうして出来上がった虚構空間に魅せられる我々は、
映画の磁力が豊かな笑いをもたらすことを確認し、感性を刺激され続けるのだ。
ここでもタチは、例のいでたちで
(帽子にパイプ、コートに丈の短いズボン、そして傘のユロスタイルというやつだ)
お上りさんたるユロ氏を演じた。
といっても、セリフもほとんどない、ストーリーらしきものもない。
立ち並ぶ近代的な建築物のなかを、例のぼくの伯父さん風情で右往左往するユロ氏。
そこで、迷路さながらの鬼ごっこの果てに、アメリカ人観光客バーバラと知り合う。
そして人を介して、ユロ氏はあっちへいったり、こっちちいったり、
動機のない移動に躍起になっている。
だが、そこで真の主役が実はタチヴィルにあるのを発見するのには、
ここではさして時間はかからない。
空港、オフィス、そして優雅な住宅を満たすイコニカルな登場人物たち。
ときには、いたるところでユロ氏のにせものに出くわしたりする。
長い廊下を向かってくる係員を待つ無駄に長い時間。
ユロ氏が見下ろす幾何学的に配置されたオフィスには天井がなく、
招かれたアパートはその断面図をみせられるかのよう。
椅子に座れば背中には痕がついたり、
画面全体に密集する人々の、それぞれ好き勝手な動きに目移りするレストランシーン。
いたるところ、つねに小さなギャグやおかしみの仕掛けが施されている。
そして、反射するガラスが映し出すエッフェル塔や凱旋門。
メリーゴーランドのようなターミナル、車、バス。
隅々まで行き届いたタチの設計がなんともまぶしいのだ。
それにしても、タチの映画は
一つのシーン、ショットにおける情報量が満載である。
瞬間にすべてを把握することができない。
どこをどう見るかは、見るものの自由だ。
幸い、ストーリーに支配される映画ではないから、
それをすべて追うのが一苦労でも、それがまた楽しい遊びとなる。
視線の快楽と言ってもいい。
結局のところ、目の前で起きているコミカルで愛すべき現象を
僕らはそれを傍観者として見せられるだけだ。
そこに、なにかが残るわけではない。
その笑いにしても、腹を抱えて笑ったり、誰かと共有するようなものでもない。
ただ、クスリと笑い、自分だけ幸せになった気分で
タチワールドの住人として、ひとりごちる世界なのだ。
そういう世界の愛おしさを、映画として創造したタチの偉大さを
この『プレイタイム』は伝えてくる。
映画を見る幸福のあり方に、未来的な視座を持ち込んだ作家。
まさに、それは遊びの時間をともなって、優雅に、そして微笑ましく、
時空を超え、われわれを非日常に連れ出してくれるのだ。







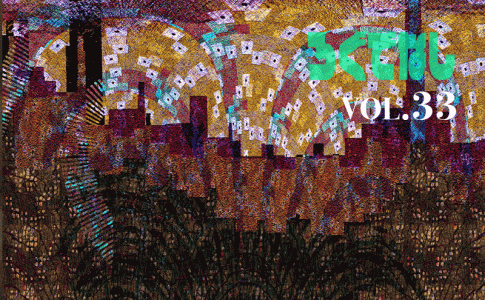





コメントを残す