天使の代償に蘇生は許されない
かつて、アメリカとその均衡を二分化していた
大国ソビエト連邦はいみじくも崩壊したが、
いまだロシアは広大な領土を持ちえている。
じつに不気味な国家である。
そのロシアの底力、とばかり、
レンフィルムを排出したこの国の映画産業はというと、
映画史に燦然と輝きを残している。
エイゼンシュタイン、ウドチェンコ、
ボリス・バルネット、メド・ヴェトキン。
タルコフスキーにソクーロフ、ゲルマンなどなど、
錚々たる天才作家たちによる映画が、
いまだどれほどの影響力を持ちうるかを
わざわざ声高に叫ぶ必要などない。
が、ロシアの映画産業が崩壊しはじめる90年代
そこに、極東のスーチャン(現パルチザンスク)から、
長い年月を経て、唐突に現れた中年作家
ヴィタリー・カネフスキーの名が刻まれて久しい。
結局は、かろうじて奇跡のような
三本の作品のみを残して、
再び映画史に封印されようとしている現実に、
まさに、呪われた作家というべく宿命を生きるしかなかった、
あのカネフスキーの傑作『動くな、死ね、甦れ』は、
永遠に語りつがれるべき使命を背負って
今なお観るものを魅了して行くだろう。
アレクレイ・ゲルマンによって見いだされるまで、
事実無名の作家であったが、
初の長編であるこの『動くな、死ね、甦れ』が世に出るまで、
おおよそ半世紀も要することになった。
無実の罪により投獄され、
むざむざ8年間の獄中生活を余儀なくされたというから、
その困難さをなげくより、
この圧倒的なまでに澄み切ったモノクロームの美しさを、
この先、いかなることがあっても
忘れえないであろう震えを前には、なす術を知らない。
雪と泥濘たけが、凍てつく寒さの合間を行き交う人々によって
練り上げられた炭鉱の町が、
あるいは、荒涼とした風景に、行く当てなどないかのように、
ひたすら漠然と伸びている線路によって
分断されるこの極東の町に、何故だか、懐かしい思いが
込み上げてくるのは気のせいなのか。
確かに、それは「五木の子守唄」であり、
「よさこい節」の旋律であり、
それらが耳に飛び込んで来るからといって、
傷を負った眼差しの重みに時空を超え共感できるはずもない。
胸をはだけて男に迫る10代の女囚は
妊娠すれば釈放されると切に思う。
が、そんな幻想は踏みにじられる。
スターリン圧政下の旧ソビエト
かつて日本の強制収容所があった町スーチャン。
スクリーン越しに、生きる強度の絶対を共有し、
認識の差異を埋めることに意味などなく、
ただ胸を圧迫する純粋なる苦しさに
眼差しがスクリーンに釘付けにされるばかりだ。
しかし、どうだろうか、
このあらわなまでの人々のざわめき、
その強度の前に打ちのめされんばかりの
映像の喚起力というものは。
小手先だけの貧し技巧など、このカネフスキーの映画には微塵もない。
物語を物語として追う事すら許されない。
まさに混沌たる当時のロシアの実情が、そこを生き抜くための叡智、
存在そのものものの困難さを伴って
絶えずピンと張り詰めた糸のように
危うき均衡の上に厳しく晒されている。
無論その先にあるのは死、
あるいは無に帰すことの緊張感である。
蒸気機関車を脱線させ、学校のトイレをイースト菌で氾濫させる、
あるいは悪党の一味に加わり、窮地に立たされてしまう少年は、
唯一守護天使ガリーヤの命がけの救助によってかろうじて難を逃れる。
子供であることの無防備さを
存在の大人びた眼差しだけが頼りだとばかり、
突き進んで見せる少年が、
その無謀さにおいて何を恐れるというのか、
人生など最初から狂っているのだと
言わんばかりに強がってみせるのだ。
にもかかわらず、失敗やあやまちは一切許されず、
生きて行かねばならないことや、
なんの安心も容赦もないことに、なんら変わりはない。
この大それた行為の主役、カネフスキーの分身たるワレルカこと、
パーヴェル・ナザーロフの眼差しを、ぼくは忘れることは出来ない。
自らの身に起こってることすら理解できず、
ただ本能による畏怖だけに律せられながら、
ひたすら『ひとりで生きる』ことしかできないこの不器用さ。
そんな少年の眼差しを、誰が受け止めてあげられようか。
無知と無垢にのみ愛された人生を見つめることの強さ、
それは守護天使ガリーヤだけの特権だ。
彼女だけが、この無知と無垢のはざまに生きる
少年を優しく見守る事が出来るのだ。
この特権の庇護にしか、少年の未来はない。
それは同時にカネフスキーの映画が
明日を生き伸びる為の術であるかのように呼応している。
だが、守護天使はひたすら過酷な運命に翻弄されるのだ。
無防備な人間を守るためには
命さえ惜しまない覚悟に身を委ねねばならないのだから。
歌声を土産に去る守護天使の苦悩をよそに、
ワレルカの無邪気な微笑み。
それにはやれやれと言ったため息しか漏れてはこない。
ひたすら生き延びねばならない。
ひたすら守らねばならない。
己の運命をも受け入れること、
それが守護天使に課された使命とばかり
大人の真似事が上手いだけの少年の運命を
一手に引き受けなければならない。
そんな思いで線路を歩いて帰還するラスト、
二人を待ち構えているのは、紛れもない死だ。
守護天使は、現実を甘んじて受け入れねばならず、
ワレルカにはそれが理解できない。
気が動転し、狂ってしまうのは残酷にもガリーヤの母親である。
この情景を目を伏せずに凝視すること、
それが無防備の代償だといわばかりの全裸の舞。
天使の死の代償に、蘇生など許されるはずもない。
これからは一人で生きてゆくのよ、ワレルカ。
はたして、守護天使の声が聞こえただろうか?
無条件に、無防備ながらに生きてゆかねばならないという、
この野生の情景に胸締め付けらると同時に、
生きる力を授けられるような、そんな思いがするのだ。
民謡クルセイダーズ:炭坑節
「炭坑節」といえば、福岡県筑豊地方の民謡で、かつて炭鉱の町として栄えた筑豊を中心に歌われてきた労働歌。「月が出た出た~」という冒頭のフレーズが有名で、炭鉱での労働や町の様子をユーモラスかつ哀愁をこめた、そんな伝統的な日本民謡を、ラテン音楽やカリブ音楽といった多国籍なリズムと融合させたのが、民謡クルセイダーズである。カネフスキーの映画にみる残酷さとは相反する、クンビアやマンボのような中南米的なスウィングがこの牧歌的に彩られたアレンジに、中毒性が漂う。










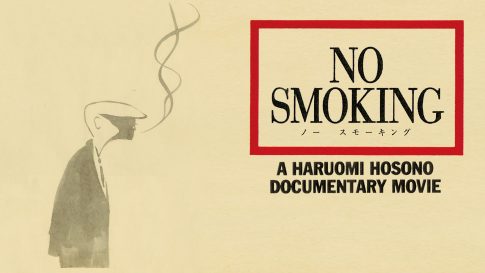


コメントを残す