不思議の国のヰタン・セクスアリス
曽根中生によるロマンポルノ
『わたしのSEX白書 絶頂度』について語る前に、
その充実した自伝書籍『曽根中生自伝 人は名のみの罪の深さよ』を手に、
読んでみるとこれがなかなか面白い。
曽根作品の解説が本人の口から聴けるのだ。
それはまさに、鈴木清順下で助監督を務めた日活時代から
日活ロマンポルノへの変遷の流れにおける
当時の現場の空気感を宿した、
貴重な証言として響いてくるリアルな言葉がある。
2011年の湯布院映画祭に、二十年ぶりに顔を見せるまでは
映画産業からはへだって、その姿をくらましていたわけだが、
一転、ヒラメの養殖業を経て、磁粉体製造装置なるものを開発し
特許を取るほどののめり込みようで、
なんとも変わった経歴を持つこの鬼才、
そんな曽根監督自身を改めて引っ張り出してまで
あれやこれや、過去の考察をも並行してやるには十分魅力的作家であり、
ちょうどその入り口に立ってみたところである。
とにかく、曾根作品は実にユニークで、
なかなか幅広いレンジを博しているのは、フィルモグラフィに顕著だが、
その何本かは確実に傑作であり
その何本かに対し、語りたい衝動が抑えきれないほど、
マニアを熱くさせるのだ。
あえて、ロマンポルノを強調するつもりはないが、
実に、不思議で貴重な映画作家であることは間違いない。
引退が実に惜しい人材である。
その曾根中生の数ある作品の中、傑作とされるのが
この『わたしのSEX白書 絶頂度』であり、
一言でいえば、ミステリアス満載、見所多い問題作である。
なんど繰り返し見ても、やはり斬新だ。
曾根中生がアヴァンギャルドな作家と言われる所以が
そこかしこに滲んでいる。
電車内の痴漢シーンのモノクロ写真による
スチールショットで構成されたタイトルバックからして、
すでにロマンポルノの範疇をこえているのだが、
そこへコスモファクトリーのファンクチューンが重なる。
ノックダウンされそうになるほどかっこいいオープニングに、
これが日活ロマンポルノの可能性だったのかと、呟いてしまう。
こうした音楽へのこだわりもまた、
曾根中生がロマンポルノ界で異端たる理由の一つに
数えられるのだろう。
また、本作で脚本を書いたのが
白鳥あかねという女性スクリプターで
女性ならではの視点が投影されているという点が、
他のロマンポルノ作品とも一味違う由縁だろう。
『曽根中生自伝 人は名のみの罪の深さよ』の中で、
曾根自身もなんどもそのことに触れている。
「男にはない感覚だから大切にしなきゃ」ということらしい。
要するに、ポルノだからって、間違ってもマッチョ的、
根強い男根主義からは隔たったものであることを強調しておきたい。
そもそも男性的視点だけの王道ものほど
つまらないポルノはないのだから。
そもそも、裸や男女の絡みだけで七十分、持つはずもない。
そのあたり、猥褻のひと声で断じうるようなものからは程遠いものなのだが、
なぜだか当時は何かとワイセツの言葉との闘いが
盛んに繰り広げられていた時代である。
正直なところ、ストーリーを追いかけてみても無駄なのだ。
ストーリーに通底したポルノほどつまらないことをよく知っている監督である。
かといって、ポルノグラフィックな快楽にふけるにも無理がある。
その間隙を縫って、熱演する主演の三井マリアという女優には
なぜかそそられるものがある。
けして華がある女優というわけでもない。
ましてや肉体美を誇るでもない。
むしろポルノ女優然としていない、
おどおどしたみずみずしさがある。
監督自身が元々芝居しすぎる役者を嫌う傾向があり
その点で好都合だったのかもしれない。
また、同時に出演の芹明香との対比が
実に面白い効果を生んでいる。
この一作のみで引退したというこの女優のことは
情報としては、なにもしらない。
それゆえに、かえってミステリーなところが都合がいい。
この二人が、ラストで絡むと言うシーンは
ロマンポルノとしての事情からは十分ありうる設定だが、
そこに益富信孝という、曽根作品に欠かせぬ、
これまたポルノ界の強者男優が絡んで、
いっそう猥雑さが増す。
この人相をみよ、と言わんばかしの強面の、
一度見たら忘れられないインパクトがある男優だ。
それにしても、採血係という設定の微妙なシュールさに
拍車をかけるような映像マジックのオンパレード。
さすがに具流八郎のメンバーであり
鈴木清順の現場に長年揉まれてきただけのことはある。
病院のシーンでの二重露光などは最たるもので
よほど実験的な作品でなければ
滅多におめにかかれないシーンだといえる。
そもそも、なぜこのシーンに二重露光が必要なのか?
監督自身の言葉を借りれば「若者たちの妄想」であり、
だから看護婦の「着物の中が透けていなければおかしい」
という発想が堂々まかり通る。
この辺り、男の願望の露骨な視覚化には
そこに二重写しという技法が、
大胆かつ的確に採用されたということなのだろう。
そうした視覚上の面白さに加え、
姉と弟との近親相姦もあれば、妙に生々しいカットがある。
自慰行為に耽る姉の股間を、弟が懐中ライトで照らしたり
情交の後に陰部そのものをタオルで拭ったり、
また、パウダーをはたいたりするシーンもある。
こうした描写は、ロマンポルノだとはいえ
なかなかお目にかかれないようなドキッとするショットがある。
これこそが、女の視点というものなのかはわからないが、
確かに、異質なショットが随所に挿入されている気がして興味深い。
エロティシズムという概念を、男の視点からではなく
むしろ、女の目線の延長上に敷くポルノ、と言い換えられるのか。
そこに、これまでのポルノ路線にない
大胆な映像美を重ねて描き出している点で、
日活ロマンポルノ出色の傑作が
『わたしのSEX白書 絶頂度』だったのだと思う。
そんな曽根中生の自伝『人は名のみの罪の深さよ』のエピローグでは
「映画は職業でした」と語っている。
つまり、職業として選んだ仕事に、見切りをつけたと言うのである。
なんとも、潔い決断であるが、それなりに、夢と希望を追いかけた
映画という世界に、未練がなかったわけでもなかろう。
監督自身、自分の作品であれ、他人の作品であれ、
非常に、物事をクールに捉えている印象がある。
最後に、「今、撮ってみたい映画は?」という質問には、
「魂の映画」とこたえている。
陸前高田の松の魂と行方不明になった東北の人の魂とが、ともに深海の中に沈んでいく中で、魂同士が語り合ってゆく話が撮りたいと思っています。
『人は名のみの罪の深さよ』
少し抽象的、観念的ではあるけれども、
スピリチュアルやら、精神性をもった映画という意味ではないにせよ、
一歩踏み込んだ、人間の本質に迫るもの、そんな風に解釈すれば
自ずと曽根映画の輪郭は浮き上がる。
いわゆる曽根節たる、外連味たっぷりの突拍子のなさで描いた怪作?を
ぜひみてみたいと思っていたのだが、
その夢叶わず、すでに鬼籍に入った曽根さんは
76でその生涯を閉じてしまった。
その残された作品をみても、
実に個性的で稀有な作家だったと思う今日この頃である。
ブラックホール:コスモファクトリー
名古屋で結成され他コスモファクトリーは
1973年に立川直樹プロデュース
「トランシルバニアの古城」でレコードデビューを飾る。
四人囃子なんかと並ぶ、知る人ぞ知る
日本の二大プレグレバンドという立ち位置ではあるが、
さて、どのぐらいの人が知っているのだろうか?
僕がこのバンドを知ったのは、まさにこの曽根中生の『わたしのSEX白書 絶頂度』からである。
劇中には、彼らの貴重なライブ演奏もしっかり記録されているから、
その意味でも、この映画は貴重な作品だ。
この映画のシナリオを読んだ立川直樹からの売り込みがあったのだという。
それを受け止めた曽根中生に、確かな音楽的アンテナがあったことの証明でもある。
サントラなど存在するわけもないが、
ちょうど、映画公開時の3rdアルバム「Black Hole」は、
確かにクリムゾンの亜流ではないにせよ、影響は感じられるが
今聞いても実にかっこいい。
メロトロンやムーグ、オルガンといったキーボードがフィーチャーされたサウンドだが、
ギターのカッティングやリズムのグルーブ感も素晴らしい。
日活ロマンポルノとジャパニーズプログレの邂逅。
なんともロマンチックで刺激的だ。





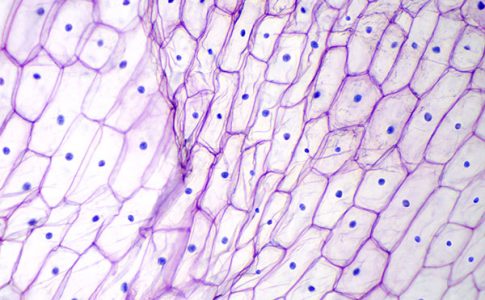







コメントを残す