不治のやばい若尾文子の魅力
増村保造の『妻は告白する』での若尾文子が、
ラストシーンで若い恋人川口浩の会社にまで出向いて、
そこであろうことか自殺を図る、などという行為を、
たとえ映画の中とはいえ目撃したとき、
人は、そうまでして恋人を苦しめるのか? という声もあげれば、
そこまで深く愛しているということなのか?
いや、それほどまでに愛情を誇示したいのか?
などと嘆息ぎみにつぶやくかもしれない。
そこまでして、という感情がとりとめもなく襲って来て、
いやあ、これは凄い映画だったなあ、という結論だかとりあえずの納得だかで、
いったん事態は収斂する。
だが、そのあとも微熱のように、治まること無く悶々と続いている、
そうまでに若尾文子なのか? という問いに、
いまだ上手く答えられない。
ココロのほうはというと、確実にはまってしまっているのである。
あのムード、声やしぐさや、
なんていうのかなあ、やっぱり女としての官能性かなあ、
などと脳天気に答えることも、もちろん可能である。
それはそれであながち間違っているわけではないが、
いや、そんなことはまあみりゃわかることでさ、
ちょっと言葉にするのが野暮なのさ。
むしろそういうイメージの上に築きあげられた、
もっと内面のマグマのような激情部、
実のところあの非常なまでの強さ、といったらいいのか、
激しさといえばいいのか、つまりはだね、
簡単に手に負えない女としての磁力がそこには強くあってね、
映画という枠のなかで、リアルにこちら側に、
その、なんてえのかな、ぐっとせまるモノをつきつけてくるのだな。
うむうむ、まさに強烈なる刃物のような媚態ってことになるんだろうか。
ことわって置きますがね、それって、男と女の場合、
ちょっと違うかもしれないがね、
女だってそれは違うんんじゃ無いって思うかもしれないしさ、
並の男じゃ受け止められないよ。
こう怖いくらい真に迫ってくるような、滲みだすような、
なんともすさまじい感じがあってね、
でもね、そこがいいいんだよな、
などというしどろもどろな答えになってしまうに違いあるまい。
もっとも、それは概ね溝口健二以降、
その助監督を勤めた増村保造との出会いにおいて開花した、
日本映画史的な出来事だ、ということははっきりいっておきたい。
そもそもが、大映のニューフェースにかかげられたアドバルーンは、
高嶺の花ならぬ低嶺の花。
この大衆的アイドル若尾文子が、どのように時代とともに変遷を遂げて、
押しもおされぬ大女優の地位にまでかけのぼったのか、
四方田犬彦・斉藤綾子による
おのおの「映画女優若尾文子」論にみごとに展開されている。
ここでは、そうした大女優ぶりを語ろうというのではないし、
その書物をめぐる考察をしようというのではない。
それは、ただひとつ、こうなのだ。
増村保造映画における若尾文子の衝撃、その強度を観よと。
ことあるごとに特集が組まれる、この若尾文子っていったい何もの?
スクリーンを離れてからそのような問いが幾度となく聞こえてきては、
映画館の闇での逢瀬を重ねたものだ。
むりもない、いいようもない何かが我々をとらえてしまう、
あの不思議なオーラに出会った瞬間から、
我々のなかのなにかを決定的に変えてしまうほどの、
蠱惑的な映画体験がはじまってしまうのだから。
山根貞男氏は作家論『増村保造 意志としてのエロス』の中で
「何があの若尾文子を動かしているか」という命題をなげかけているほどだ。
情念を内に秘めたこの蠍座の女は、
とりたててプローポーションを誇った美女というわけでもなかったし、
自ら裸体をさらすほど明け透けで大胆なこともなかった。
(時に、その肢体のモデルの出来不出来によって、
妙な懐疑までかけられていたというから、
まったく映画というのは罪つくりなものである)
時に清純で明朗なふりをしてみせはするが、
だがいつのまにか官能のなんたるかを知り尽くしているかのような、
目線、うなだれ、微笑み、ちょっとしたしぐさ、挑発、そして微妙な声色、
それら調子をあたかも無意識下で繰るかのように
男を翻弄する術を身につけて、スクリーンを変遷していった。
そんな彼女が出会うべくして出会ったのが
イタリア帰りの増村保造という名の才能だった。
思えば、初々しさなら溝口の『祇園囃子』を、
ちょっとスタイリッシュで粋なところなら
小津の『浮草』を、色香漂うしとやかな姿というなら
吉村の『越前竹人形』を、
ただ単純にあくの強いものをというなら、川島雄三の『しとやかな獣』
なんかを思い出してみるけれど、それじゃあどこか物足りない。
やはり、なんといっても二十作品をも数える
増村作品での彼女の強度を持った眼差しの数々が、
とりもなおさず観たいのだ。
それら増村作品における若尾文子演じる代表的な「女」たち、
なかでも『妻を告白する』『女の小箱より「夫が見た」』『清作の妻』『刺青』『赤い天使』における、
彼女の生きざまには、ちょっと凄いまでの感動がある。
いやほんとうに、物凄く、凄い。
そこに現れた女というある種の幻想は、
男という生物にとっては、かくもやっかいな存在ばかりだ。
ただやみくもにいやな女でもなければ、
世にいうところの、ただのぐずぐず女たちではない。
すなわち、己の業=生命線であるかのごとく突き進むがゆえの、
人生翻弄型と成り果てることの凄み。
狂気と紙一重だと知りつつも、やっかいかもしれず、
こんな女は勘弁願いたいのはうすうす分かっている。
にもかかわらず、なぜかこんな女こそを求めてしまう野郎どもが、
実は逆に悲しき男としてのぐずぐず加減をさらしながら、
まったくダメな男ね、と翻弄されてしまう究極のマゾヒズム。
その意味で、増村映画のなかの女たちは、
どんな不幸な境遇であっても、男たちのまえに屈することはない。
そんな女たちを若尾はいきいきと演じてみせる。
だからこそ、この場合の“媚態”とは、単に男に媚び、
女としての生命体を保持するための策略とは明らかに違う。
そうなると、山根貞男氏のいう
“意志としてのエロス”という言葉がしっくりとくる。
こうして、男たちは女という生き物の魅力=怖さの術中にはまる、
いわばアンビバレントな揺れを体験せざるをえないのだ。
それは、カマキリの例を持ち出すこともなく、
本能でありながら自己破壊へのステップというべきものかもしれない。
こうした男女の凌ぎあうさまを、
ことごとく傑作に仕立て上げた増村VS若尾のフィルムにおける睦ごとに、
まずはブラボーといわせていただきたい。
男と女、本能の対決。生きるべきか、死ぬべきか?
いやあ恐るべし文子様。
これぞ男と女の越えられぬ綾ではないか!
かわいそうだとか、同情されるとか、そうなるとつまらないわけですよ。だからどちらにもかかるくらいにやっておかないと。怖くて利己主義でイヤな女だな、という面も半分思わせておいて、だけども、こういう立場にたったら、こういう行動をとらざるをえないだろうな、と思わせるという。その両方にかかるくらいに‥‥‥そのへんですね。
(「映画監督増村保造」ワイズ出版より)



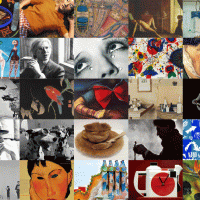









コメントを残す