愛すべき片栗粉にまみれた言葉たち
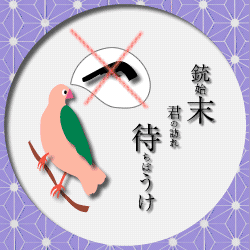
これは世にいうところの俳句や川柳などではない。まず温度が違う。言葉が徘徊するので必然的にヒートするのだ。一見形式を拝借してはいるが、あくまでも言葉が踊る(パロールンロールする)ための最適なリズムが引用かつ咀嚼されているにすぎない。それはちょうどヤドカリが巻貝に間借りしやすいように、わざわざ貝殻に即した身体つきをしているというのとなんら変わりあるまい。要するに、形はどうあれメタモード脳髄のハイハイテック&ボキャラッタな言語捕獲システムによって自発的にキャッチされるところの愛すべき片栗粉にまみれた言葉たち、それらが夢みる流動水に溶かれタコヤキの鉄板のような何か問う凹な容器に流し込まれでもし出来上がった、言うなれば回転質の湯気蒸す奇マグレードな百句というわけだ。ただし、冷めやすいのでいったん転がりだせば風邪をひいてしまいかねない危うさを常時兼ね備えているはずだ。よって、これはハイ句と呼ばれる精神の軽食、さしずめちょっとした茶菓子程度のもの、程よい頃に程よくつまめ、というモノでしかないだろう。



■志陣野歩蓮/shijinno pollen
肩書き・ヒップハイカー
銃始末 君の訪れ 待ちぼうけ
元来の俳諧Aに対し、ハイク、すなわちことばが紙面を徘徊するところの「徘徊集」となって現れた表現が、その続編として、ことばのオブジェ化と俗化にともない「俗・俳諧集」へと進化し、さらに加速するゾクゾク感と横溢する言葉たちの氾濫によって「ゾクゾク徘徊集」へとさらに発展し、三部作の完結となった。こうして、俳諧を徘徊した俳諧が、さらに徘徊するために何らかの形に属することで、続編を展開してゆくことばの実験なのである。
A→A’→AA→AA’とあたかも出世魚のごとく表層を戯れたのち、俳諧でも川柳でもないという明確な一線に至り、ことばそのものが、徘徊するかしないか、つまるところ、ただそれだけだということに落ち着いたのである。
●徘徊集から俗徘徊集、ゾクゾク俳諧集へいたるコンセプト
かつて、なんでもない便器を「泉」などと銘打って美術界に席巻した、コンセプチュアルアートの父、彼の名はマルセル・デュシャン。ダヴィンチのモナリザにひげを描き加えて「LHOOQ」と名づけた生っ粋のダダッ子は、そこで再びヒゲをとって「RASEE LHOOQ」などというダダの遊びを興じた。つまりはひげをそったモナリザによって、オリジナリティに対するまったく新しい視点を持ち込んだコンセプチュアルアートを具体化したのだ。
こうしたコンセプトをことばの領域で行うことは可能か? そこで俳諧が徘徊となり、俗を纏った俳諧が、俗をぬぐわずに、さらにゾクゾクするような徘徊を続けてゆくハイクは、文字どおり俳句というジャンルを軽く卑下する。いやはや、ひげをつけくわえたり、とりのぞいたりする遊び、に類似してはいないか?
誹諧10選
- ペテン師も ペー字めくれば 天使なり
- 熱帯夜 天使の魚の 涼し槽
- キッチンの 天使レンジな チン解凍
- うらぶれし 幽霊屋敷か 裏飯屋
- 雨上がり レイン坊やの 七不思議
- 望月や ラビッ人たちの キネの音
- モシャモシャと ひとり紙食う 複写っ鬼
- 微震でも マグニ中毒 近く花瓶
- 電波の技 行動伸びたる コードレス化
- 差異コロジー バクチ打ちたる ココロうち

