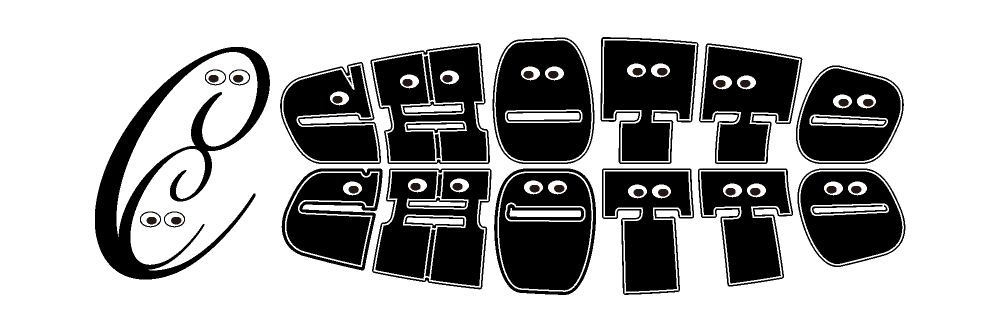ちょいといびつな空想科学寓話集

人はなぜこんなにも物語を必要とし、作家たちはありもしない世界を、わざわざコトバを駆使して、それを活字化し、書籍として流通させてまで、見知らぬ他者に、物語を伝えようとするのだろうか?
このような問いから始めれば、人によっては哲学的な命題にまで進展するだろう。それは、個々作家、それを受け入れる読み手側のありようにまで及んでしまうことになるのかもしれない。
しかし、率直に言ってしまえば、ただ語りたいのだ。聞いて欲しいのだ。ただそれだけである。それをどう受け止めるかどうかなんてことは、本当のところは知ったこっちゃないのだ。
たとえば、ここで、カフカであれ、安部公房であれ、星新一であれ、現実を言語によって解体した想像の世界の担い手たちを引っ張り出すまでもない。それがたまたま自分自身のフィルターを通して目の前に現れたというだけだ。同時にそれを受け手として、誰かに読まれうることが一つの前提になっているはずである。独り言でもない限り、そこに物語を公表すれば、望む望まざると関係なしに、伝播してゆく可能性は否定できない。まさに、読む対象としての現実が立ち現れる。その現実世界に関して、確かにこれはあまりにひどいという場合を除いて、何かを喚起する要因となりうることとも共存している。だから、事実は小説より奇なり、などとわざわざかこつけなくとも、現実が面白くないからといって、個々の物語がつまらないというわけでもないし、反対に現実が面白すぎるからといって物語が面白くなるわけでもないのだ。あえていうなら、現実を見つめる眼差しが、少しばかりいびつな方がより人の興味を掻き立てるような話を思いつきやすくなる、そのぐらいはいっていいのかもしれない。
そこに、作家は、彼自身のコトバでもって、世界を書き換える必然性があるのではないか、などと思う。それが作家の特権である。まさに自分自身の立場そのものであり、また他者と共有しうる部分なのかもしれないとも思うのだ。もちろん、その理由がひとつであるはずがないし、簡単にことばで語り尽くせるものだとも思わない。
目の前に現れたるその世界のいち目撃者である読み手は、手にした本の、あるいはその物語の端にふれ、つまりは作家の意識のとある側面にふれることで、自分自身の現実との関わり方を交えて、何がしかの意識の交感が始まってしまうのだとしたら、その意義は決して小さいものではない。そこに、可能性というものの始まりがある。その世界はというと、世界を揺るがすような大作もあれば、吹けばとぶような取るに足りない凡庸な言葉の羅列といったものある、というのが物語の持ちうる宿命だ。
ここで晒されるような寓話は、あくまでも、小さな世界だと思う。吹けば飛ぶような話である。個々人間の社会全体からすれば、ミクロな世界に過ぎない。とはいうものの、この小さな世界で語られるお噺たちは、いま、自分が立ち尽くす現実世界から、どうにかこうにか変換したコトバたちであり、 それが、あまりにも空想的(非現実的)であるからといって、現実からの逃避を意味するわけではない。空想的であればあるほど、それは、現実というものが露わにされてしまうことは周知の事実である。そもそもフィクションとは、それぞれ読み手の創造空間において、勝手に変異しうるウイルスのようなものではなかろうか。むしろ、この世界の発露は、現実に対し、研ぎすまされた感性を促すことになるかもしれないが、単なる戯言のようなものと解釈されても、なんら不都合はないのである。
とくにアンダーグラウンドを彷徨しうるような内容でもないし、現実からすれば、題材は実に甘く、でこぼこで、滑稽じみているかもしれないが、かようにあっちこっちで傷を負いながらも、気丈に笑いつづける道化師のように、ときに大胆に、ときにもの哀しく、ときにまぶしく、ときに鈍く読み手にフィードバックするであろう内容として読み解かれるのは全くもって幸福なことである。
◆衝動異物
●クツカリ編
それにしても山積みになった靴に唐突に間借りするなんて、いったい 何をどう勘違いしたのか。それゆえ、思わず《衝動異物》と呼んでし まいたい衝動にかられる小動物。そんなことをしでかすヤツとはいっ たい何者ぞや?
●シャポカリ編
かつてある日突然靴に間借りしたクツカリこと、衝動異物が消息を たってその後の動向が聞こえてこない。あれは一部の人間たちのうち で起こった単なる一過性の現象だったのか。人の目をかいくぐろうと も、確かにこの世のどこかに、棲息していることはまちがいない。そうした中、とある、アパートに、衝動異物が発見された……