ポランスキーの非尋常的臨場感は映画の神をも狂わせかねない妄想の宝庫である
ロマン・ポランスキーの『反撥』は
オープニングから、不安に怯えるドヌーブの大きく見開いた目が
恐怖を誘導してくる。
まるでヒッチコックのサスペンスのように、どこまでも扇動的だ。
だが、ホラーでもスリラーでもなく、
むしろ“恐怖という現象の内部に入り込んだ映画”というべきであり、
外界が主人公を脅かす、そんなあからさまな悪は一切出てこない。
彼女自身の内側で勝手に膨張し、伸び、ひび割れ、世界を侵食していく何者か、
その異様な力学によって、古いアパートの一室が、
人間の精神の奥深くに開いた
“暗い裂け目”のような空間へと変貌する異質な事態が描かれる。
まず、この映画を真に理解するためには、
キャロルという一人の女性が映し出す心理崩壊だけでなく、
その背後に無言で流れ続けている、
作家本人の“生の影”に目を向けなければならない。
ポランスキーは幼少期、ナチ占領下のポーランドで暮らし、
家族を失い、隠れ、逃げた記憶を抱え
世界がいつ自分に牙を剥くか分からない不穏な空気の中で成長した。
彼の人生そのものが“世界は侵入者の連続である”という大いなる傘の下にある。
母親はそのアウシュビッツでドイツ人に虐殺され、
また、妊娠中の妻のシャロン・テートが
カルト教団によって惨殺されたという痛ましい実体験を持つ。
同時に、自分が13歳の子役モデルに性的行為を強要した嫌疑をかけられ
裁判で実刑を食らっている。
それゆえ長い間、アメリカ本土の土は踏めない状況に追いやられ
未だ、性的倒錯者のレッテルを根強く持たれているのだ。
この世界観は、『反撥』の内外の空気そのものといっていい。
アパートの扉、壁のひび割れ、見知らぬ男の視線。
すべてがキャロルの私的空間へ侵入しようとする“外界の圧力”として機能する。
世界は彼女を優しく包むでも、無関心に放置するでもなく、
つねに彼女の心の皮膚の表面をなで回し、傷をつけ、侵食する。
そこに、言いしれぬ不気味さがにじみ出す。
特に、壁から伸びる無数の男の手は、
ポランスキー自身の“迫害の記憶”を象徴するかのようなシーンである。
歴史はとっくに過ぎ去っても、その影だけが内面に残り続け、
外界はつねに侵入しようとするのだ、と。
『反撥』は何と言ってもドヌーブの神経症を病んだ
あの究極の演技なくしては成立しない。
キャロルを演じたカトリーヌ・ドヌーヴは、
無垢と冷たさ、現実性と幻想性を奇跡的に併せ持つ女優だ。
とりわけ、この頃のドヌーブはどこか非人間的な表情を
演技を超えてのぞかせる。
彼女の美しさは祝福ではなく、
むしろ彼女を世界から隔離する“透明な殻”のように作用する。
彼女は男たちから好奇の目で見られ、触れられ、求められる。
だが彼女は一切それを受け入れない。
むしろ、彼女の美しさそのものが“侵入の契機”として働き、
彼女をより深い孤独へ追いやってしまうのだ。
ドヌーヴはこの矛盾を、苦しげに沈黙するだけで完璧に表現した。
ポランスキーが求めたのは、
恐怖を叫んだり、泣き崩れたりする女ではなく、
恐怖を“内部で凍らせる女”である。
その静けさが、映画の不気味さを異様なほど増幅している。
『反撥』は「被害者が狂気に陥る物語」として語られがちだが、
本質はそこにはない。
重要なのは、被害者であることがそのまま妄想を生み、
妄想が倒錯へ転じ、倒錯が世界の形をねじ曲げるという、
“心理内部で発生するスリラーの構造”である。
男性への嫌悪、触れられることへの恐怖、
性的トラウマの影が随所に暗示されていることからも
キャロルはたしかに被害者ではあるが
その恐怖は次第に彼女自身の内部で増殖し、
世界の見え方までを変形させていく。
凹む壁、空間の歪み、長く引き伸ばされる廊下の影。
世界そのものが、彼女の妄想の延長として描かれることに息をのむ。
こうしてみていると、ポランスキーのスリラーものには
明確な“敵”が存在しないことが圧倒的に多い。
外界そのものが曖昧な敵意を獲得し、
主人公の精神をむしばんでいくという筋立てが十八番なのだ。
その倒錯は、倫理や現実の境界を裏返しにする。
まるで世界がひっそりと“反転”する瞬間を見せつけられるようだ。
映画の最後に登場する古い家族写真を忘れるわけにはいかない。
家族が並んで写る中で、
幼いキャロルだけが顔をそむけている。
あのショットは、ポランスキーには珍しいほど説明的な“解答”である。
彼女の狂気は突然生まれたのではなく、
ずっと前から裂け目として彼女の中にあったものだという伏線であろうか。
家族への不信、男性への拒絶、孤立、沈黙。
それらはすでに写真の中ですでに息づいている。
ポランスキーは、キャロルの崩壊を描いたのではなく、
崩壊の源泉へ回帰させたに違いなく
被害妄想は突発的な症状ではないのだと、
幼い頃から育っていた“影”が、
アパートという密室で放たれたに過ぎない。
ポランスキーの人生は、迫害の記憶だけでなく、
のちに性的事件をめぐる大きな“影”を背負うことにもなる。
ここでは彼個人の倫理を論じるつもりはないが、
“倒錯した監督”というイメージが、
彼の作品に特別な層を与えていることは否定できない。
観客はどうしても、作家の影を作品に重ねてしまうものであり
この“誤読可能性”が、ポランスキー映画の緊張感をさらに高めている。
つまり、作品外の“影”が、作品内部の“影”を濃くするのだ。
ドヌーヴの透明感の奥に沈んでいく狂気を見るとき、
観客の意識のどこかに
「これは監督の闇とどこか通じているのでは?」そんな不安がよぎる。
この“外側の影”が、映画にさらなる深度を与えている。
『反撥』は、世界が侵入してくる恐怖を描いた映画ではない。
世界を侵入者として知覚してしまう心の“倒錯”を描いた映画だ。
チコ・ハミルトンの情動的音楽もさることながら
これほどまでに音が細部にわたって恐怖を演出する映画も珍しいが、
ギルバート・テイラーによるカメラワークで構成する
強烈な一体感のあるモノクロームの世界は
実に見事なまでにサスペンス調を演出している。
キャロルは被害者であり、被害妄想者であり、
倒錯した欲望と嫌悪の狭間に立たされた存在だ。
外界はつねに彼女を脅かし、内側では恐怖が増殖し、
やがて世界そのものが歪んで見える。
その瞬間、スリラーはスリラーを超えて、
“精神の裂け目を覗き込む詩”へと変換される。
ポランスキーの影とドヌーヴの幻想に
迫害の記憶、性の嫌悪、孤独、沈黙などが静かに混ざり合い、
アパートは彼女の心を映す“鏡の迷宮”になる。
そして観客は気づくだろう。
結局のところ、キャロルの中にあるヒビは、大げさな幻想ではなく、
誰の心にもひっそりと存在するものだと。
世界は侵入者の連続である。
その世界に触れたとき、
人は誰もが、ほんの小さな“反撥”を胸に宿すのかもしれない。
Repulsion · Dinosaur Jr.
殺伐としたグランジ風オルタナロックの喧騒の中に、一際けだるいJ・マスシスのボーカルが乗っかるダイナソーJRの記念すべきファーストアルバムから『Repulsion』。果たして、この曲がポランスキーの映画に影響されたかどうかまではわからないが、限りなくグレーなカオス感と衝動的疾走感が繰り出されるサウンドである。とはいえ、やっぱりドヌーブの壊れた精神性にはかなわない。いくら、音量を振り絞ったところで近づけない狂気というものがある。こちらは狂気と言うよりは、むしろ果てしなく、怠い虚無感の方が強くのしかかってくる青春系のオルタナサウンドの香りが残っている。




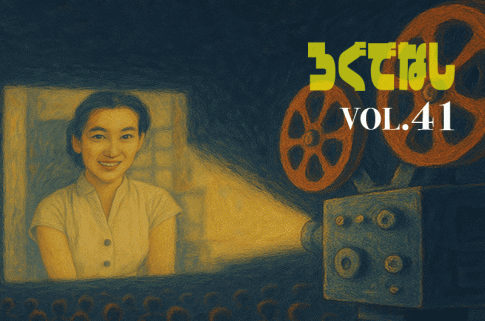








コメントを残す