感情を重ね着してきた立体女優、クールビューティとはいわせない
一時期“ツンデレ”という言葉がもてはやされたが、
ぼくにとっての元祖ツンデレ女優はモニカ・ヴィッティ、その人である。
彼女を思い浮かべるとき、多くの観客はまず、
沈黙の中に立ち尽くす姿を想起するだろうか?
無機質な建築、荒涼とした風景、途切れがちな会話。
その中心で、彼女は何かを語ることも、激しく感情を噴出させることもなく、
ただ世界と噛み合わない感受性として佇んでいる。
それは、ミケランジェロ・アントニオーニ映画におけるヴィッティであり
ふたりの巡り合いが生んだ、
20世紀後半の映画史に燦然と刻まれし、最も象徴的な「虚無の女性像」である。
だが、ヴィッティのキャリアをその像だけで語るなら、
ぼくらは彼女の半分しか見ていないことになる。
彼女はけして、アラン・ドロンのような美意識の引き立て役でもなければ
ブニュエルの元で、解体され、隷属する不条理のアイコンでもない。
なぜなら彼女は同時に、笑い、転び、怒り、逸脱する、
天性のコメディエンヌでもあったからだ。
ここでは、アントニオーニのミューズとしてのヴィッティと、
そこから離れた自由な女優ヴィッティを分断するのではなく、
その振幅全体をひとりの女優の軌跡として捉え直してみたい。
虚無を生きる身体
『情事』に始まり、『夜』『日蝕』、
そしてカラー作品『赤い砂漠』へと続く実存四部作での
アントニオーニ作品におけるヴィッティは、
疎外感と伝達不能性というテーマのもとに
しばしば抑圧された女性として語られてきた。
しかし、この抑圧は社会的な意味での被害者性というより、
世界そのもののあり方を身体で引き受ける役割に近い女だったはずだ。
アントニオーニの世界では、すでに意味は回収不能であり、
人間の感情は風景や建築に先取りされている。
感度のいいヴィッティは、おそらく「何も感じていない」のではない。
むしろ、感じすぎた末に、感情がどこにも着地しなくなった存在なのだ。
彼女の沈黙は内面の欠如ではなく、
世界との関係が断線した状態を可視化するための表現だった。
このときヴィッティは、心理を演じる女優ではなく、
時代の感受性そのものを体現するスクリーンそのものの美となった。
アントニオーニは彼女を通して、近代の終焉、関係の不可能性、
そこから回復なき世界を凝視した。
その意味で、ヴィッティは単なるミューズではなく、
彼の映画倫理を成立させるための不可欠な共犯者だったと言える。
沈黙の裏側で
しかし、アントニオーニ映画のヴィッティを見続けてきた観客が、
後年の彼女のコメディ作品に触れたとき、
少なからず戸惑いを覚えるのも事実だろう。
あの沈黙は本質ではなかったのか?
あの虚無は裏切られたのではないか?
そう感じてしまうのは、ヴィッティを「ひとつの像」に固定してきた
われわれ観る側の無意識の欲望にほかならない。
実際、ヴィッティはもともと舞台出身で、リズム感と身体性に富んだ女優だった。
国立演劇アカデミーを卒業し、シェイクスピアやモリエールの作品に出演し、
演劇をもってそのキャリアをスタートさせた女優だった。
笑いのタイミング、誇張された身振り、言葉の間合い、
それらはアントニオーニ映画の中で封じられていただけで、
消えていたわけではない。
解放としてのコメディ
その封印が鮮やかに解かれた印象を受けたのが
ジョゼフ・ロージーの『唇からナイフ』である。
ここでのヴィッティは、虚無を失ったわけでも、救済されたわけでもない。
彼女はただ、赴くまま、動き、跳ね、戯れる。
ロージーの描くモンドでビザールな世界は、意味の崩壊を隠そうとしない。
だからこそヴィッティは、世界に適応する必要も、理解する必要もなく、
演じる身体として解放されるのだ。
その解放感は、アントニオーニ的虚無の否定ではなく、
虚無が別のかたちで生き延びる可能性を示していたといえる。
この流れを決定づけたのが、イタリア喜劇の名匠たちである。
ティント・ブラスの『私は宇宙人を見た』、
あるいはマリオ・モニチェッリの『結婚大追跡(原題:La Ragazza con la Pistola)』において、
あたかも感情のデパートガールたるイタリア女を最大限に発揮し、
ヴィッティは怒りや欲望、滑稽さを引き受けながら前進する女性を演じる。
黒いレーザースーツを纏い、銃を握る。
実にかっこいいモンドガールである。
だが、そこにあるのは軽薄な解放ではない。
沈黙を知った者だけが到達できる、成熟した笑いを纏うコミカである。
振幅としての女優像
重要なのは、沈黙するヴィッティと笑うヴィッティを、別人として扱わないことだ。そのキャリアを「虚無から笑いへ」という単線的な転向に落とし込んではいけない。
同じ感受性が、異なる世界に置かれたときに示した反応の違いにすぎないのだ。
アントニオーニの世界では、そこに虚無を滲ませ立ち尽くすことが誠実さであり、
ロージーやモニチェッリの世界では、戯れ、ずれることが生き延びる術だった。
どちらも、世界を信じきれないという一点で、深くつながっている。
まさに、ヴィッティは真の女優だった。
モニカ・ヴィッティの立体性
こうして改めて振り返ると
モニカ・ヴィッティは、虚無の化身であり、
同時にその虚無を笑いへと変形させた女優だったのは間違いない。
沈黙も、跳躍も、どちらも彼女自身であることに変わりはない。
そしてその二つを知ってしまった観客にだけ、
彼女の女優像が平面ではなく、立体として立ち上がってくる。
そういえば、小さい頃、寒がりで服を重ね着していたヴィッティは
「セッティ・ヴィスティーニ(直訳すると七つの小さなドレス)」というあだ名を
家族からは冗談でつけられていたというエピソードを思い出す。
つまり、ヴィッティの女優魂の下には
いくつもの感情が幾重にも重ね合わされていたのだ。
彼女は私生活でもアントニオーニのミューズであったが、
その愛情を婚姻という形式にとらわれなかった。
だが、時を重ね、17年間の婚約期間を経て、
そう、彼女は八十になるろうかという2000年に
イタリアの映画監督、脚本家、写真家ロベルト・ロッソと結ばれている。
ヴィッティは90歳越えの人生を全うし、イタリア公共テレビがそれを生中継した。
その万感の思いが届いただろうか?
たが、晩年には認知症を抱え完全にスクリーンを背に、
ロッソと共に完全にプライベートな生活で過ごしたのだった。
そんなイタリアの至宝の輝きは
色褪せることなく、ぼくらは今も彼女を見続ける。
彼女の沈黙が観たい。
そこからまた弾け飛ぶ彼女が観たい。
ただそこにいるだけで成立する存在美。
そして大衆はその奥に続く影の回廊を永遠に追いかけるのだ。
虚無の中に立ち、あるいは笑いながら跳ね回ったその立ち振る舞いは
虚構や幻想というひとことで片付けられない奥行きがある。
そうしたすべてを引き受けた女優としての眩しさの前に、
ぼくらもまたヴィッティのすべてを受け入れ、その魅力に乾杯するのだ。
John Dankworth – Modesty Blaise Theme
ぼくが愛してやまないモニカ・ヴィッティの、この立体的な魅力に近づくには、アントニーオーニ的な気だるさを離れ、まず『唇からナイフ(Modesty Blaise)』のサントラあたりがちょうどいいのかもしれない。このスインギー・ロンドンな空気のなかに、希望の香水と、倦怠の煙草が混じった匂いともいうべき、モンドミュージックが満載に詰め込まれている。音楽は1940年代後半そのスイングジャズが盛り上がるなか、サックス奏者としてのロンドンを席巻し、1960年代には映画音楽家として進出し活動の場を広げたジョン・ダンクワース。漫画のように、そして一つの舞台のように、ガジェットの洪水のなかにあってもモニカ・ヴィッティという花は咲き誇るのだ。






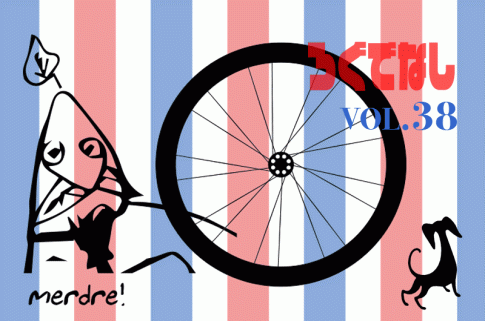





コメントを残す