ロマンの敗北、遠い日の青春に捧ぐ
中島貞夫監督『ポルノの女王 にっぽんSEX旅行』を見たのは
確か、池袋の文芸坐のオールナイト企画だった。
当時はストリーミングもないし、DVDにもなっていなかったはずだ。
今から30年近く前の出来事である。
他のプラグラムがちょっと思い出せないが、
この一本を見れた満足感をなんとなく覚えている。
B級でありながら、どこか男のロマンに満ちた本作を見た興奮は
迎えた夜明けを格別な思いで満たしてくれたと記憶する。
そんな映画を何十年ぶりかで再見した。
この映画に登場する一人の男、
五味川一郎演じるは荒木一郎である。
どうみても垢抜けない指名手配犯の顔をしているが
なんとなく、若い頃の自分の姿にも重なってどこか親近感があった。
荒木一郎といえば、俳優のみならず、歌手、作家、ラジオのパーソナリティ、
そして幾度も騒がせた、まさに昭和世代の才人だった。
デビューは十代、ドラマ『少年探偵団』の明智小五郎役で注目され、
瞬く間に歌手としても大ブレイクした。
「空に星があるように」は今なお歌謡史に刻まれる名曲でありながら、
その後の人生はメディアとの軋轢とスキャンダルに彩られた。
羽仁進の映画『愛奴』でのロケ中に、女優志願の女子高生に手を出して
強制猥褻罪容疑で逮捕されるという、映画を地でゆくような
ドジなスキャンダル事件をきっかけに3年もの謹慎を食らっている。
だが、その脛傷が逆に演技に箔をつけた。
自身のプロデュースにも長け、時に傲岸不遜とも評された彼の存在は、
どこかつかみどころがなく、昭和という時代のヒリついた“裏側”を
そのまま歩いてきたような印象さえ受ける。
彼の魅力は、良くも悪くもそのいかがわしい“クールさ“にある。
スターでありながら、常にカメラのレンズ越しには下層に生きる男ばかり。
すべてを演じきる前に、演じていることの嘘臭さにも気づいてしまう男だ。
そんな醒めた目が、この五味川一郎にもそのまま投影されているのだ。
他人のエロ話に触発され、我もと街ですれ違う女に声をかけるも
不器用すぎて思うようには運ばない。
かけてた牛乳瓶の底みたいなメガネを落として、レンズは割れる。
いざという時には言葉が出ない、おまけに吃る。
そして笑われ自虐に落ちいる、なんとも情けない男だ。
空港で、ひょんなことからスウェーデン娘が勘違いで車に乗り込んでくるが、
日本女すらだめなのだから、外国娘なんてとんでもない、
そういって、いったんは拒むが、言葉が通じないので
その勢いで爆弾製造に励むオンボロアパートに連れ込んで、
ここぞとばかりに、スウェーデン娘を強引にモノにして、
ひとまず、満足感に耽る。
やれやれ、そんな、どうしようもない男を演じている。
『ポルノの女王 にっぽんSEX旅行』において
彼は、欲望に屈し、言葉の通じない人形のような娘にしたい放題を尽くす。
まさに“ろくでなし”である。
しかし、途中で、その己の虚しさにさえ負けてしまう。
負け犬はどこまでも負け犬であり続ける。
一方、小柄なダイナマイトボディ、ロリータリンドバーグ嬢が
艶やかにスクリーンを暴れ回るが、やはり男の力には敵わない。
ここからは、和製「コレクター」の世界、監禁とそして飼育に走る。
フリーセックスの国の自由さにあきてやってきた異国で
その自由さを逆手に取られ手込めにされる悲しさ。
とはいえ、ドジでマヌケで気弱な上に、
ニヒリズムを滲ませる五味川ができることには限界がある。
この映画においての荒木一郎は、いつだって“負け犬”なのだ。
異国からやって来た女を征服するよりも
自分を正当化することで頭がいっぱいだ。
けれど、それは“他者”としてではなく、
逆説的にこの国の“最も日本的な男”の表象として現れるからだ。
つまり、結果的に、その不器用なやり方ゆえに、
知らぬ間に、無垢の愛を手にしてしまう。
まさに神風が吹く。
時折“本音”をぽつりとこぼす。
だがその本音こそは、どこか諦めに満ちている。
「俺が悪かった。帰りな。」
そんな弱腰の声を吐く男に思いがけず愛を奏でてしまうのが
いとしのリンドバーグ嬢、国境を超えた女のサガなのか。
人形のような可愛い佇まいで、それゆえに男の欲望のおもちゃにされる女。
しかし、荒木のその佇まいにはロマンチスト特有の“歪み”がある。
それは、自分がロマンの中心に堂々と立てないことへの歪みではなく、
自分の限界、ロマンという虚構を知っているがゆえに、
あえて主役を引き受けることへの照れのような美学で、
3枚目に甘んじるしかないのだ。
そして、それが異国娘を受け入れた瞬間に
またまた勘違いをして、自分が負け犬だったことをつい忘れてしまう。
荒木には彼の過去には小説家としての顔もあった。
たとえば処女作『ありんこアフター・ダーク』には、
性と死、孤独と自嘲が交錯し、
どこかこの映画と同じ匂いが漂っている。
自らの青春にピリオドを打ち、そこに「苦笑」を添えて物語化する力。
それが彼の最大の魅力であり、同時に彼を
“昭和の男”として時代に埋没させなかった所以でもある。
五味川一郎は、恋に焦がれて、成功者を遠く夢見て敗れ続ける男であり、
その怒りの果てに、所詮、自らをも傷つけてしまう不器用な男だ。
ただ異国の女のとなりで、その性を眺め、夢をみることしかできない。
彼が知る現実は、爆弾という逃げ口上しか持ち合わせていない。
だがその姿こそが、まさに当時の日本、
いや昭和という「成熟しきれなかったロマン」の象徴なのだ。
金も女も未来もない、自己肯定さえない負け犬としての自分。
それでも、男たちは夢を見続けた。
着実に、一歩一歩歩き続けるしか成功の道はない。
その憧れの集積に、熱意と汗を涙をそそぎこまれたロマンが花開いた。
それが高度成長を遂げた日本の真の姿であろう。
ここにはその擬似体験しかない男の夢が哀愁を誘う。
異国の女、解放されたセックスへの憧れ。
そこに言葉などいらないが、愛の実体を期待しても無駄だ。
その夢は、手を伸ばした途端に遠のく泡のようであり、
男を狂わせ、男を嘲笑う。
そして一人の男は、窮鼠猫を噛むかのごとく
最後の砦、ダイナマイトをちらつかせて
自ら世界を終わらせようとする。
この情けなさこそが、荒木一郎がずっと演じ続けてきた
“昭和の男”そのものの原点だったのだ。
ひとつのロマンの終着点。
ただその背中に、時代の希望があった。
そこに、我ら昭和に生きた青春がそこへと重なる。
フリーセックスからの危険な遊戯への手招き。
そしてひとつの場所に居座れない不安、自由への憧れ。
そうした哀愁のロマン漂う中島貞夫の和もの青春映画、
ロードムービーとしての情感を含ませた本作は
当時のまだ人生の酸いも甘いも知らなかった若輩の自分にでも捧げようか。
まさに若きみうらじゅんあたりが考えそうな妄想は
確かに、どこかで夢見ていたことかもしれないのだ。
Virna Llindt – I experienced love
スウェーデン・ストックホルム出身のVirna Lindt(ヴァーナ・リント) は、お色気、というよりはインテリで、単なるポップとは一線を画し、ニュー・ウェーヴ、サウンドトラック的なドラマ性、そしてちょっぴりスパイ映画のような気配が混ざったユニークなスタイルを持っていたシンガーで、1980年代初頭のインディ・ポップ/シンセポップ・シーンにおいて、独特の存在感を放っていた。そのスタイルは「ジョン・バリー meets ニュー・ウェーヴ」と評されることもあって、クールに、しかしどこか謎めいた情緒を含んでいて、まるで夜の街角の灯りを背にした女性像を描くようなムードは、レトロでシネマティック、そしてポップな誘惑に満ちている。この『ポルノの女王 にっぽんSEX旅行』には、ヴァーナのファーストアルバム『SHIVER』に収録の「I Experienced Love」を捧げよう




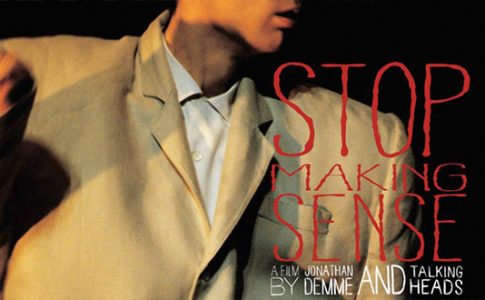








コメントを残す