団結美学のペーソスを浪花語りで
長谷川安人監督の『集団奉行所破り』は
東映時代劇の中でも特異な輝きを放っている一本だ。
注目すべきは、舞台が江戸ではなく大阪であること。
冒頭の市川小金吾の浪花語りには、思わず引きこまれる。
このリズムが映画をテンポ良く、コメディ調に運んでゆく。
チャンバラでもなく、勧善懲悪でもなく、もっと滑稽でもっと人間臭い。
波止場に吹く湿った風にきく話として、
かつて海を渡り盗み、戦い、笑っていた男たちが再び集う群像ものだ。
彼らはもはや海賊ではないが、
時代に追われ、波に居場所を失っても陸に上がった“元海賊”たちであり、
どこかアウトローとしての連帯関係にむずばれている。
だが、東映映画の定番の、あの波しぶきのオープニングのように
彼らの血の奥にはまだ潮の音がはげしくくすぶっていることを証明する。
そこには、脚本を手がけた小国英雄の、
構造と笑いを兼ね備えた知恵がみごとに息づいている。
小国英雄といえば黒澤明の盟友として知られる脚本家である。
『七人の侍』『用心棒』『天国と地獄』など。
どの作品にも共通しているのは、“構造としての人間ドラマ”だ。
善悪ではなく、立場の交錯。
個人ではなく、集団の力学。
それゆえ彼の筆は、常に
社会の仕組みそのものを描こうとする野心が見え隠れする。
『集団奉行所破り』でも、その構造美は健在だ。
奉行所という制度の象徴を中心に据え、
そこに反旗を翻す元海賊や素浪人、スリ師、藪医者、スケコマシ。
アウトローたちを適時適所に配置する。
つまり、これは“七人の侍”の裏返し版であり、
“天国と地獄”の滑稽な転写だと気付かされるだろう。
この脚本の巧みさは、集団が動くとき、世界があらたに呼吸をみせるという
小国ならではのリズムにあると思う。
一人ひとりが違うテンポで話し、違う理由で笑い、違う夢を見ている。
それが大阪という町の空気と混じり合い、
まるで落語の寄席のように転がっていく仕立てが面白さを生む。
江戸の時代劇が「武士の論理」で語られるのに対し、
大阪の物語は「商人の言葉」で動く、
つまりは情と絆と現実のバランスということなのだ。
しかし、義理より利、名誉より勘定、
そして何より“笑い(ペシミズム)”がものを言うのが商人(あきんど)の世界。
大阪は、いわずとしれた江戸時代から“天下の台所”として栄えた商都である。
廻船問屋、両替商、米仲買、彼らは日本の経済を支配しており、
だが、その裏では、密貿易や裏金、贈賄が日常的に行われていた時代だ。
奉行所はそうした経済の監視役であると同時に、腐敗の温床でもあった。
小国は、この「制度と商人の癒着」に目をつけ戯画化する。
佐藤慶扮する悪徳奉行の腹心、まむしの金次郎こと竹内金次郎は、
かつては奉公人として使えた家を裏切って、今の地位にある男だ。
理屈と冷笑で動く成り上がり権力の顔である。
それに対し、金子信雄扮する元海賊の軍師・勘助は、
庶民の知恵を武器に闘う“口八丁の策士”だ。
制度対民衆、理性対知恵。
ここに小国の社会観が実に機能している。
大阪弁のリズムが、映画の根幹をなすのは冒頭から導線が敷かれているが
掛け合いがまるで落語の「噺」のように転がり、
一つひとつの会話が、剣戟よりも痛快な切れ味を放つ。
いわば会話のキレが絶妙な映画になっている。
この言葉の音楽性こそ、小国英雄が黒澤作品で培った
「会話のリズム」を庶民語に翻訳した成果として描かれているのだといえる。
この映画の最大の魅力は、なんといってもキャストのアンサンブルだろう。
勘助役の金子信雄を筆頭に、大友柳太朗、内田良平、里見浩太朗
そこに伏兵で神戸瓢介、市川小金吾、そしてベテランの田中春男の味。
これだけ達者がそろば、十分面白い作品になる。
東映の黄金期を支えた“役者職人”たちが、
各々のリズムで舞台を作り上げてゆく。
金子信雄といえば、なんといっても仁義シリーズ。
あの山守親分の味を想起するところだが、
黒澤映画の理知的世界とは対極にある、
ずる賢くも憎めない庶民の知恵を体現している。
が、その統率力に長けたそのしゃべり口には、
ネコさん節たるどこか飄々とした温かみもある。
彼が口八丁で仲間をまとめる姿は、侍ではなく“噺家”のそれであり、
その容姿外見からも、どこか、名人たる枝雀師匠を彷彿とさせる。
大友柳太朗の素浪人は悪源太とよばれ、
寡黙でありながら闇を抱え込んでいる。
幼少の頃、町奉行の欲望の前にさらされた
母親の無残な姿がこびりついているという設定だ。
彼の剣は、かつての誇りを引きずる武士の哀しみと怒りを宿している。
言葉で動く勘助とは対極に、沈黙で語る源太。
この対比が映画全体に陰影を与えている。
最後出入りの死闘で犠牲になった源太を弔う鶴の折り紙が
なによりも哀愁を誘うエンディングに無常を運んで来る。
内田良平演じる藪医者・道伯は、傷の処置に痔の薬をあてがう偽医者であり
知識人の皮肉を背負った滑稽な存在でもあるが、
最後には、きっちり、その実力を発揮し、集団を鼓舞する策士でもある。
田中春男の吉蔵には、“すぼけ(素呆け)’といわれるほどの
卑小な小市民の風刺が効いている。
が、そのすぼけゆえに、情を寄せる女が哀愁を引き立てる。
そして、東映ニューフェイス、里見浩太朗スケコマシ適役の丹次郎や、
神戸瓢介&市川小金吾のスリ師コンビは、完全に“漫才のノリ”で色を添えている。
彼らの場面では、時代劇が一瞬、よしもとならぬ東宝喜劇へと転調するのだ。
このように、全員が主役であり、全員が脇役でもある。
それこそが小国英雄が『七人の侍』以来磨き続けた群像の美学というわけだ。
まるで群像映画の描き方の見本のように、
誰もが一つの駒でありながら、全体の動きの中でのみ生きることに徹し
それが人間社会というものの滑稽さと愛おしさを象徴する。
物語の発端となるのは海賊時代に自分達を守ってくれた、
廻船問屋河内屋善右衛門が御上の利権によって
無碍にされているという“情”である。
その「七回忌」という法要は単なるプロット上の仕掛けではない。
仏教における七回忌は、死者の霊がようやくこの世を離れ、来世へと旅立つ節目。
つまり“忘却”と“再生”の境界にあたる儀式なのだ。
脚本では、この七回忌を「記憶を呼び戻す装置」として用いている。
かつて奉行所に奪われた財、失われた義理、そして死者への恩。
それらを思い出す者たちの行動が、無謀な“奉行所破り”へとつながっていく。
この設定によって、単なる盗賊劇が、記憶の奪還劇へと昇華されている。
七回忌は制度の外にある“情の律法”であり、
奉行所は制度の内にある“権力の律法”である。
この二つが衝突するとき、笑いと悲しみが入り混じるが、
そこに大阪という土地のペーソスが宿すことでうまくバランスが保てる。
それゆえに大阪人の笑いには、権威への抵抗が含まれてくるのだ。
『集団奉行所破り』は、その精神を時代劇の中で見事に再現した。
奉行所という制度の“壁”を、剣ではなく笑いで破る。
彼らの武器は知恵と会話、そして連帯だ。
映画のクライマックスは、勘助たちが一斉に奉行所へなだれ込む場面。
その姿は「乱」ではなく「祭」に近い。
制度を笑い飛ばし、死をも冗談に変える。
それがこの映画の最大のカタルシスとして機能している。
長谷川安人の演出は、派手な殺陣よりも“人の顔”を重視することにあり、
アップの連続によって、笑いと涙が交錯する。
まるで大坂の芝居小屋で演じられる人情噺のように、
観客はいつの間にか、笑いながら胸を熱くすることになる。
小国英雄は、黒澤の下でかような「構造の詩学」を学び、
長谷川安人と共に「庶民の詩学」へとたどり着いた人だ。
『集団奉行所破り』の群像は、権力に挑む英雄ではなく、
制度の狭間に生きる“哀しき笑いの職人たち”の趣がある。
彼らは語り、騙し、笑い、つかの間の自由を掴むほんとうの自由人たちである
そんな時代を超えて“生きる知恵”そのものだ。
ゆえに、愛しく、そして乗れるのだ。
海の匂い、関西弁のリズム、役者たちの間合い。
それらすべてが、江戸の権力構造を笑い飛ばした庶民の声として響くことで、
それを娯楽に落とし込むことにまんまと成功している。
そしてラスト、笑いの渦が収まった後に残るのは
どこか懐かしくも、大阪という土地の哀歓と、
人間という存在の“やるせない明るさ”のツケなのだ。
起承転結に抜かりなく、見事に心に残る仕様である。
ファニー・カンパニー – スゥィート・ホーム大阪
70年代初頭、横井康和が桑名正博と出会い結成された浪速のロックバンド、
その名もファニーカンパニー。
「東のキャロル、西のファニカン」と呼ばれたほどに、その実力を物語る。
なんといってもメインは桑名正博のココテコテ関西弁のボーカルだ。
シティポップの流れでも、もっと評価されていいシンガーだと思う。
そんな桑名の歌う「スゥィート・ホーム大阪」は、
なんの関係もないのに、笑うほど『集団奉行所破り』に馴染んで聞こえる。
時勢にはどこか叛逆的でありながらもユーモアと哀愁が滲む曲。
一晩かぎりの、笑いを伴った意趣返しを試みたストーリーに、
旅立ちを宣言しながら哀愁を隠さず歌い上げる歌。
まるで寄席の高座のように、共に言葉のテンポで転がっていく。
この映画に、ファニー・カンパニーの
「スゥィート・ホーム大阪」を贈りたいと思うのは、
その笑いの底に流れる感情が、驚くほどよく似ているからだ。
クライマックスの騒動が終わったあと、
もしこの映画にエンディングテーマが流れるとしたら、
派手な勝利の音楽では似合わない。
少し緩くて、少し照れくさくて、
「まあ、こんなもんだっせ」と肩をすくめるような曲がいい。
奉行所は破れても、大阪そのものはなにも変わらない。
それでいいのだ、とこの映画も、この歌も、静かに言っている。
制度に対する真正面からの抵抗ではなく、
「まともに相手をしない」という、浪花的な反骨として機能する哀愁。
笑って破り、何事もなかったように街へ繰り出すための歌。
これこそが浪花の流儀であり、『集団奉行所破り』と共有する空気だ。
つまりそれは勝者の歌ではなく、生き残ってしまった人間の歌だからだ。






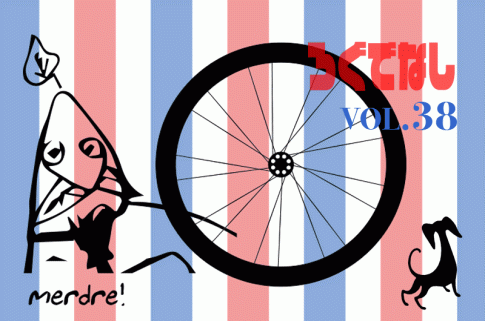






コメントを残す