初めにジャーありき
ボブ・マーリーに関しては、高校生のころから聴いてはいる。
ただジャンルのひとつとして、漠然と聴いていた気がするし、
当時はレゲエに影響されて出てきたニューウェーブやポップミュージックの
楽曲のなかのレゲエの方に、より親しみをもっていたといっていい。
大学に入ると同時にバイトをしはじめたとあるカフェで
出会った連中がみなレゲエが大好きな人ばかりだったことで、
その風向きが少しずつ変わってゆく。
不思議なことに、そのカフェ空間では、オーナーの好みから、
レゲエとマリア・カラスとスティーブ・ライヒが混じり合って再生されていた。
ぼくの真のレゲエ体験は、そこから始まったといっても過言ではない。
彼らが熱狂するレゲエの魅力にはまってゆくのはそれからだ。
こうして、長い間、聴いては来たものの、
その本質というか、レゲエの真の良さに気づくのはもっと後のことだった。
そう、人生を重ねて、リアルにその音楽の魅力へとようやく辿り着いたことになる。
その意味では、レゲエしかり、ソウルしかり、魂のある音楽は、
中身(魂)を伴わない人間には縁遠い音楽なのかもしれない。
そう思うのだ。
話を改めてボブ・マーリーに戻そう。
「One Love,One Heart!」
この言葉ほど素直に世界中で口ずさまれ、
願いのように響き続ける歌はないだろう。
だが、その裏にあるボブ・マーリーの痛み、叫び、苦悩、そして人生、
僕らはいったいどこまで理解しているのだろうか?
レイナルド・マーカス・グリーン監督による『ボブ・マーリー:ONE LOVE』は、
単なる音楽の回顧ではなく、ボブ・マーリーというひとりの人間が
時代と社会に対してどんな戦いを挑み、どんな和解を果たしたか?
その魂の遍歴を描いた映画である。
音楽ファン、レゲエファン、誰もが知るレジェンドを
いま改めて振り返るいいタイミングがやってきたのだ。
映画としてみれば、批評家の評価こそ平均的だったものの、
一般の観客には深く支持されたと言っていいだろう。
母国ジャマイカでは、史上最高の初日興収を叩き出し
全米及び14の国と地域で初登場No.1を記録したの無理もない。
それはレゲエが世界中で認識され、愛されていることの証だ。
ただ、この手の映画評価が難しいのは、
まずは、演じるものと実在の人物との乖離があればあるほどに、
映画そのもの訴求力が薄れてしまうことにある。
遠い歴史の人物ならいざ知らず、
ある程度、記憶を共有できる人物の場合はなおシビアである。
その点、同じく、クイーンの伝記映画『ボヘミアン・ラプソディ』での
ラミ・マレックの熱演と映画の成功で、
ひとまず、この手の試みが、胡散臭く失敗作には終わらないということを示した。
『ボブ・マーリー:ONE LOVE』も、幸い、その流れにあると言っていいだろう。
批評家が「定型的」と評した構成も、
マーリーの人生に触れたことのない新しい観客層には
“癒しの入門書”のように機能したはずである。
この後に、ボブ・マーリーの楽曲や本場レゲエをじっくり聴き、味わい、
さらに、その音楽への探究の旅に出るきっかけにもなることだろう。
単なるヒストリーという意味なら、
『ボブ・マーリー:伝説のルーツ』といったドキュメンタリーなどを観ればいいし、
1979年7月、ジャマイカで開催された第2回レゲエ・サンスプラッシュに出演したボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズの圧巻のパフォーマンスを記録した、
シュテファン・パウルによる「ボブ・マーリー ラスト・ライブ・イン・ジャマイカ レゲエ・サンスプラッシュ」などを観れば、素晴らしい音楽的体験もできるだろう。
替えの利かない主役を、こうして映画化に際して、
かつてマルコムXを演じた男が、レゲエのレジェンドに挑んだ、
主演のキングズリー・ベン=アディルによるマーリーの再現によって、
外見のコピーとパトワ(ジャマイカ訛りの英語)による語り以上に、
あの独特のリズム感、
沈黙の中の光を宿した眼差しを捉えたことが
高く評価されたことに、異義を唱えるつもりはない。
とはいえ、はたして映画だけで十分感動的か?
というシビアな問いには、どこかで、素直に頷けない自分がいる。
あえて、誤解を恐れずにいえば
この映画は、“レゲエ編大河ドラマ”としてみるぐらいで
ちょうどいいのかもしれない。
ボブ・マーリーの真の偉大さ、その音楽への愛/深みを感じるものなら、
そのあたりは永遠のテーマであり、逃げることはできないはずだ。
それらをどう伝えていくのか?
その課題は残されたといっていい。
この映画で描ききれなかったものを、逆に見出して、
ボブ・マーリーとは何者だったのか?
レゲエとは、ラスタファリとは? そういう思いに駆られるならば、
この映画はそれだけでも価値はあるのだと思う。
とはいえ、この映画もまた「One Love,One Heart!」の名の元に愛された。
ボブ・マーリーの音楽が、レゲエが普遍的に愛されているように。
音楽シーンは映像的にもうまく構成されており、
とくに1978年のワン・ラヴ・ピース・コンサートの再現には、
観客も思わず息を呑む。
暴力と対峙し、音楽で和解を果たすボブの姿は、
単なるミュージシャンを超え、使者的存在として立ち上がる。
レゲエは、いわばジャマイカという音楽のるつぼで生まれた、
進化系のポピュラー音楽である。
スカ、ロックステディ、アメリカのR&Bやアフリカの儀礼音楽、
あらゆる要素を吸収しながら、1970年代に確立されたジャンルであり、
「リズムの逆転」「空白の強調」「重厚なベースライン」
そして「ワン・ドロップ」のリズムで構成される唯一無二な形態だ。
そこに、伝道師ボブ・マーリーの魂が乗る。
つまり、それ以上に重要なのは、レゲエが単なるサウンドではなく
「精神の言語」を司るという点だ。
マーリーはその言語を用いて、ラスタファリズムの思想、
黒人解放、エチオピア回帰、スピリチュアルな再生を詩的に、
かつ政治的に発信し続けたことに意味がある。
映画を通しても、そのことはきっちり掲げられてはいる。
では、命をかけてマーリーが叫ぶ「JAH」とは何か?
神の名であり、抵抗の象徴であり、精神の声である。
西洋人にとってのイエス・キリスト同様、
マーリーにとっての音楽とは、祈りであり、説法であり、
時代の外に響くメッセージだった。
トレンチタウン、つまりはゲットーに生まれたボブ・マーリーの人生は、
消して平坦ではなかったが、けして孤高なものではなかった。
彼の背後には常にリタの母性と、”The Wailers”があった。
何しろ、伝説の初期のピーター・トッシュ、バニー・ウェイラーとのトリオ時代は、
ゲットーの叫びと若き情熱のコーラスだった。
アイランド・レコードとの契約によって音楽が国際化する一方、
内紛や方向性の違いにより1974年にトリオは解散を余儀なくされたが、
その後、アストン・”ファミリー・マン”・バレット率いる新生Wailersとともに、
より宗教的・霊的な音楽へとシフトしていった。
I Threes(リタ・マーリー、ジュディ・モワット、マーシャ・グリフィス)による女声コーラス隊は、マーリーの音楽に”母性”と”光”を与えたのだと思う。
マーリーの声が祈りなら、I Threesの声は癒しといっていい。
ロックの世界においても、マーリーはまさに“異端の王”だった。
彼はギターもち、反体制を叫ぶロックの精神を持ちながらも、
リズムの奥深さとスピリチュアルな言葉の重さを持っていた。
マーリーの出現によって、世界の音楽は“前方に進むビート”から、
“後方にうねる波”へとシフトすることになる。
彼の存在は、レゲエをポップカルチャーの中に定着させただけでなく、
ポリティカル・ミュージックに愛と赦しを持ち込んだ偉人だ。
ヒップホップ、アフロビーツ、ワールドミュージック。
マーリーの影響を受けたジャンルは数知れず。
レゲエとは、踊る祈り、低音の抵抗、ルーツ回帰への共鳴の言葉になった。
とはいえ、こうして言葉を重ねても解決には至らない。
それは映画とて同じことだ。
映画『ONE LOVE』は、音楽映画としても、伝記としても、
しかし、それを伝えようとしていることは伝わってくるが、
そもそもが、マーリーの”神格化”ではなく、”人間化”ではなかったか?
傷つき、迷い、祈りながら、それでもなお歌うことを選び続けた男の物語が
そこにまぶしく描き出されている点には寄り添うしかない。
この映画は、ボブ・マーリーという“伝説”が、
現実に生きて、揺れて、叫んでいた“声”だったということを思い出させてくれる。
ボブ・マーリーの死から40年以上経ったいまでも、
彼の音楽への愛は消えることがない。
それはなぜか? 彼の音楽が“商品”ではなく、“遺言”だからだろう。
金ではなく、名声でもなく、その魂に殉じたのだ。
息づくラスタファリズムは人生の羅針盤であり、歌うための信仰だ。
そこに込められた言葉、音、リズムは、誰かの自由を願う力、
共に生きようという祈りとして、ぼくらの耳を越えて魂に届く。
映画のなかでは、ボブが常に暴力や抑圧に対して直接的な敵対ではなく、
音楽を通じた和解と共鳴を選ぶ姿勢が繰り返し描かれている。
暗殺未遂事件の直後には「Smile Jamaica」でステージに立ち
「One Love Peace Concert」では、敵対する2人の政治指導者を
ステージ上で握手させるシーンも描かれている。
常に、政治に利用され、不安定な祖国の政治状況に翻弄されながらも
彼の真の偉大さは、権力者側にはなびかず、
最後まで、レゲエへの愛、ラスタファリズムへの献身を貫いたことである。
その結果、ガンに侵されても彼は西洋医学への道を閉ざし、
36歳の若さで、志なかばでこの世を去ってなお、英雄視され続けるといった
ひとりの伝説譚として、映画を見ることもできるだろう。
とはいえ、映画『ONE LOVE』は、それだけで完璧なわけではない。
だが、完璧でないからこそ、そこに宿る不完全な祈りが、よりリアルに響く。
われわれが今なお、混沌とした世界情勢に生きているさなか、
One Love、その言葉を、今こそどう聴くべきなのだろうか?
われわれは、それを音楽の力で癒し、癒され、
さらに次世代に伝えてゆく使命を帯びるのを強く感じるのだ。
『ボブ・マーリー:ONE LOVE -オリジナル・サウンドトラック-』
- 01.Get Up, Stand Up
権利のために立ち上がれという、ラスタの教えと抵抗の精神を体現する代表曲。マーリーとトピーター・トッシュの魂の結晶。沈黙を破る最初の一歩がここにある。 - 02.Roots, Rock, Reggae
アメリカの黒人音楽文化とラスタ的精神の橋渡しをした、軽やかで骨太なレゲエ讃歌というべきか。黒人音楽の血脈を紡ぎ直す、踊れるマニフェスト。 - 03.I Shot the Sheriff
エリック・クラプトンのカバーで有名になった一曲。不正義に対抗する象徴的な一撃。自己防衛の権利と告発をラスタ的に語る寓話的楽曲。 - 04.No More Trouble
「戦争はいらない、もう問題はごめんだ」と祈るように繰り返される。銃弾より祈りを、怒りより静けさを。今こそ歌われるべき曲。彼の“非暴力”への願いがここにある。 - 05.War / No More Trouble(Film ver.)
ハイレ・セラシエの声と共鳴する音の檄文。戦争を否定する歌ではなく、“闘い方の提案”だ。 - 06.So Jah Seh(Film ver.)
「恐怖を恐るな、わたしがそばにいる」、Jahがそう言ったという、ラスタファリズムにおける“神託”の歌だ。 - 07.Natural Mystic
風に混じる見えない気配。天上からの声。予言者としてのマーリーの側面。映画冒頭での神秘的な導入にも使われた、「霊の気配が風に混じる」ような象徴的楽曲。 - 08.Turn Your Lights Down Low
愛の静けさと赦しを奏でるロマンチックな一曲。リタ・マーリーとのデュエットも名高い、内省的ラブソング。 - 09.Exodus
マーリーが暗殺未遂事件から回復した後のロンドンでレコーディングされた名盤のタイトル曲。「脱出せよ、バビロンから」、は魂の旅路。“出エジプト”は内なる解放のメタファー。ラスタ的アフリカ回帰の最重要テーマ。 - 10.Jamming
リズムと共同体がひとつになる祝祭のような曲。“Jah”と“Love”の融合がここに。戦う音楽に宿る“喜び”の発露。ちなみにjamminとは、歌ったり踊ったりと気持ちのいい時間を過ごすという意味だ。 - 11.Concrete Jungle
ゲットーの苦悩を歌ういながら光を探す歌。都会の閉塞感、「空は見えても、自由は見えない」という切実なメッセージからの人間回帰への道標。 - 12.No Woman, No Cry
カバー曲も多い名曲。「泣かないで、愛おしき人よ」。女性とトレンチタウン共同体への哀歌。 - 13.Three Little Birds
隠れた名曲。ボブとウェイラーズによって設立されたタフ・コングのあった、キングストンにあるホープ・ロード56番地の窓のそばに現れた鳥たちがインスピレーションの源だ。小鳥が語る「ささいなことは全てなんとかなるものさ」。癒しの極致ともいえるシンプルな希望の歌。 - 14.Redemption Song
晩年のアコースティック曲。「精神の奴隷から自らを解放せよ」と語る遺言のような楽曲。最もシンプルで、最も重い遺言。映画の中のハイライトシーンのひとつに歌われる曲。 - 15.One Love / People Get Ready
ウェイラーズの1stアルバムに収められていた、ボブの代名詞たる曲。愛は分断を越える。最も有名で、マーリーの最大のメッセージソング。 - 16.Is This Love
これは愛だろうか? 誰かを信じることの不安と喜びを歌う。
愛と平穏への献身が感じられる美しいミディアムバラード。 - 17.Rastaman Chant
アンチバビロン。祈りの根源、太鼓と声と煙の中に神はいる。宗教儀礼的な霊性の核ともいえる一曲で、ラスタマンとしての使命が込められる。映画の祈り的締めくくりに流れる曲。









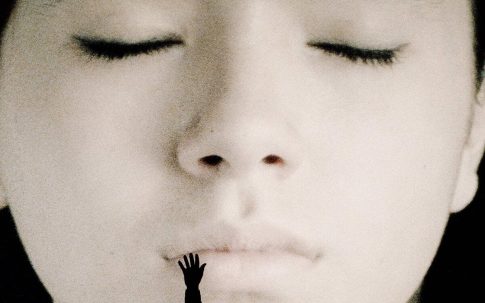
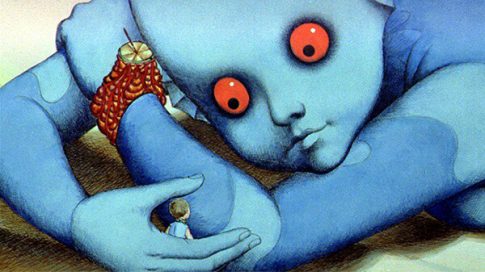


コメントを残す