読み語るムジカと聴き視るポエジア(小説編)
文学と映画をめぐる考察として、グダグダ、ダラダラと
思うところを綴ってきたのだが、この特集の最後を、
文学と音楽をめぐるコラムを挟んで〆たいと思う。
ミュージシャンの中にも本好き、読書好きは多いと思う。
とりわけ、シンガーソングライターにとって、曲を書くことは、
ある種の文学的センス、文学趣味が大いに関与するところだろう。
昔から、僕は好きなミュージシャンがどんな本を読み、
どうインスピレーションを得ているのかに関心を持っていた。
それぞれ、触発された本や文学から直接、楽曲へと向かう場合もあれば、
ミュージシャンの生き方そのものが、リスペクトする文学者に重ね合わさることもあるかもしれない。
本はいつだって、我々にもミュージシャンにも、
インスピレーションの源であり続ける。
中には、自分で文学作品を書くミュージシャンだっているし、
その詞の世界は文学以上に難解である場合もある。
音と言葉の共鳴と共存。それが文学という名の洗礼を浴びて、
よりいっそう豊かに響くのだ。
そうした側面を吟味しながら音楽を聞けば、
また違った音楽の魅力にたどり着けるかもしれない。
文学と音楽を嗅ぐ旅、夢見るプレイリスト
The Beatles:Norwegian Wood (This Bird Has Flown)
サニーデイ・サービス:苺畑でつかまえて
マライア:うたかたの日々
大瀧詠一:乱れ髪
Kate Bush:Wuthering Heights
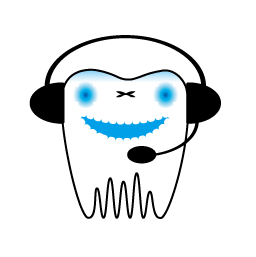
ピンク・フロイドのデヴィッド・ギルモアに見出され、その後1977年、ケイト・ブッシュは19歳の若さで「Wuthering Heights」で音楽界に鮮烈なデビューを果たす。インスピレーションの源は、エミリー・ブロンテの同名小説『嵐が丘』と、それを映像化したテレビドラマだった。ドラマを観た夜、彼女は衝動的に曲を書き上げ、キャサリンの亡霊の視点から、ヒースクリフへの哀切な呼びかけを音にした。
♪“Let me in your window”──その一節は、小説における最も幽玄な場面、キャシーの魂が窓辺に現れる描写をなぞる。幻想的なファルセットは、まるで彼岸からの声のように揺らぎ、原作のゴシック的情念をサウンドで再現する。メロドラマと純文学の境界を超えたこの曲は、単なるオマージュに留まらず、小説の核心──「死してもなお続く愛」──を、三分間の曲に昇華した。
ケイト・ブッシュはこの1曲で、音楽における文学的想像力の可能性を押し広げたと言える。そして彼女自身が、嵐が丘を彷徨うキャサリンの声となり、聴く者の窓辺に今なお囁き続けているのだ。
たしか、この曲ってTVバラエティ「恋のから騒ぎ」のOPに使われていたんだっけ? ちなみにケイト自身、TVドラマ視聴後、彼女はたった1晩でこの曲を書き上げたとされており、作曲はピアノで行い、録音用のカセットテープに吹き込んだと本人が証言している。歌詞は、ヒロインであるキャサリンの霊の視点から書かれており、原作小説の中盤に出てくる「ヒースクリフ、私よ、キャシーよ」という亡霊の呼びかけの場面を忠実にトレースしている。
DAVID BOWIE:1984
IGGY POP ·Mass Production
Steppenwolf:Desperation
戸川純 :眼球綺譚
南佳孝: 冒険王
加藤和彦:アラウンド・ザ・ワールド
冥丁:夢十夜
プレイリスト一覧
- The Beatles:Norwegian Wood (This Bird Has Flown)
- サニーデイ・サービス:苺畑でつかまえて
- マライア:うたかたの日々
- 大滝詠一:乱れ髪
- Kate Bush:Wuthering Heights
- DAVID BOWIE:1984
- IGGY POP ·Mass Production
- Steppenwolf:Desperation
- 戸川純 :眼球綺譚
- 南佳孝: 冒険王
- 加藤和彦:アラウンド・ザ・ワールド
- 冥丁:夢十夜




![[門戸無用]MUSIQ](https://lopyu66.com/wp-content/uploads/2020/11/misiq-1-485x300.gif)

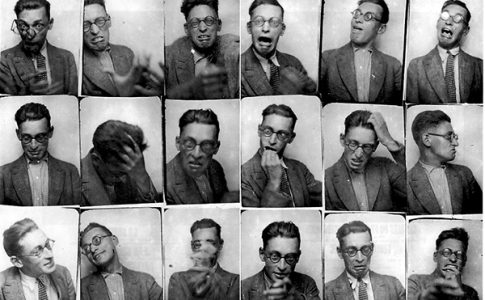

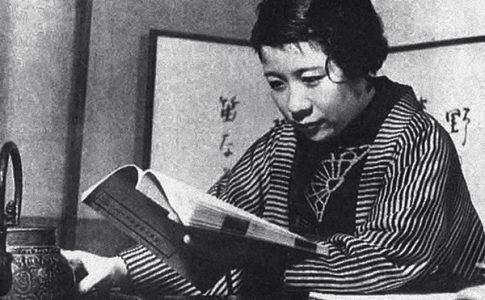

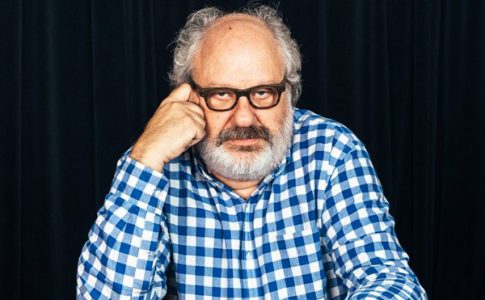


この曲だけはちょっと、異質である。というのも、曲が先にあっての文学だからである。が、特別枠として、まずは冒頭、ここから始めさせてもらうことにする。
村上春樹の小説『ノルウェイの森』は、ビートルズの同名曲から始まる。ハンブルク空港、流れる機内音楽。突然耳に入った「Norwegian Wood」の旋律が、主人公ワタナベの過去の記憶を静かに呼び起こす、それが物語の発火点になっている。
僕自身、ビートルズの「Norwegian Wood」を初めて聴いたとき、まだ村上春樹の『ノルウェイの森』とは結びついていなかった。熱心な村上春樹読者じゃなかったこともある。そこから時間を経て、アコースティック・ギターの旋律に乗って語られる、この男と女の出会いの物語を味わいながら、やがて煙草と静寂と虚無が交差する時間を共有することになる。
この曲は、ビートルズ中期の異色作だが、アコースティックな響きと、シタールの導入によるエキゾチズムが、心地よくもどこか切ない香りが漂う。曖昧な関係とすれ違う心が、わずか2分余りの楽曲に込められているこの空気感こそが、小説全体に漂う“親密さと孤独”の予兆として繋がっている気がしてくる。
村上はインタビューで「この曲を聴いて物語が一気に立ち上がった」と語っている。つまり『ノルウェイの森』という小説は、曲から生まれ、曲へと回帰する“音楽的記憶小説”なのだ。語られるのは、青春の傷と、癒えぬ喪失の物語。その森はどこか美しく、優しい旋律に包まれているが、その萌芽がこのビートルズの曲のなかに、すでにあったようにも思えてくる。〈She showed me her room, isn’t it good, Norwegian wood?〉という無垢な問いからも、“別れ”を予感させる調子に変わってゆく。だからこそ読者は、ページをめくりながら、そっと音に耳をそばだてているだけの幸福を味わうのかもしれない――あの、消えそうな木の香りとともに。
ちなみに「Norwegian wood」というのは、意訳をすれば「ノルウェイ製の家具」っていうのが定説であって、「森」ではないということである。当の村上春樹は『ノルウェイの木をみて森を見ず』というエッセイで、Norwegian Wood=ノルウェイ製の家具、ではないことについて触れているが、この辺りの文学的解釈というか、流れに関しては、また別の機会に取り上げてみたい。