貨幣の寓話
カネは天下の回りもの、人の手から手へと移り行く媒体であり、
いわば、人の間をしらないうちに媒介するウィルスのようなものかもしれない。
ロベール・ブレッソンの遺作、その名も『ラルジャン』もまた
今は無き、そのブレーズ・パスカル旧500フラン紙幣にノスタルジーをそそられながら
1枚の贋金が一人の青年を狂わせることになる貨幣の寓話だ。
アンドレ・ジイドによる小説『贋金つくり』が書かれた国、
フランスのパリを舞台にした現代版の寓話には
その硬質で静謐な映像の中に、人間の変質、社会の冷酷、
そして神の沈黙という大きなテーマが、ほとんど不可視の形で織り込まれている。
トルストイの短編『にせ利札』を原作としながら、
ブレッソンは、この道徳的物語を説教臭く描くことを潔く拒絶する。
ひたすら無表情なカメラと、モデルと呼ばれた素人俳優たちによって、
まるで機械が悪を運んでいくかのような、非演技的における“構造の悲劇”を描き出し
まさに贋札づくりに欠かせぬ、確かで完璧な職人芸が支えるこの映画は
いみじくも職人ブレッソンの「シネマトグラフ」に傑作を残し終わりをつげた。
物語は、ある高校生ノルベールが父親からもらう小遣いが足りないと、
その工面のため相談する悪童にそそのかされ、写真店で偽札を使うところから始まる。
その紙幣は、まるで呪いのように次々と他者に手渡されてゆき
何人かの人生を破滅させていくのだ。
なかでも特に重要なのがイヴォンという人物である。
どこにでもいる、いわ任意に選ばれしこの生贄たる男は
この偽札によって巻き込まれた罠によって職を失い、
刑務所に入れられ、愛する家族をも失い、
最終的には無差別の殺人にまで手をそめるに至る。
だが、イヴォンの変貌は激情に満ちた心理劇としてではなく、
むしろ極端に抑制された“行為の連鎖”としてだけ語られるだけだ。
彼が感情を露わにすることなどない。
むしろ我々が見せられるのは、扉の開閉、受け渡される札束、
無言で運ばれる荷物、刑務所の鉄格子、そういった行為や構造、
そして耳に刻まれる音だけである。
だからこそ、観客はその行間に、
むしろ「語られなかった苦悩」や「沈黙の絶望」を読みとることになる。
ブレッソンは人間の“外部”だけを映すことで、
“内面”の真実に触れるという逆説を成立させる稀有な作家なのだ。
ここにあるのは、単なるモラルの話などではない。
むしろこの作品は、現代社会における“罪と罰のメカニズム”そのものを
静かに暴き出してゆく。
偽札は単なる紙切れでありながら、人々を翻弄し、
道徳的判断を曇らせ、法と秩序という制度すらも操作していく点に、
このブレッソンの視線が冷徹に注がれる。
誰がどう悪かったのか? イヴォンか、写真店の店主か、
それとも偽証した写真店の店員か?
はたまた社会そのものなのか? 慈悲なき神そのものの存在なのか?
ブレッソンは決して容易に答えを与えはしない。
また明確な答えなどはなからないのである。
ここでは、悪は誰かの“心”に宿るものではなく、
むしろ“構造の中に生じてしまう必然として描き出されてゆく。
この構造的な無慈悲さを、
例えるなら、黒沢清の『キュア』に通じるような
“説明なき連鎖”の恐怖をもたらすものと見做してみよう。
『キュア』では催眠によって人が殺人者へと変貌していくが、
『ラルジャン』では貨幣と制度の連鎖によって、人が静かに壊れていくのだ。
両者に共通するのは、個人の意志や倫理では到底抗えきれない
“社会の奥に潜む装置”としての悪であり、
そこが現代的ミステリーの源とさえいっていい描き方をしている。
ここでブレッソンが描いたのは、神の沈黙のもとにおける倫理の不在である。
ベルイマン映画のように、個が神の不在に抗うのではなく、
ブレッソンは最初から神が語らない世界を前提にして、
そこに生まれる冷酷さをあくまで無表情に映しだす鏡のような世界を作り出す。
皮肉なことに、その無表情さの中にこそ、
神なき時代の人間の孤独と痛みが、もっとも鮮烈に立ち上がってくるのだ。
この映画の終盤で、刑務所から刑期を終え解放されると
イヴォンがたまたま街で見かけ、一回顔を見合わせた程度の婦人のあとをつけ
その世話になった献身的な婦人の一家を皆殺しにするという。
まるでテネブリズム絵画のように、
光とシルエットだけで、その恐ろしさを醸し出すブレッソンの演出の妙もあって
衝撃的な凶行に及んだ後のラストシーンには、ただ茫然とする。
いったい何が起こったのか? 誰にもわからない。
『私が神ならあなたを赦すわ』とまでいってくれた婦人もその犠牲になった。
懺悔、赦し、救済、そのいずれもが与えられることなく、
ただ出来事だけが静かに進行していく恐ろしさをまざまざと見せらつけられ、
その後、シーンは切り替わり
カフェに居合わせた警察官に、イヴァンの告白と逮捕と言う現実で唐突に終わる。
残酷な行為を犯した事件性もなく、それを見守る群衆まで、
どこまでも客観的に、単なる事象として描き出されるだけである。
だが、その無情なまでの簡潔さの中に、
奇妙な透明さと、ある種の崇高な美しさが宿っているのもまた事実である。
まさに、これぞブレッソンである。
ちなみに、原作のトルストイの短編『にせ利札』は二部構成になっていて
ブレッソンはその第一部だけを元に映画化している。
原作の二部では主人公ステパン(映画ではイヴァン)の悔悛と聖人ぶりが描かれ、
貨幣の寓話のはじまりとなったミーチャ少年(映画ではノルベール)と
その父親との関係修復までもが描かれて終わる。
いわば人間回帰の物語であったことを思えば、
ブレッソンが第一部のみで、あの唐突な幕切れで映画を終えたところに
ブレッソン哲学が真髄が滲んでいるともいえる。
『ラルジャン』は、ブレッソンの映画美学の集大成であり、
同時に彼のフィルモグラフィーにおける最後になった。
遺作でありながら、むしろ彼のスタイルはここで一層純化され、
極限まで削ぎ落とされた形で提示されていることに改めて驚く。
その意味でこの作品は、単なる終点ではなく、
彼の美学が辿り着いた“永遠の現在”として語り継がれてゆくべき映画である。
ブレッソンが仮に、さらに生きて映画を撮り続けていたとしても
けして安易に人間回帰を謳うような、
そんな映画作家にはなっていなかったように思える。
そこがブレッソンの凄みであり、映画の永遠性を保証するのだ。
これは貨幣という寓話を背負わされた人間性の悲劇なのか、
それとも、その寓話を弄んだ人間側の悲劇なのか?
はたまた、それを見つめる神の無慈悲への挑戦なのか?
沈黙の中で問いを発し、観客にその答えを委ねて終わるのだ。
われわれは各々思いを自らに問いなおすべく映画なのであり
そこにこそ、ブレッソンのシネマトグラフの詩情があるのだ。
Pink Floyd – Money
ブレッソンは基本音楽を使わない映画作家だったが、もし、この映画に、ピンク・フロイドの名盤『狂気』から、その名も「マネー」なんかを当てはめるとどなるだろう? あまりもずばりすぎて、面白くもなんともないが、こちらは明確に「金は諸悪の根源さ」と拝金主義へのブラックユーモアが歌われ、レジスターと小銭の効果音に、ベースのグルーブとエレピが重なりテンポを刻む7/4拍子で、コーラス部だけ4/4拍子になる、そんな面白い展開の曲だ。終盤に聞こえてくるダイアログは、ロジャー・ウォーターズがアビー・ロード・スタジオのスタッフや周囲の関係者たちにインタビューして録音した素材の一部で、「狂気」に取り憑かれるとは何か? 正気とは? といったテーマに対する即興の生の声を、曲間にちりばめた形で使っている。
“I don’t know, I was really drunk at the time…”
(「さあな、あのときは酔っぱらってたからよく覚えてねぇ…」)、とは、つまり、金とアルコールと狂気の三角形を連想させる上で、アルバム全体の「狂気」へのコンセプトの一部を暗示しているわけなんだね。







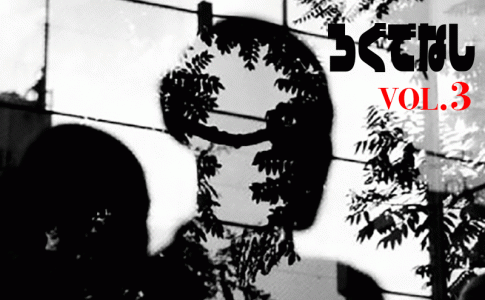



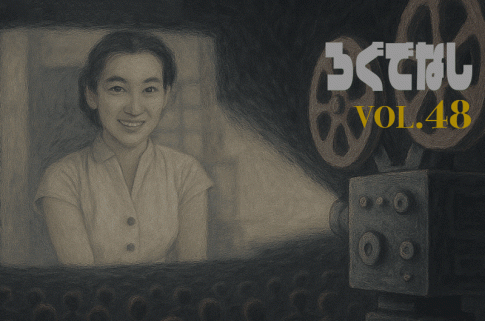

コメントを残す