キッズリターン トゥ フォーエヴァー
北野武という映画監督は、今の日本映画において
特別なポジションを担っていることは確かである。
出どころが異質であると同時に、内外での評価に随分隔たりが生じている、
そんな映画作家であるからかもしれない。
ここで北野武の『KIDS RETURN』について語る前に、
映画監督北野武への思いを語ろう。
正直なところ、武映画に関して、
手放しで好きだとはいえないところがある。
『その男、凶暴につき』で深作欣二の代役で監督デビューして以来
20本近くの映画を撮ってきて、今や押しも押されぬ映画作家であるのだが
その作品公開時期に多少ずれはあってもかれこれ逃さずには見てきたが
好きなもの、がっかりさせられるものもあるなかで、
一方的に評価を下すには少々気が重い。
というのも、かつて漫才ブームのなかで現れた
立て板に水のごとく、相棒の相槌すらもはねのけるほどの熱量で
ひとりで毒舌を吐きまくって、一世風靡したツービート、
そのビートたけしの栄光を見知っているものからすると
いつのまにやら、世界のキタノと賞賛されるまでに上り詰めたはいいが
ひとりのお笑い芸人の顔がどうしてもちらついてしまうのだ。
いっそうどこかで、映画に専心していてくれれば、と思ったものである。
要するに、TVでおなじみのたけしとしてのパブリックイメージが
純粋な評価の足かせにもなっている気がしているのである。
が、そこは所詮言い訳に過ぎない。
処女作『その男、凶暴につき』では、
すでに以後の武映画の萌芽がかいま見られたし
忘れがたい『あの夏、いちばん静かな海。』でのサイレントな美しさなど
当初繰り出された作品群には、その才能が新鮮に映ったものだ。
が、『アウトレイジ』あたりまでくると、エンターテイメント性が確立され
完全にこなれた映画作家としての威風が一人歩きし
かつての新鮮味よりは、飽和的な限界点のなようなものが見え隠れし
つくづく映画とは残酷なものだという思いにかられてしまうのだ。
はっきり言えば、二足のわらじで通用するほど
野暮な世界ではないということではないのか。
それは果たして映画監督北野武の限界なのか、
それとも、芸人ビートたけしとしての終焉なのか?
そこに突き当たってしまう。
とはいえ、人間北野武に強く魅力を感じるがゆえに
『大久保清』を始め『戦場のメリークリスマス』のヨノイ軍曹など、
俳優ビートたけしのあのたたずまいには常々惹きつけられてきたし
今こそ冷静に映画そのものをみつめなおさねばならないと思うのだ。
そんな北野武のフィルモグラフィーのなかで、
個人的に好きな一本を選べと言われると、
まず、6作目『KIDS RETURN』に行き着いてしまう。
このあたりの武の映画愛が、純粋に武カラーのような気がするからだ。
なによりも、当時バイク事故で生命の危機にさらされ、
そこから見事復活を遂げたたけしの真摯な生への思いが
ボクシングシーンを中心に、リアルにつきささってくる。
ふたりの落ちこぼれの高校生マサルとシンジの青春物語は
いまみても、映画としての瑞々しさをたずさえている。
自らのバックグラウンドである漫才的要素をふんだんに挟み込み
のちに映画そのものを推進してゆく暴力描写とをバランスよく混ぜ合わせ
人間そのものの生の息づかいを丁寧に描き込んでいる映画になっている。
『KIDS RETURN』を今、再評価するとすれば、
芸人的な遊びや小手先芸からは一歩引いた視線がぶれていないからである。
始まりと終わりに見る、マサルとシンジが二人乗りをする自転車シーンが
この映画の全てを物語っているのだが、
すべてが終わった後、再び出くわしたふたりが
「俺たちもう終わっちゃったのかな?」
「まだ始まっちゃいねぇよ」」と交わす流れで、
再び人生を踏み出しそうとする二人の未来は、
まさに当時の武自身の姿に重なる映画構造になっているのだと思う。
この映画が感傷に溺れず、やすっぽくないのは、
一人はヤクザ組織へ、もうひとりはボクシングという
肉体そのものを武器に怖い物知らずに知らぬ世界に飛び込んでゆく
その無軌道な若さがまぶしいからだ。
当人の経験も多分にいかされたボクシングを主題にした映画作りは
随分前から構想されていたというが
シーンそのものは実に本格的で、ごまかしはない。
しかし、あくまでもそこで描き出されるのは
権力や華やかさを求める人間の弱さと苦い汗である。
マサルが道を踏み外し、そのまま負のベクトルのままに
ヤクザ社会へと身を投じるのも、
シンジがボクシングを通じて、栄光と挫折を知るのも
結局のところは、武自身が経験した芸能社会での経験で裏返しでもあり、
組織そのものは、いずれもさしてかわりのない危うい世界、
幻の世界、という武流の冷徹な眼差しが射抜かれている。
学校という絶対的な組織からはみ出た二人が
次に所属し夢見た組織そのものにさえ、罠が有り欠陥はあるのだ。
それを身体にも、心にも痛みを分かち合ったふたりだけが踏み出せる次の一歩。
それこそが若者の特権であるといわんばかりに
もう一度自転車という究極のアナログな乗り物に乗り合わせ
新たに社会に踏み出そうとするそんな飾りのない姿に、心が動かされるのだ。
RETURN TO FOREVER:CHICK COREA
なんの捻りもないが、チック・コリアの永遠の名曲「RETURN TO FOREVER」を捧げよう。名義こそ、チック・コリアだが、これはRETURN TO FOREVERというバンドの演奏だ。ベースにスタンリー・クラーク、ドラムがアイアート・モレイラとボーカル、パーカッションがフローラ・プリムのブラジル出身の二人。以後メンバーは変遷しているが、
チックとスタンリーは変わらないが、個人的にはフローラ・プリムの声が入ったこれが一番好きだ。








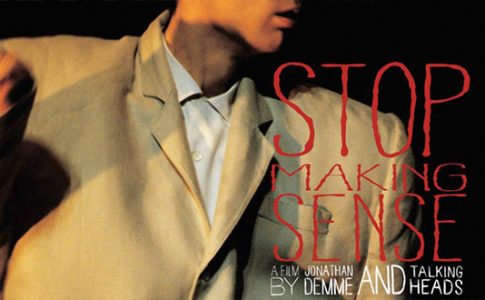




コメントを残す