薬ばやめっぺか、人間ばやめっぺか?
「覚醒剤やめますか? それとも人間やめますか?」
これは1980年代に実際放送されていた、
麻薬撲滅啓蒙CMのキャッチフレーズである。
「人間やめますか」の響きには、
それ相応のインパクトを感じ取ったのを覚えている。
人間はいくら強がったところで、
本能的に自分が人間だという最低限の境界線を越えることを恐れる。
要するに、覚醒剤とは、太宰治『人間失格』よりも
はるかに厳しい烙印をちらつかせなければいけないほどに
人に警鐘を鳴らさねばならないほどのもの、ということなのだ。
とはいえ、所詮、覚醒剤など他人事にすぎないと思う人間には
手を出すやつは文字通りクズ人間であり、
しったこっちゃない、というのが本音であろう。
なぜ、薬に手を出すかは人それぞれに事情はあるだろうが、
ハードな夜勤仕事などをこなすために手を出した
というような口実をしばし耳にする。
その時は目がランランとし、頭が実に冴えるらしい。
また、性の快楽をも増すのだという。
スポーツなどで薬物が禁止されているように、
肉体の限界を超えるためには効果があるのだろう。
だが、そんな安易な行動の見返りは凄まじい。
そこはやった人間でしかその恐ろしさはわからないところだが、
柳町光男の「さらば愛しき大地」での薬物依存の恐ろしさは
ヘビーかつリアルな描写の刻印として記憶から今なお離れない。
結論、覚醒剤は手を出したが最後である。
その薬物中毒の男山沢幸雄を熱演したのは根津甚八である。
茨城の鹿島という、かつてのどかで閉塞的な農村固有の空気間のなかで
家長制度の扱いに不満をもつ幸雄は覚醒剤におぼれてゆく。
ただでさえ兇状持ち、短気で、酒飲みで
身内にも容赦はなく当たり散らす性格。
子煩悩ではあるが、その子供を事故で失うという辺りで
人生はいよいよ深みにはまってゆく。
背中に子供二人の名を彫り込むはいいが、よそで愛人を作る。
そして自分より優遇される弟、および家そのものを恨みながら、
荒れ果ててゆく狂気が実にリアルで迫ってくるものがあった。
舞台はかつて「最後の未開の地」とされた鹿島臨海工業地帯をめぐって
高度成長期以降の変革ぶりがまさに話の核にあり、
しばし娯楽映画に多々登場した、おおらかな“トラックもの”とは
一線を画すハードな内容がリアル感たっぷりに描き出されているのだ。
が、なにも薬物恐ろしさやその啓蒙映画というわけでもなく、
また、男と女の不倫のもつれに特化した映画でもない。
地方固有の因習のなかで、主人公を含め、その土壌に宿る、
逃れられない運命共同体としての、むせるような空気感のなかで
その混乱と狂騒が見事に映りこんでいるありさまに息を呑む。
全編、茨城弁固有の土着性も手伝って、家のありかた、人と人との有りよう、
家族の絆の問題等が露わにクローズアップされている。
おそらく、これは当時の日本社会の縮図ともいえるのだろう。
絶望とともに、幸雄の眼差しの先には、
そんな茨城の豊かな青い稲穂とその稲穂を通り抜ける、
何人たりとも犯しえない、木々を揺らす美しい風が広がっている。
失われてゆく愛しき大地への思いと
薬物に犯され運命に飲み込まれてゆく男の無情感がそこはかとなく漂っている。
この映画が心底記憶に刻まれるのは、その対比の素晴らしさでもあり
農村から工業地帯へと生まれ変わるその過程のなかに
むき出しの愚かさや哀しみをともないながら
人間の営みそのものがくりかえされていた時代感覚なのだ、
そう認識させられるからかもしれない。
田んぼの中の農道をゆく葬式の行列、鶏をしめる、あるいは逃げ惑う養豚、
ちゃぶ台返し、廃バス利用の事務所、開発の土地成金とその恩恵の家etc
時代の鑑そのものの描写が次々に出てくる。
ちなみに、柳町光男は茨城県牛堀町出身であり、
リアルタイムで体験してきたその原風景の空気感を
どうにか映画に残したかったのだという。
昔を知る茨城県民なら、なおさら感慨深いものがあるに違いない。
まさに失われた昭和の風景の刻印が、この映画を圧倒的に支配しているのだ。
そのなかで、なんといっても自然の音がふんだんに効果を発揮し
場の臨場感を醸しだしているのは興味深い。
いみじくも、かつての成田空港開発をめぐる三里塚闘争の生の現場で
映画を支えてきたカメラマン田村正毅による
大地を愛おしむようなカメラワークが冴え、
実に印象的で素晴らしいショットが
ここでも映画を支えているのがお分かり頂けようか。
反面、主人公を襲う幻覚や幻聴の臨場感においては
まさしくサスペンスそのものの効果を生み出してゆく。
いたるところに幻覚、幻聴のシーンを挟みこみながら、
たとえば、ダンプ仲間の蟹江敬三扮する大尽の新築の家屋では、
ありもしない地震の影におびえ、雨戸を閉め
浴室の配管を通って弟に襲われる幻聴に
ひたすら排水溝にトントンと詰めものをする奇行をみせたり
クライマックスでは、順子のモノローグとともに
キッチンでジャガイモの皮を剥くおとを幻聴の音がリアルに誇張され、
幻聴として覚える幸雄をそのあとの唐突な殺意へと駆り立てる
見事な演出がなされている。
迫り来る運命に抗うことができないのはなにも幸雄だけではなく、
そんな男に惚れてしまった秋吉久美子演じる順子もまた同じである。
逆に、その運命の波に飲み込まれてゆく家や大地のたたずまいは
あたかも神のように、ただひたすらに不穏に受け止めるしかないのだ。
この映画のたたずまいそのものを終始支えているのはそれだ。
当時からそれ以後へと移りゆく変遷のなかで、
「さらば愛しき大地」を未だ色あせない傑作として記憶にとどめているのは、
何人も抗えぬ大地の重みそのものであり、また美しさなのだと。
The Velvet Underground : Heroin
ドラッグってなんだろう? 単なる逃避の誘惑か、それともインスピレーションの源か? かつてはアウトローな生き方にはドラッグが全て、なんていう間違ったイメージも一人歩きしていた時代もある。それによって、多くの有能なアーティストが溺れて、自分を見失っていったのは事実であるが、だからドラッグというものを賞賛する気もないし、かといって、頭ごなしにその生きざまを否定する気もない。ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのファーストアルバムに収録されたこの「ヘロイン」はまさにそのものずばりの曲だ。「おまえこそ俺の死そのもの・・・俺の女房、俺の人生」と歌われ、まさに曲調そのものがヘロインをやったような感じを疑似体験させる曲である。ルー・リードもまた、ドラッグに溺れたアーティストの一人だったが、同時に溺れゆく人間たちを冷静に見つめた時代の証人でもあった。残された作品は狂気にみちているが、今聴いてもかっこいい。











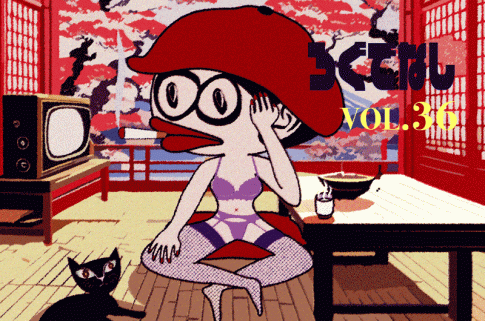

コメントを残す