日常を詩として捉えること、JJ 流幸せの捉え方
ジム・ジャームッシュとの付き合いはそれなりに長い。
80年代からミニシアター系ムービーとして席巻し始め
『ストレンジャー・パラダイス』『ダウン・バイロー』
『ミステリートレイン』と次々に、
ジャームッシュのオフビートな世界観にハマって以来、
ほぼすべてリアルタイムでその世界に浸ってきた。
とにかく、なぜだか気の合う友達のような感性に
ウマが合う作家だと勝手に思ってきた。
シリアスすぎず、ユーモアがあって
それでいて心にしっかりと刻まれる映画の手法。
それは新しくも古くもなく、どこにでもありそうでいて
実はどこにもない独特な空気感に包まれている
ジム・ジャームッシュ独特の個性である。
すでにベテランの域に達しながら
変わらないといえば当初から何も変わらない作家。
それが安心して見たくなる所以でもある。
中でも日常の延長上に物語が展開するスタイルが好きだ。
この『パターソン』と言う映画は
これまでのスタイルに即した、ジャームッシュらしい作品で、
特に新しいスタイルなんてどこにもない。
なのに、とても新鮮で愛くるしく心地よい。
晩年に向かうにつれ、
同じようなテーマを繰り返し、
円熟の極みとしての映画にこだわった
あの小津調の空気感にも通じる。
ただ、こちらもそれなりに歳をとって
ものの見方にも微妙な変化があり
そうしたこなれた見方、と言うのはあるのかもしれない。
ニュージャージー州パターソン市で
バスの運転手として働くパターソンの一週間が描かれている。
アダム・ドライバー演じる主人公パターソンは
愛する妻、愛犬、そして詩を書くことが日常の全てである。
そうした淡々とした基本的日常の中に
無上の幸せを滲ませる。
だから、事件らしい事件は何もない。
そう、この映画を観て、「ムッシュ」や「浴室」「カメラ」などで知られる
ベルギーの作家トゥーサンの小説を思い出した。
何気ない日常とおかしみ、その空気感は
ジャームッシュ映画にもどこか共通するものがあるかもしれない。
エミリー・ディキンソンを愛する少女に遭遇しようが
ラスト付近で、日本からやってきた永瀬正敏が
『ミステリートレイン』以来の27年の歳月を経ての
記念すべき再会として登場しようが、
それは別に事件と呼ぶようなものでもない。
詩は単に日常の一部だからだ。
あたかもラッパーたちが韻を踏むラップのように
生活のルーティンの中での一つの出来事にすぎない。
同じことを繰り返す中に生じる心地よさ。
それは美しい一編の詩のような日々を
生きていると言う特権的事実が
パターソンを、パターソンとしての時間を
うまく保守せしめるのだ。
こうした事態を映画として表現する技を
人はちょっとイージーに考えてしまうきらいがあるけれども
そんな芸当が誰にでも易々とできてしまうわけはない。
だからこそ、ジャームッシュの映画を観に
わざわざ映画館に足を運ぶ、そんな気がする。
パターソンの視線はすこぶる優しい。
そして、その見えている世界の向こう側に、
人が無意識のうちに求めている幸福の実態が見え隠れしている。
『パターソン』を見て以来、
僕自身、柄でもなく、一人で飲みに出かけることが増えた。
そこで得るかけがえのないものとは
言葉にすると陳腐になりがちなのだけれど
自分の時間をはっきりと認識することで
より他者の視線に触れることさえも心地よくなり、
日常のなかに心を許す空間なり場所が勝手に広がってゆく。
あえてそうした場に身を置く行為が
幸福を確認するためには、必須の体験のように思い始めているところだ。
もちろん、何かに承認されたいと言うような
諸々の欲求から、できるかぎりへだたることが前提だ。
そうすれば自ずと美しい詩の恩恵に預かることになる。
その中で人生の機知を学んでゆくパターソンのように
静かに、心の声に耳を傾けるゆとりが生まれ、
そうした生き方を幸せの総称して感じることができる気がしている。
ジャームッシュの映画体験そのものの価値は
まさにそんなところにあるのではなかろうか。
この『パターソン』の、何も起こらなさが素直に素敵だと思えた。
Emily Dickinson · David Sylvian
『パターソン』にはエミリー・ディキンソンを敬愛する可憐な少女が出てくる。このエミリー・ディキンソンという人は、アメリカ文学史上で最高の詩人と評されているほどの詩人だが、生前は全く無名のまま55歳で生涯をとじた人。そんな詩人についての曲がデヴィッド・シルヴィアンの「マナフォン」に収録されているのが「Emily Dickinson」。このアルバムは非常に難解ながらも、ディキンソンの詩的宇宙に呼応するかのように、グリッチノイズや幽かな不安定な電子音にまじって、シルヴィアンのささやくような、詩の朗読のような歌が美しい曲調となって展開されてゆく詩的なアルバムだ。










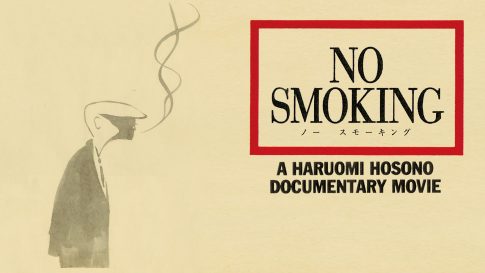


コメントを残す