死にガミガミいうことなかれ主義
子羊が第七の封印を解いた時
およそ半時間のあいだ天に静けさがあった
七つのラッパを持った七人の御使いが
ラッパを吹く用意をした。
『新約聖書のヨハネの黙示録』より
「アジャラカモクレン、テケレッツのパー」
古典落語「死神」で、
死神が病床の人間の枕元に座っていればご臨終
足元ならば、その題目を唱えさえすれば死神は姿をけし
延命が約束される。
一度は死んでもいいと考えた男が
医師を語ってひとつ金儲けをと言う誘惑の前に
結局は欲に押されて、最後は自ら寿命を縮めてしまう、
概ねそんな話である。
死神に一度憑かれてしまえば抗う方法などないのだ。
けれども、少々の延命なら交渉次第。
そこが物語として面白いところだ。
そんな話がベルイマンの『第七の封印』である。
中世は北欧、海岸に佇む死神、
そして十字軍遠征から戻ってきた騎士アントニウスと従者ヨンス。
待ち受けていたのは黒死病、いわばペストが蔓延する現実社会と
それを傍に見つめる死がある。
アントニウスは不気味な死神に、
言うなれば死刑宣告を受けることになる。
けれども、十字軍と言う不毛な巡礼の旅に疲れ
疑問しか湧かない男としては、命よりも気になることがある。
神がいるのか、いないのか、それだけが気がかりなのだ。
それを見届けた暁には、素直に死神の宣告を受け入れようと覚悟はある。
そのためにチェスを挑む。
少なくともチェスの対戦が終わらぬうちは
この世にとどまれると言うわけだ。
アントニウス役はベルイマン映画に不可欠のマックス・フォン・シドー。
これが記念すべきベルイマン映画の初演、文字通り出世作となった。
で、一度見たら忘れられないこの死神にはベント・エケロートだ。
黒マントに白塗りのこの強烈なる個性は
のちにシュワルツェネッガー主演の『ラスト・アクション・ヒーロー』や
マーク・ウェブ監督作『500日のサマー』といった映画への、
いわばインスピレーションの源泉となり
映画史においても重要な影響を及ぼし続ける問題作である。
出会う様々な人物たちを通して神の存在を問うアントニウス。
それは死に、神に、つまりは見えない存在に踊らされている
愚かな人間模様というわけである。
疫病で家族を失った少女は言葉すらも失っている。
『羅生門』を彷彿とさせる下落した悪党に堕落してしまった聖職者、
また、ジャンヌ・ダルクよろしく魔女狩りの生贄に処される女、
終始牧歌的で見えぬものが見える旅芸人ヨフとその一家、
不貞に走る妻と嘆く鍛冶屋・・・
不安の渦巻く中世の終末観、恐れおののく人々を
実に豊かにこれ見よがしに祝祭的に描き出してゆくこの映画は
いわゆる宗教映画でもなければ
難解な哲学的映画と言うわけでもない、
どこか眉唾の芸術映画である。
そのうち少女と旅芸人一家、鍛冶屋夫妻を従え
アントニウスは妻のいる城への旅を続け、
ついにはチェスに負ける。
すなわち、死神との約束の時が来る。
大鎌と砂時計を持った死神を先頭に、
死の舞踏を伴って丘を登ってゆく一行。
死は絶望ではない。
死はある意味、あらゆる苦しみからの救済でもあるのだ。
苦悩するアントニウスはかくして
不毛な問いから逃れうる唯一の解決方法、
死に迎えられるだけだ。
それを遠方より見届けるのが、旅芸人ヨフ。
この旅芸人一家こそ、
この映画の重要なキーワードになっているのがわかるシーンだ。
つまりは信仰を持たず、
ただ純朴に生きている男だけに見えるありのままの現実。
マリアさま、そして死神を一人見ることができるが、
彼の無邪気な人生になんら影響を及ぼさない。
可愛い妻と子供に囲まれただ幸せに暮らしている。
そう、気楽に生きようよ、肩の力を抜いて。
そんな楽観主義だけが終末を
ただ生き延びる手立てなのかもしれない。
そんな声が聞こえてくる。
確かに見ようによっては哲学的なテーマかもしれないが
それをベルイマンはどこか狡猾なる演出で
あざ笑うかのように死神というキャラクターを前面に押し出してきて
大衆を映像のマジックでじんわり高揚させてゆく。
モノクロームに映える黒マント、白塗りの死神で
時折ぞっとするぐらい怖いシーンもあるが
反対にどこかユーモアラスで
人間的な表情をものぞかせるこの面白さ。
そう、この死神はどこか道化師のようである。
やはりベルイマンは凄いのだ。
しかし、同時にこれはまごうかたなき映画であると実感させられる。
というのも、死神を演じたベント・エケロートの方が
すでに51歳の若さで他界しているが、
一方のマックス・フォン・シドーはといえば
昨年三月に91歳の大往生で、荼毘に付されその偉大な生涯を閉じた。
先にチェスに負けたのは死神を演じた方であったのだ。
マックス・フォン・シドーはチェスには負けたが
いうまでもなく、輝かしい映画人生に勝利した俳優だったのである。





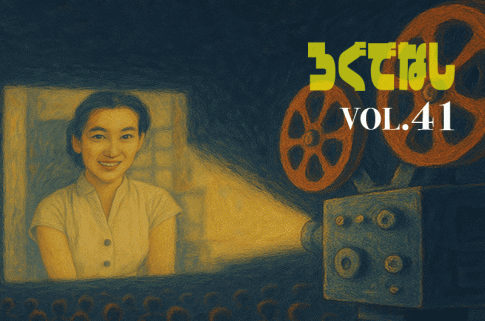







コメントを残す