鉄の女はサッチャーでもサッチーでもなく、ユペール様である
イザベル・ユペールを最初に観たのは
個人的に、最高にして彼女の代表作だと信じて疑わない
ジャック・ドワイヨンの『女の復讐』だったと思う。
この映画におけるユペールの女としての恐ろしさは、
今なおも脳裏から離れることがない。
交通事故で死んだ男の妻セシル役を演じたユペールは、
ベアトリス・ダル演じる元愛人をとことん追いつめてゆく。
その追いつめ方の凄まじさといったら!
思わず映画ということを忘れてしまうほど
鬼気迫るものがあった。
改めて女というものの怨讐劇に震撼させられる思いがしたものだった。
もちろん、映画の出来も素晴らしかったし、
なんといってもイザベル・ユペールという女優の実力を
まざまざと堪能できる作品として、
『女の復讐』はもっと評価されてもいい映画だと思う。
そんなイザベル・ユペールはいまやベテランの域に達しており、
ジャンヌ・モローなきフランス映画界の中で、
ドゥヌーブに次ぐ、NO2の座にいる女優ではないかと思う。
すでに、かなりの実力派として認知され、
このところの活躍ぶりはフランス映画に留まらず、
目覚ましいものがある。
やはり、本物の映画作家や映画好きたちに支持され、
引っ張りだこになるわけである。
その中で、何よりまずこの『エル』を語らずにはいられない。
これはもう、何といっていいのか、
言葉にするにもいろいろ大変な映画だが、
中身はかなり面白い作品であったのは間違いない。
レイプ犯と、殺人鬼を父に持つ女ミシェルとの間に起こる、
ブラックジョークのような日常の連続が、
オトナの演出で描き出されるストーリーで、
何度もいうが、イザベル・ユペールって女優は素晴らしい、
いやどうにも恐ろしいと言い換えなきゃいけないほどの演技を
ここでも期待通り見せてくれる。
この女優がもつ格調の高さでなければ、
いわゆる単なる“変態映画”で終わってしまうところを、
力技でもって傑作の域に押し上げてしまったといえよう。
監督はオランダ人ポール・ヴァーホーヴェン。
自分には聞き慣れない名前だったが、
こんな革新的な映画をよくも撮ったと思う。
レイプという、なんとも重苦しい社会的なテーマが
中心に据えられるのだが、この映画の素晴らしさは、
レイプによる被害者を倫理的に被害者然として描かず、
父親がかつて世間を震撼させた殺人鬼である、
という被害者側のバックグラウンドを巧みに組み入れながら、
サイコスリルな展開で新たな視点を持ち込んだ斬新さにある。
イザベル・ユペールの演技が申し分ないのはいうまでもないが、
それに比べて情けない男たちとの間にくりひろげられる奔放な姿が、
決してストーリーとしての品を落とす事なく、
サスペンス調を伴って展開されてゆく。
最後にミシェルがとる、レイプ犯に対する反応が
物議をかもしたというのだが、映画を見終わると、
それはそれでありかも、とも思ったりした。
その意味で、アメリカではなく、
舞台をフランスを舞台に選んだのは正解だったと思う。
保守的なアメリカのモラルよりは、
個人の考えが尊重されるフランスならではの倫理観が、
ここではうまく作用した映画になっている。
覆面をしたレイプ犯がヒロインを襲うという
ショッキングなオープニングのあと、
なぜか寿司を注文し平然と息子と夕食をするなんてのは、
いったいどういう神経なんだろうか。
彼女はゲーム会社の経営者で、最初はその社内に犯人がいるのでは、
と思わせるミステリーな要素も面白く、
とにかく周りの男達が60を越えて
なおも魅力的なひとりの女性に、翻弄され群がるのだが、
それを涼しげに交わし適度に受け入れながら、
男のようにサバサバ颯爽と振る舞う姿に憧れる社員がいる、
というのはなんとなくわかる気がする。
そのヒロインを狙うのが、まさかの隣人である。
その事実を知っていながら、交通事故の際に助けを求めたり、
逆に自ら誘惑するようなそぶりをみせたり、
家にまで出かけて息子と晩餐の席についたり、
その後も男の挑発にのってみせる奔放さというのか、
このヒロインの自由な立ち振る舞いを、
一般の女性からすれば、
なぜレイプという屈辱的な仕打ちをした相手に対して
あのような対応がとれるのか、疑問だったのではないだろうか。
たしかに、この映画におけるミシェルの強さには、
ある種の違和感があるのかもしれない。
それでいながら、あんな風にすべてにおいて、
凛として筋の通った強さを発揮できる女性像には
敬意のようなものを感じてしまう。
それにしても、奔放すぎる。
ちょっと変という声も理解できないわけではない。
ミシェルのような女性の行動を理解するのは簡単ではない。
また仮にこうした女性がいたとしても、
日常を生きてゆくのは別の意味で
大変なことなんじゃないかと思わせるほど、
常識からかけ離れてはいるのだ。
まさに最強の鉄の女像がここにある。
ただ、この映画のベースには、ヒロインの背景には、
幼少時からその父親の過ちゆえのトラウマを
引きずっているわけだから、
あながち、ああした性質の基盤を考慮する余地はある。
だから、単にレイプという事実に対する、
あれほどまで冷静沈着に向き合える鉄の意思に、
妙に納得させる伏線がきっちりと敷かれている演出の見事さに、
感服させられるのだ。
それにしても、この映画を見る限り、
『ロボ・コップ』や『氷の微笑』で知られる
ポール・ヴァーホーヴェンがオランダ人で、
ハリウッドに活躍の場を求めるタイプの監督ではない気がする。
案の定、アメリカからヨーロッパに舞台を移し、
イザベル・ユペールという最強の女優を得て撮り得た本作で、
ようやく真骨頂を発揮したということなのだろう。
とにもかくにも挑発的かつスリリングな面白い映画だった。
そしてそのポール・ヴァーホーヴェン自身の素晴らしい言葉を引用して終わろう。
僕は“いいアート”とは、時に心をかき乱すようなものだと思うし、そういうものであるべきだ。それは観る者を動揺させ、怒らせなくてはいけない。確かにアートは“美”だが、“美”だけであるべきではない。矛盾があり、人々を動揺させ、彼らに違う考えをさせるものであるべきだ。彼らを不安にすべきだ。僕はいいアートは挑発的で、大胆で、ちょっと平手打ちのようなものであるべきだと思う。
まさに、『エル』は平手打ちを何発食らったかわからないような映画だった。
そう、イザベル・ユペールという女優は、
決して、自ら暴力的に振る舞うような野蛮さはないのだが、
言葉や、冷徹な態度でもって、
平手打ち以上の仕打ちで相手に決定的なダメージを与えることのできる、
そんな女優なのである。
EGO-WRAPPIN’:サイコアナルシス
エゴ・ラッピンの曲の中でもパンチの効いたナンバーといえば「サイコアナルシス」。はっきり言って意味を求めるのはナンセンス。精神分析のメカニズムを歌にするなんてことは、おそらく誰にもできない芸当だけど、中納良恵の歌はそんな小難しいことを吹っ飛ばすだけのアッパなーパワーとエネルギーに満ちていて、圧倒される。この半端ない高揚感だけがサイコに抗えるのかもしれない。




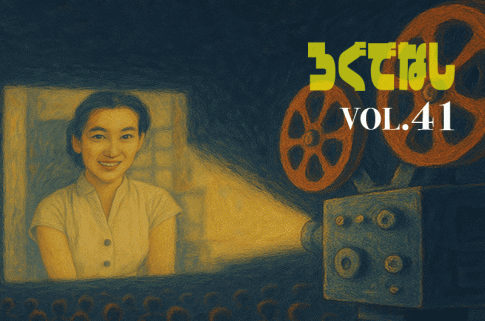



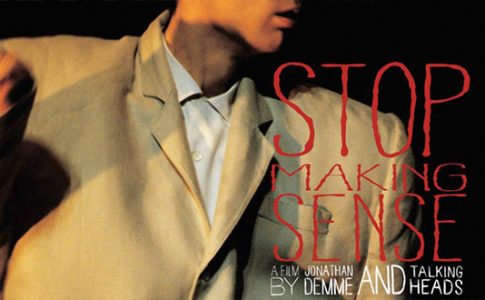




コメントを残す