いじめられっ子、世にはばかることもなく・・・
いうまでもないことだが、スティーブン・キングは実に偉大な作家だ。
モダンホラーというジャンルにおいての地位を確立し、
その原作を元にした映画化があとを絶たないことからも、
映画界においても貢献度というものは実に計り知れないものがあり、
また、一定の水準以上のクオリティを誇っている作品が多いのも、
そのことを証明している一端だといえるのかもしれない。
もっとも、自分は原作の熱心な読者でもなく、
あくまでも映画化されたごく一部のスティーブン・キング作品のファン、
というだけのことであるが、
その第一歩が全てデ・パルマによる『キャリー』に始まっており
記念すべき、この第一章について、語らぬわけにはいかない。
いじめという陰湿な行為、気運が、
時代とともに薄らいでいるとは到底思えないが、
すくなくとも、世間の受け止め方、感じ方には
その時代時代で違いはあるはずだ。
(少なくとも自分が知っている)昔は、
体罰をふくめ、いじめは日常茶飯事に身近にあったし
なにか特別な事件でも起きない限り、表だって取り上げられはしなかった。
言うなれば、泣き寝入りの時代でもある。
個人的には被害者も加害者も
どちら側の立場の体験も持ち合わせているにはいるのだが
(なんならそのことを回想することもできるが)
そんなことはここではどうでもよいことであり
それこそ、ひたすら己が強くなるしかなかったと、
今思えば、そう考えていたのは間違いないのであった。
なにかしら、卓越した強い力をもつことは
いじめからの脱出の第一歩である、今でもそう思う。
要するに、何かしら自分を大きく見せる必要がある。
この際、他力本願は捨てるべきである。
とにかく、“力”をつけるしかないのである。
それは武力でも、知能でもなんだって構わない。
必要なのは他者よりもすこしでも上から臨める何か、である。
それによる、自信しかないのだ。
なんなら芸が身を助ける、などということがあり得るのかもしれない。
映画『キャリー』における、いじめられっ子キャリーは
サイコネシスという強力な武器を、隠し持っている。
いや、こういった方が正しいのであろうか?
つまり、そうした力が発揮されるということは、
彼女が不幸の渦中にあり、
まさに反意識として現象があらわれるのだと。
でなければ、彼女は単に悪として忌み嫌われ
破壊、支配を目的とする異星人と何ら代わりがなくなってしまう。
(原作では、街そのものを壊滅状態にさせてしまうのだから・・・)
彼女の境遇は、その家庭環境に根ざしているのが、
いきなり映画の冒頭シーン、女学生たちの着替えシーンで露呈される。
つまり、高校生にもなって
女としての通過儀礼たる初潮を知らなかったことでいじめを受け、
その歪んだ成長過程っぷりが想起されるのだ。
すでに、ここで太ももを伝う血が、あのラストへと流れ行く、
文字通りの惨劇への導線として、
実に驚くほど巧妙かつスリリングに描かれている。
バックで使われる例の金属的な音は
あのヒッチコック『サイコ』へのオマージュというべき
バーナード・ハーマンによる音のサンプリングなのか
そのものズバリとして使用され、サスペンス効果を生んでいる。
嫌が応にも、あの有名なシャワーシーンの、
あの恐ろしい殺戮を思い起こしてしまうのだ。
母一人娘ひとりの家庭で、母親は
妄信的、狂信的なキリスト原理主義者であり
そのことが、キャリーを残酷にいじめの対象へと駆り立てる
元凶にもなっているのは明らかだが、
クライマックスのオチが、そうした日常で育まれ
まさにホラー要素として展開する様は、実に王道である。
家庭でも、学校でも、彼女は救いがなくひたすら追い詰められていくのだ。
しかし、ここまでくると、
なんだか思いもよらない可笑しみのような感情すらわき起こってくるではないか。
とりわけ、ブタの血を頭から浴びた屈辱でのキャリーの怒りは
大映の『大魔神』のそれのように手がつけられず、
見方によれば吉本新喜劇やドリフの稚気、暴徒のそれさえも想起させるものだ。
自分を心配して世話を焼いてくれた担任教師にさえも
キャリーは怒りの対象として、矛先を向けてしまう。
映画では、担任教師および、他の生徒の哄笑が
マルチ映像で展開されるが、これらはキャリーの妄想に過ぎない。
が、時すでに遅し。
キャリーの忿怒は収まる事を知らず、瞬く間に分別を超えるのである。
考えて見るがいい、日本の学園ドラマを引率してきた数々の名物熱血教師達、
村野武範であるとか、中村雅俊や武田鉄矢ような人が、
このような惨劇の犠牲者になるだなどと一体誰が想像できようか。
熱弁をふるって、学生たちを勇気づけ、涙まで誘った後に、
一転、逆襲の一撃を食らって泡を吹くだなどという展開では、
きっとお茶の間はドン引きだろう。
パーティー会場はもはや、手のつけられない事態へと発展するが、
その恐るべきパワーを駆使するキャリーの
恐ろしく見開かれた目力には、
かつて、あの岡本太郎の究極のパフォーマンスを彷彿とさせはしないだろうか・・・
そして究極のクライマックで、元凶たる母親が
娘を自らの手で決着をつけようとする暴挙に出たおりに、
逆に、奇術師のごとく、超能力で刃物の応酬で退けると、
そのまま、自らのパワーで、丸ごと自宅を解体してしまう。
この辺りはもう、スティーブン・キングというより
デ・パルマの感性、オリジナリティに喝采を贈るしかない。
そして・・・
あとは己の目で確かめるしかない、究極の夢オチが待っているというわけだ。
とにもかくに、凡百のホラーでは味わえない、
スリルと興奮が待ち構えた傑作であることは間違いない。
さて、最後にキャリーを演じたシシー・スペイセクに触れぬわけにはいかない。
この映画を見たものには、忘れがたいほどの強烈な個性を放っている。
初潮をも知らぬ内気な高校生役を演じたが
この時はすでに二十六才、担任コリンズを演じたベティ・バックリーとは
わずか二才しか違わなかったというから
まさに、体当たりの演技、ハマリ役だったのだろう。
随所に本人のこだわり、演技への意志を覗かせて
いじめられっ子の溜飲を下げる、
怪物キャリーを演じたこの女優の超個性っぷりこそがホラーなのだから。
バビル二世 エンディングテーマ
映画で怪物キャリーが見せた超能力、そんなテーマを元にした楽曲を探すのは一苦労である。そんなとき、このアニメのことが頭をよぎった。原作は「鉄人28号」で有名な横山光輝による漫画「バビル二世」である。5000年前に地球にやってきた宇宙人・バビルの遠い子孫である山野浩一少年が、三つのしもべ、ロデム、ロプロス、ポセイドンとともに、世界を支配しようとする悪の帝王ヨミに立ち向かう、そんなアニメだ。昭和世代の人間にとっては、感慨深いものがある。とりわけアニメソングといっても、ばかにできない思いがあり、バビル2世のOPはもちろん、エンディングテーマも、その一曲だ。アニメのストーリーは思い出せなくとも、歌はなぜだか記憶に残っている。おなじ、サイコキネシスを使うといっても、バビル2世とキャリーでは、状況がまったく違う。キャリーの怒りはあくまでも、個人的なコンプレックスに対する裏返しであり、いうなれば、内的パワーの高まりの発露である。ともあれ、超能力を駆使するという共通点によって、ここにふたつが結びついたのは.実に興味深い帰結に思えた。悪を倒すには、並半端な力では対抗できない。その意味では、超能力というのは、いじめられっ子にとってのひとつの壮大なロマンなのだろう。










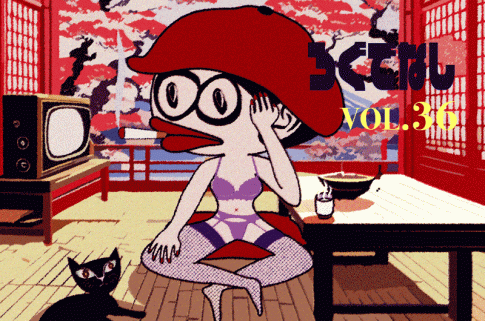


コメントを残す