はじめてリュミエール兄弟の“動く画面”をみて、すなわちスクリーンの汽車を前に逃げまどった人々は圧倒的にただしかったとのだと、今なら堂々そう言える。というのも、だれもが作りごとには思えない映画というものがあるし、われわれはいつだってあの光の帯のなかの住人だと簡単に思いこんでしまう、実にこまった人間なのであるわけだから・・・映画はほんの数時間だけなら、無茶を許してくれるばかりでなく、我々に無茶を強いたりするわけだから、本当は怖く影響力の強いものなのだ・・・同時に、惹かれてしまう、寄りそってしまう。まさに威風堂々理想の父のごとくであるばかりでなく、ときに観音のごときやさしさでこちらの気分をなぐさめてくれる不思議な作用をもたらすものである。あるときには、恋人にさえなってくれる、つまり四六時中考えていたい場面や登場人物というものさえある。まあ、そんなこんなのくだりはこの際どうでもいいが、映画とは? と実直に思いあぐねてみれば、コクトーがいったように「詩人たちの手にある危険ですごい武器」ということに異論はない。鈴木清順がのたまう「スペクタクル」そのものでもある。けれども、それこそが芸術と娯楽の区別が・・・などと、そんなこたあしっちゃあいない。映画は所詮映画なのである。自分が映画というものに魅了されてきて、少なくとも、映画とは何か、を考えはじめて、そう改めて思い直したまでである。
とはいえ、それは、あきらかに映画=人生だということに他ならない。それがたとえ作り物であってもだ。むろん、表現や芸術も多かれ少なかれそういうものだと思っているけれど、映画には多かれ少なかれ観て楽しむという側面を意識するきらいがある。つまり観客がいてはじめて成立するという考えである。哲学的で、難解、芸術的なものが優れているということでは、まったくない。反対に、面白くて、楽しめて、これぞエンターテイメントというものが優れているわけでもない。そこには明確な主体=作り手の意図がある。その上に、映画というものは、ひとつの社会を形成している。組織化されたスタッフがあり、不特定多数の観るひとがいる。自分を取り巻くあらゆるものを意識せずには成立しえないものだ。
こうした前提を考えたとき、映画というものが少し巨大で複雑な構造をもった「ハイブリッドな生き物=怪物」に思えてくる。生誕百年をすでにこえた現在、映画は時代を明確に写し出しながら、未来へとその生きた手をのばしはじめている。この生き物を捕らえることは、各自が人生を考えることに等しい。時代の空気を吸い込みながら、映画は変貌しつづけているのだから。いま、映画はすでに百歳を超え未来永劫を生き延びようとしている。画面に映りこんだ列車を観て逃げ出す観客など、どこにもいない。が、あまりにも実直に現実を見据え、映画に投影した人生を見せられた観客が、そっぽをむくことは多いにあることである。こんなの映画じゃないよ、わけがわからない、カネを返せ……と観客は堂々と映画を批判できうるのだ。それでも、我々が映画に魅せられることには変わりがないのである。
いや、むしろ、こうした一様でない表現のありかたこそ、=人生そのものである。では、何が魅力的で、何が映画へと熱狂させうるのだろう? 所詮、これは学問ではない。個人の嗜好のもとに、映画は語られればよいのだ。偏愛しうる映画について、語るその主体の偏愛的な視線をもって、映画というものをただ素直に捉えること。できることは、ただそれだけでよろしいのではないかと。
映画について考えることは作品を創ることよりも、批評というレベルはとりあえずおいておくとしても、まだ容易なことにちがいない。もっとも、破天荒さならいくども頓挫し公開に至ったレオス・カラックスの「ポンヌフの恋人達」や、夢かなわずも後世に多大な影響を及ぼしたホドロフスキーの「DUNE」。あるいは、約三十年もの年月をへて、世直しならぬ配給直しで名誉を回復したウイリアム・フリードキンの「恐怖の報酬」など、映画史には問題作が散見している。ひねくれものならカウリスマキをそう簡単には越えられないだろうし、才能だけならオーソン・ウエルズにかなわないのだし、ユーモアにおいてチャップリンやキートン、ジャック・タチに対抗しうるなんて無理だし、魂の領域においてベルイマンの深さには竦むのだろうし、愛においてはトリュフォーのそれにかなうべくもない。革命といえばゴダ-ルにはあたまがあがらないかもしれないし、洞察力なら、ルノワールにどうあがいたって劣ってしまうのだし、高貴さならヴィスコンティには太刀打ちできないし、センスということならフランソワ・オゾンには口がふさがらない。観察眼という視点ならフレデリック・ワイズマンに及ぶものはなく、厳格さでいうなら溝口には決して及ばない。いやはや、この世界の達人たちをしのぐことは口で語るほど、容易ではない。ならば、いまはなき淀川センセイのあしもとにもお及ばないながらも、視線の「愛」、対象への「愛」をもってそれを唯一のルールとしよう。
僕を知ってもらうためにランダムに選ぶ10本
- 『セリーヌとジュリーは舟でゆく』ジャック・リヴェット
- 『パリ、テキサス』ヴィム・ヴェンダース
- 『ミツバツのささやき』ヴィクトル・エリセ
- 『カビリアの夜』フェディリコ・フェリーニ
- 『悪太郎』鈴木清順
- 『めし』成瀬巳喜男
- 『雨月物語』溝口健二
- 『動くな、死ね、甦れ』ヴィタリー・カネフスキー
- 『ラ・パロマ』ダニエル・シュミット
- 『第七の封印』イングマール・ベルイマン

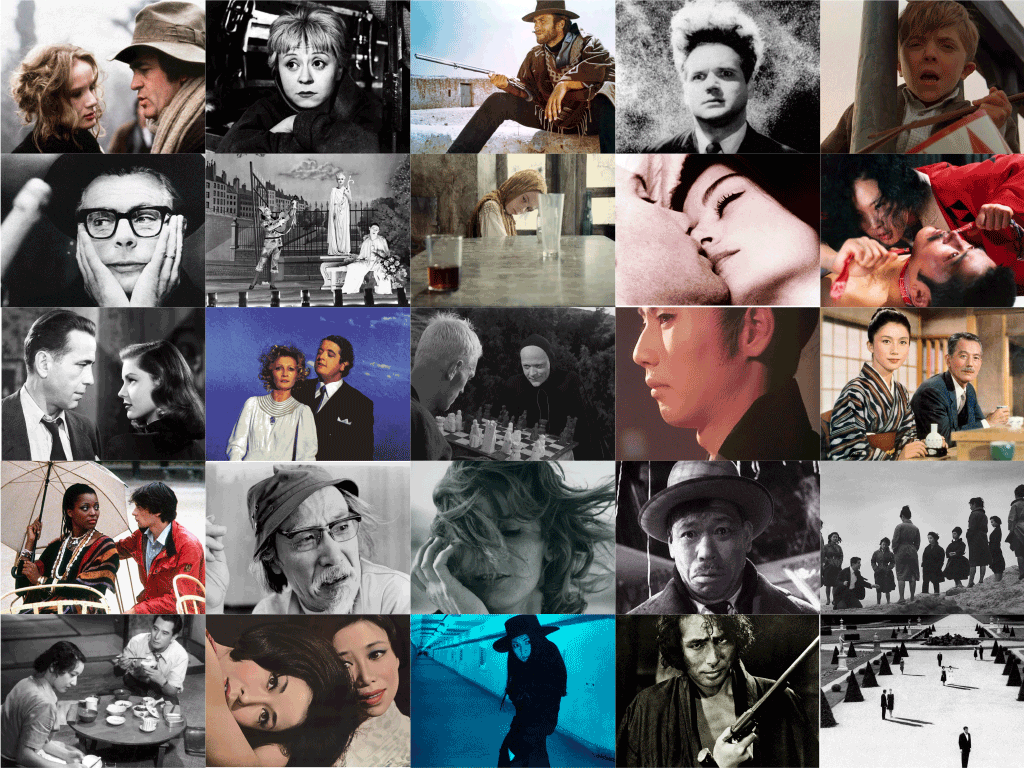











コメントを残す