地上で生きるためには流行を追わねばならぬ。が、心はもはやそれには従わぬ。
『大股びらき』ジャン・コクトー
目新しい文学にとんと触れていないし、決して熱心な読書家というわけでもない。手元の書架も整理してしまった今となって、活字を語るにも遠い記憶をたどるしかない。かつて、活字なくして生きていけぬ、という時期があった。こそこそ読むにも時間とゆとりあってこそ。活字にも人間が宿りまするな、その文体、コトバとコトバの行間にある思い。ひとえに想像力なければ、ただの目の運動、脳への適度な刺激、いわゆるボケ対策いうやつでっしゃろか。活字に疲れたら、そんなとき絵が見られれば、というだけでなんて素敵なことでっしゃろか。そこから活字をくみとるもまた文学とちゃいますやろか。コトバの限界をうめる無垢の描画に、にやりとしたり、ひとりごちてぼぅっとなり、ときにはじいんとしてみたり、はっとなって、おやまあ! 興奮することも少なくありませんねえ。色、形、そりゃあ楽しいなあ。でも、ほんとうは、自分のココロのなかがこうした風景でいつもいっぱい溢れているような、そんな自分でいたいなあ、それだけですねん。文学や詩、そして雑誌でも画集でもなんでもいいけど、ココロを満たす滋養を眼球から取り込むという遊びなんです。そのための本はなくてはならないものになってしまいましたねぇ。
僕が好きな書物 VOL.1
砂の女/安部公房
カフカになく安部氏にあるもの、それはなんだろうと考えることがあります。しいていえば決して括弧でくくりえない真の官能性、まさしく砂のようにざらざらした肌触りのエロスということかもしれない。前者が鳥なら、後者は爬虫類的な視線を結晶化しうる作家なんじゃないかと思う。ある種の高みからとある種の近接的な視線文学の差異・・・あののめり込ませるような、あるいはたえず微妙に流動しうる物質にからみ合う男と女、人間性の根源を読ませる術において、安部氏の文体構造は、砂に負けずおとらぬ狡猾な手練に長けているのだと思う。勅使河原宏の映画化によりヴィジュアル性が再現され、自分のなかで砂の女=岸田今日子のイメージがすっかりしっくりできあがってしまったが、文字で読む不条理文学と言うのもまた格別な味。
エロ事師たち/野坂昭如
町田康を遡ること二十数年。エロ事の諸々をいかにも巧みなオオサカ弁での繰り言の醍醐味、神戸に生きた先人野坂昭如の当時のパワーは絶大。ブルーフィルム扱うすぶやんを中心に描かれた世界観は独特で、事師の世界描かしたらこのひとの右にでるものおらずってな、匂いたつようなコトバの情感みごとな作品、いやあ、野坂節の原点ここにありか。これを読むとつまらぬエロがいかにはびこっているかがよおわかるってもの。はまりますよ。で、イマムラの映画化にはちょっと異議あり。やっぱりこれって文学でこそ。だれぞ、これを見事映像化できるキャラはおらんのやろか?
死の病い・アガタ/マルグリット・デュラス 小林康夫訳 朝日出版社ポストモダン叢書
「それに侵されたひとは自分が、それを、つまり死を持ち搬んでいるのだということを知らないから、それからまた、死に先立つどんな生もなしに、つまりどんな生を死ぬというどんな意識もないままに死んでいるようなものだからね。」『死の病い』より
見つめながらも沈黙している読み手は、このデュラスのテクストを読む快楽、それはテキストを追う、あるいは追われる快楽を享受しているのだろうか。同時にそれはある種の苦しみであるかもしれない。透明な汗、動かない肌、苦痛と快楽の背中合わせの無表情がある。生きていることのファントムとしての個体が、あたかも自分の影のように追ってくる。そう、言葉もまたしかり、それに追随して行きつく果てを、それは知っているのかもしれない、すでにかようなまでに侵されてしまっているのだから。
耳ラッパ―幻の聖杯物語 レオノーラ・カリントン 野中 雅代 (訳)
絵を描くのも文学を綴るのは手ではない。下界の魂だ。そして野暮な文学批評は避けよう。マックス・エルンストのミューズだった画家レオノーラ・カリントンの黒いユーモアに乾杯。耳ラッパ耳に当て99歳のウルトラおばあちゃんマリオンは、キュートネスポエジーを持ち合わせた暗闇のファンタジーを生きるダーク・アリスなのだ。そこはユートピアであると同時に、病んだ地球への警鐘とでもいうのか、アイロニーがちりばめられている。もっとも、お説教などではなく、魔術をもってして、あのカリントンの絵の世界のごとく。最近再発されたんですねえ・・・・これを矢川澄子訳で読んでみたかったなあ。
カフカ短篇集 フランツ・カフカ 池内紀 (訳)(岩波文庫)
カフカといえば「変身」や「審判」もいいけれども、やっぱり短編がよろしい。もっとも好きなのは「父の気がかり」というやつでその主人公オドラデクは人間じゃないちょっとみると平べたい星形の糸巻きのようなやつだ
そうだ。それって、どんなやつなの? それだけじゃほとんどわからないけれども、その愛おしさはなるほど伝わってくるのだから不思議だ。カフカといえば池内氏の訳で読みたい。そうインプットしはじめたのはこの短編集がじつにカフカらしいものでしっくりときたから。「掟の門」や「橋」といった寓話も好きですねぇ。寓話といえば、「カフカ寓話集」があります。もうひとつ大好きな短編「断食芸人」を収録してくれてます、あわせてカフカはやっぱり面白いとあらためて思います。文庫という形での短編として、イチオシ。ちょうどKが仕事のかたわらに小説を書きなぐったように、通勤の行き帰りにこれを忍ばせてこそ、カフカも浮かばれますかな。
女生徒 太宰治 (角川文庫)
実をいうと高校生のころ一番読んだ作家がダザイとヘッセでした。逆もまた真なり、彼こそは人生を真面目に考えるがゆえにその反対にいく人間だったのでしょうね。そんな気が伝わってきます。とても日本的で、とても東北的で、つまりは独特の閉鎖気質、ナルシズム。いまでいう引き蘢りやオタク人間たちの心情とオーヴァ-ラップするという意味で、まずは「人間失格」がありますが、太宰という作家には、女心を理解するためのキーワードがいろいろあって勉強になります。もっともそれを実践した覚えなどありませんが。そして、これ、自分のなかにある女性性と出会う作家なのかもしれません。「女生徒」というのはそういう一冊でした。
「ヘンリー・ダーガー 非現実の王国で」ジョン・マクレガー 著 小出由紀子訳 作品社
これを文学と呼んでいいか悪いかは別としても、非常にショックを受けた一冊である。ヴィヴィアン・ガールズといっても世のパンク娘のことではなくして妄想つづりものの中の登場人物たちのこと。死後発掘された世界のお宝ダ-ガ-おじさんの、絵の図版39点と小説の部分訳からなるこの本は、単なる画集でもなければ小説集でもない、60年にもおよぶひとりの孤独な妄想絵巻である。ヘンリ-・ダーガ-そのひとにふれうる格好の出版物であるが、本人のぞまずして、世にでまわってしまう不条理もさることながら、中で描かれるちんちん娘たちの世界、凄まじきバイオレントでイノセントなカオスは衝撃的だ。さあて、生けるヘンリ-たちにも愛の手を。
クヌルプ/ヘルマン・ヘッセ 高橋健二訳
ヘッセは10代の時によく読んだ。ここではアウトサイダーをはみだしもの、ではなくただ不器用な人間としてとらえようと思う。別に、わざわざ人生からドロップアウトしたいわけじゃない。人生に誠実であろうとするあまり身動きがとれなくなるタイプの人間は、常々シンプルなポジションへと立ち返らせるところの道標を求めている。ヘッセの文学はそうした人間たちになんらかのポジションを与えてくれる気がした。何ごともまず探求、求めよ、そこに場所がある。すれば道はおのずと開ける、いや開けなくともいいんだよ、ありのままでありさえすれば。まあずいぶん身勝手な解釈をしていたものだ。でも、自分にとってヘッセ文学はどれもそのような道標であったことは間違いない。今はちょっと違うけれど。まあ、ちょっと冷静にみれば、人間そのものにそなわっている善の部分をそれほど高尚なものとおもわず、文学という俗の部分でうまくとらえ直すっていうか、自分はそこでまたなんとなくくすぐられるのかもしれない。いつかまたヘッセの文学にもどりたいと思って生きてきたが、今はどこかでそんなヘッセのエッセンスがうまく人生に溶け込んでいる気がしている。高橋健二訳が素晴らしい、とは清志郎もいっていったな。
ジャズカントリー/ナット・ヘントフ 木島始訳
ヘッセは10代の時によく読んだ。ここではアウトサイダーをはみだしもの、ではなくただ不器用な人間としてとらえようと思う。別に、わざわざ人生からドロップアウトしたいわけじゃない。人生に誠実であろうとするあまり身動きがとれなくなるタイプの人間は、常々シンプルなポジションへと立ち返らせるところの道標を求めている。ヘッセの文学はそうした人間たちになんらかのポジションを与えてくれる気がした。何ごともまず探求、求めよ、そこに場所がある。すれば道はおのずと開ける、いや開けなくともいいんだよ、ありのままでありさえすれば。まあずいぶん身勝手な解釈をしていたものだ。でも、自分にとってヘッセ文学はどれもそのような道標であったことは間違いない。今はちょっと違うけれど。まあ、ちょっと冷静にみれば、人間そのものにそなわっている善の部分をそれほど高尚なものとおもわず、文学という俗の部分でうまくとらえ直すっていうか、自分はそこでまたなんとなくくすぐられるのかもしれない。いつかまたヘッセの文学にもどりたいと思って生きてきたが、今はどこかでそんなヘッセのエッセンスがうまく人生に溶け込んでいる気がしている。高橋健二訳が素晴らしい、とは清志郎もいっていったな。
大胯びらき・ジャン・コクトー 澁澤龍彦訳
le grand ecart (グランテカール)とは「両脚を広げて床にピタリとつけること」という意味のバレー用語ですね。少年期と青年期の狭間、いわばコクトー十八番の暗喩。当人は自叙伝説を否定しますが、主人公にその面影がだぶるのはまあしかたがない。とはいえ、ラディゲの「肉体の悪魔」に対抗したこの青春小説には、豊穣なアレゴリーはもちろん、人間コクトーとしての文脈がなんとも初々しい。「ジャック・フォレスチエは涙もろかった。」で始まり。「地上で生きるためには流行を追わねばならぬ。が、心はもはやそれには従わぬ。彼にはそのことがちゃんと分かっていたのである。」で結ばれる。澁澤氏の処女翻訳作品でもある。「petit copin」を「ちびくん」といいかえたタッソーのことばの移替えの手さばきも見事。堀辰雄がこの作品を下敷きにしちゃてるんですね。で、そういえば、コクトーにガールフレンドがいたりしたんですよね、若かりし頃は。


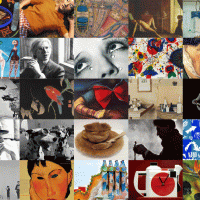










コメントを残す