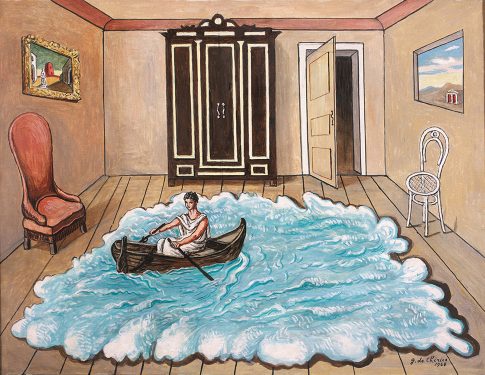ジャン=ピエール・メルヴィル『恐るべき子供たち』を視る
コクトーは文学史的にも映画史的にも、 はっきりとした位置づけの難しい作家だった。 本人は、詩人の血の下に、あらゆる創造メディアを駆使しながら、 詩の世界に戯れ、その世界で才能を発揮し、 今のマルチクリエーターの走りとしての認識も高い。 ある意味、属性なき作家として、その名を刻んだ自由の人だった。 『恐るべき子供たち』には、その奔放な男遍歴から毒好み、 そして生涯抱えていた死の観念といった禁断の世界の片鱗が コクトーの美学として随所に貫かれている作品だ。