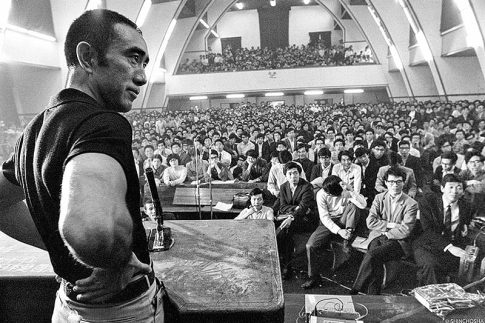ロベール・アンリコ『ラムの大通り』をめぐって
粋な映画とは、このことをいうのだと言わんばかりの作品がある。 ロベール・アンリコ監督による『ラムの大通り』のことだ。 ベティちゃんこと、かのベティ・ブープ(元祖BB?)のモデルの1人 1920年代当時の“セックスシンボル”であった女優 クララ・ボウをイメージしたというのだが、 こちらもそのセックスシンボルの系譜で一世風靡した、 フランスの恋多き女優ブリジット・バルドー(こちらもBB)が リノ・ヴェンチュラを虜にしてしまう銀幕の女優として登場するのだ。