時速8km、赦しのロードムービー
デヴィッド・リンチの名を聞くだけで、
ぼくらは漆黒の闇に沈む悪夢のような世界を思い浮かべてしまうのだ。
『イレイザーヘッド』の胎児的恐怖にはじまり
『ブルーベルベット』の倒錯したフェティッシュ、
『エレファントマン』の残酷で聖なる奇形児の宿命を、
あるいは『マルホランド・ドライブ』の多層的幻影を思い出すからだが、
現実の裏側に潜む狂気を覗き続けた男はそれだけではない。
そのリンチには、あえてそれまでの暗黒世界を封印し、
ひとりの老人の穏やかな旅を描いた映画がある。
1999年の『ストレイト・ストーリー』。
これは、上記の作品にはない、
リンチという作家の“優しさの核”をむき出しにした、
実に稀有な一本であるといえるだろう。
正直に告白すれば、映画としては
自分にとってリンチはこの一本でも十分なのだ。
物語は至ってシンプルだ。
リチャード・ファーンズワース扮する73歳のアルヴィン・ストレイトが、
病に倒れたハリー・ディーン・スタントンの兄ライルに会うため、
耕運機で数百キロを旅するという実話に基づいている。
時速8km、ゆっくり、ゆっくりと進むその旅は、疾走感とは無縁だ。
むしろその遅さこそが、人生というものの本質を照射しているかのように
じわじわと、ゆるやかに迫ってくる確かなものがある。
出くわす人間たちも、このスローライフの男に優しく、そして温かい。
ちなみに、350マイル(約560km)といえば、
おおよそ東京から青森ぐらいの距離だろうか。
平坦な道はある意味、のどかだが、下り坂ともなればそれなりにスピードが乗る。
映画でもそのあたりの狂騒ぶりが描かれている。
制作経緯もまた、リンチらしからぬ温かさに満ちている。
脚本を書いたのは、当時のパートナーであり編集者でもあった
メアリー・スウィーニーとジョン・ローチ。
メアリーがアイオワの地元紙で読んだこの老人のニュース記事を脚本化し、
リンチに見せると、「これを撮りたい」と彼は即決したらしい。
暗黒の詩人として知られる男が、こんなにもストレートで
ヒューマンな映画を撮ると、誰が予想しただろうか?
しかも、本作はディズニー配給。
リンチ映画史上、いや、世界映画史上でも、
奇跡と呼ぶべきコラボレーションがここにあるのだ。
では、この映画がリンチ映画である理由とは何だろう?
そこには彼の人生観が余すことなく注ぎ込まれている。
リンチと言う人は、実は幸福な幼少期を送った。
アイダホやモンタナの田舎町を転々とし、
自然と人々の温かさに育まれた彼は、
世界の優しさと同時に、その裏に潜む闇を
敏感に察知する感性をも併せ持っていたのはよくわかる。
『ブルーベルベット』冒頭、芝生を掘ると蠢く虫たちが現れるシーンは、
彼の原体験から生まれている。
完璧に見える世界の奥には必ず恐怖や狂気が潜むものであり、
それを知っているからこそ、彼はこの『ストレイト・ストーリー』で、
“世界はこんなにも美しい”と、あえて赦すように撮ったのではないだろうか。
主演のリチャード・ファーンズワースもまた、
映画を超えた真実をスクリーンに刻んでいる。
彼は末期癌に侵されながら撮影に挑み、
痛みに耐えながらもアルヴィンの穏やかな微笑みを演じきった。
いや、演じたのではない。
彼自身が、老いと死を見つめながら生きる男だった。
その表情、仕草、ひとことひとことが、演技を超えた存在感となり、
観る者の胸に迫ってくるのだ。
終盤、兄ライルを演じるハリー・ディーン・スタントンと再会するシーン。
二人はほとんど言葉を交わさない。
ただ、見つめ合い、涙ぐむだけだ。
このシーンこそ、リンチが描く“赦し”の極致だ。
スタントン自身、第二次世界大戦で沖縄戦に従軍した兵士だった。
戦争が男に刻む沈黙、痛み、赦しの重さを、彼は誰よりも知っていたのだろう。
その体験はこの映画のシナリオの根底にも反映されているにちがない。
というのも、面白いことに、スタントンとリンチは
後にジョン・キャロル・リンチ監督『ラッキー』で共演する。
『ラッキー』はスタントンの遺作となったが、
デヴィッド・リンチ演じるハワードが、亀を失くして嘆く老人として登場し、
ラッキー(スタントン)と静かに会話するシーンには、
二人の深い友情と哲学が滲んでいたのを思い出す。
リンチは、常に世界の裏側を覗き、恐怖を描き続けてきた作家であるが、
『ストレイト・ストーリー』では、その恐怖を静かに見つめ返し、
「それでもなお人間は優しい」という人生の詩を差し出している。
耕運機のエンジン音は、どこか禅僧の読経のようにも響き、
アルヴィンの旅路に連れ添ったトラクターは
地面を耕す機具でありながらも、
彼自身の人生の地層を掘り返す垢まみれのシャベルでもあった。
時速8kmの旅は普通に考えても遅い。
それを敢行する男に、物語を託したくなるのもわかる。
つまり、その遅さがあったからこそ、彼は兄と和解することができた。
そして、その旅を撮ったリンチもまた、
自身の作家人生において一度だけ、
この混沌とした世界を赦すようにカメラを回したかったのかもしれない。
そう、じっくり人生そのものを見つめたかったのであり
優しさは暗黒の果てにあるのだと、
まさにそういうタイミングだったのだと思う。
『ストレイト・ストーリー』。
それは、暗黒の映像詩人デヴィッド・リンチが、
この世界に捧げた“優しさの時間”だったのかもしれない。
漆黒の幕間であり、夜明け前の闇がいちばん深いように、
この映画の最後に差し込む朝の光のような、
静かで、限りなく優しい瞬間を刻印したかったのかもしれない。
ぼくにも3つ違いの姉がいるのだが、どこかの河川敷でもいいから
いっしょに、また、澄んだ星空を見上げながら、
子どもの頃を懐かしみたいそんな思いがこみあげてきた。
Good Morning,Mr.Echo-Swing Slow
アルヴィン・ストレイトが耕運機にまたがり、時速8kmで進んでゆく物語。まるで心臓の鼓動のように、一定で温かく、どこか懐かしい振動は、道すがら彼が出会う人々の声、風の音、草を踏む音――それらすべてを取り込んで、どこかから返ってくるエコーのように、ゆっくりと心にしみていく。そんな作品には、日本が誇る音楽王細野晴臣と歌姫コシミハルの牧歌的ユニット・SWING SLOWの「Good Morning,Mr.Echo」で一息吐こう。力の抜けたテクノミュージックながら、この二人のコンビだからこそ出せる音の掛け合いもまた、まっすぐで、ゆるやかで、どこか明るく切なさをひきだしている。声にならない想いを、エコーのように届けるための、長い、やさしい旅の始まりに、この幸せなグッドモーニングを贈りたい。








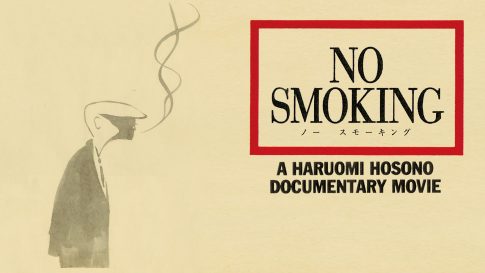




コメントを残す