バーン先生のユートピア講座を体験しよう
知識じゃなく、実際に目撃し、体感すること。
それがなにより大切なんだ by デイヴィッド・バーン
トーキング・ヘッズの伝説のライブ映画『STOP MAKING SENSE』の感動は
40年たった今も忘れてはいない。
(いみじくも4Kレストアでの公開も鑑賞したあとだ)
ダブダブのスーツを着込んだデイヴィッド・バーンの、
クニャクニャダンスが目に焼き付いて離れない。
何より、トーキング・ヘッズ全盛期、
その音楽のカッコよさは、サントラを聴いても今なお十分高揚感がある。
時代が変わり、デイヴィッド・バーンもそれなりに歳をとり、
今度はスパイク・リーと組んで、『AMERICAN UTOPIA』という
またもやご機嫌な映画を届けてくれた。
集大成? いやいや、新たな歴史がここに始まった、
そう言っても過言ではないだろう。
映画館でたっぷり映画を浴びるように体験し、
そしてその体験冷めやらぬようにとサントラを繰り返し聴き、
再びまた、ストリーミングで映画の興奮を思い出しながら
そしていま、こうして冷静を装いながら言葉を書いている。
ポストパンデミックにおいて、もっとも元気をもらった一本の映画である。
なんだろうか?
この洗練された舞台。
素晴らしい楽曲の数々。
インテリジェンスと完璧なまでのパフォーマンス。
賞賛ばかりになってしまうが、映画をみて、
まるで、現地で鑑賞しているような臨場感と高揚に胸打たれた。
至福のひととき、そう告白せねばなるまい。
紐解けば、ザ・バンドの『ラストワルツ』や自身の『STOP MAKING SENSE』、
そんな系譜に属するライブパフォーマンスを扱ったミュージカルであり、
ある種のファンタジーをもりこんだ、なによりも映画である。
むろん、単なるライブパフォーマンスを映像化しただけの映画ではない。
時代とともに、確実に進歩や進化をもちこみながら、
デイヴィッド・バーン自身もまた着実にアップデートしている。
実にスマートなアーティストだ。
素敵なマイラ・カルマンのイラストの幕があがる。
コードレスの楽器演奏、ドラムパートの解体から細分化へ、
時にダンサーのごとく舞台中を自由に裸足で動き回り、
時にさりげなく凄腕の演奏で盛り上げてみせる、
誰一人欠かすことのできない一人一人の仲間に支えられ
バーン自身の世界観、人生観を垣間見せる2時間のステージ。
映画としてのエンディングにもぬかりない、
ラストシーンがこれまたイカしていて、
バーン初め、ステージメンバーが終わったばかりのパフォーマンスを
興奮と充実感でたたえ合っているのを目の当たりにしながら
NYの街並みを縫って、みな爽やかにサイクリングスタイルで家路に就くという
そんなしゃれたシーンが挿入されて終わるのだ。
さすがはスパイク・リー&バーンの仕事だ。
自転車とデヴィッド・バーン。
世界各地で自転車に乗りながら体験した思いを記した
『Bicycle Diaries』というエッセイを残しているぐらい、
移動手段だけに終わらない存在としてのバーンの思いが伝わってくる。
曲目に関しては、映画を見るなり、
あるいはサントラを確認すればそれで良いのだろうが、
やはり、実際に体感する曲の流れのなか、
ハイライトという意味では、ジャーネル・モネイのプロテスト・ソング
「Hell You Talmbout」じゃないかと思う。
権力という、不当な暴力の前に犠牲となった
アフリカ系アメリカ人たちの名前が、
次々に映像とともに連呼される。
パーカーションと声だけのとても力強いナンバーで
メンバーが見事に一体化していると同時に
これこそは、バーン自身の意識の高さをも象徴しているナンバーだと思った。
あらかじめ、「年配の白人男性の自分が歌ってもいいだろうか」と
わざわざ本人に了承をえたのだという。
この曲が、本プログラムに入っている意味はけして小さくはない。
それを意識するまでもなく、メンバーからしても多国籍チームだ。
それはバーン自身もまた、小さい頃スコットランドからの移民だという
アインデンティティの問題も影響しているのだろう。
人種差別から選挙の投票率、そして選挙に行くことの重要性など、
様々な関心事を盛り込みながら、バーンのユートピア思想はショーとして続く。
そこで、改めてデイヴィッド・バーンの書く歌詞が意味深というか、
どこか哲学的解釈を要し、示唆に富んだものだったりするってことに、
改めて驚かされるのだが、
監修に当たったピーター・バラカン氏も、その旨、
ネイティブからしても、解釈が難しい歌詞だといっていた。
バーン先生が現れるステージは、脳ミソの模型を片手に始まる。
よく使う領域、あまり使用されない領域・・・
まずは人間の知能(脳神経)についての言及に始まる。
そこで、人間の脳は大人になれば退化するのだろうか? なんてつぶやく。
以後、科学や哲学、そして政治にいたるまでが
まるで大学の講義みたいに興味深く語られてゆく。
イーノに勧められたというダダイスト、クルト・シュヴィッタースが書いた音響詩
《ウルソナタ》のナンセンスな詩のことを紹介しながら、
ナチズムへの批判として、ヒューゴ・バルの詩を歌っている「I Zimbra」。
デトロイトの高校生に歌わせたバージョン(エンディングで使われている)もある
「Everybody’s Coming to My House」では
「孤独になることは決してない」
「みんな帰らずにずっといる」というリフレインが、そのあとに続く
「この人生において僕らはただの観光客」というフレーズを経て、
ラストの名曲「ROAD TO NOWHRE」へと連なっていく。
その「ROAD TO NOWHRE」では
「我々は行き先のない道の上にいる」という、
まさにこうして歩いてどこかに向かっているということの確かさと安心感、
ここにバーン流の理想郷(アメリカンユートピア)を感じ取ることができるのだ。
この曲で「破滅を諦め、喜びさえ感じさせる曲を書きたかった」と本人がいうように、
仮に終末が来ようと、死が迫っていようが大丈夫なのだ、
そんな楽観思想のもとに進む先に、ゴールなんてものがあるはずもない。
ユートピアとは、必ずしも理想を掲げることではない。
われわれは知識や理屈の前に、その理想を体験しようと
とにかく前につき進むことなのだといっているように思えてくる。
そこに、冒頭のバーンの言葉がすんなり入ってくるはずだ。
その途中に、その過程に、いろんなモノが見えるだろう?
デイヴィッド・バーンの歌詞の裏テーマである「観察」、
それは人種差別、不正選挙、なによりも人生そのものである。
そして、今こそわれわれはコミュニケーションそのものによって、
互いにつながりを持つべきなのだと。
そんな風なメッセージが、ここにあれやこれや聞こえてくるはずだ。
バーン先生は、今や、アメリカという国のみならず、
現代の夢先案内人、いや、かくなる人類の先頭を行く
理想郷のリーダーなのかもしれない、そう思った。
STAGE SET
- Here
- I Know Sometimes a Man Is Wrong / Don’t Worry About the Government
- Lazy
- This Must Be the Place (Naïve Melody)
- I Zimbra
- Slippery People
- I Should Watch TV
- Everybody’s Coming to My House
- Once in a Lifetime
- Glass, Concrete & Stone
- Toe Jam
- Born Under Punches (The Heat Goes On)
- I Dance Like This
- Bullet
- Every Day Is a Miracle
- Blind
- Burning Down the House
- Hell You Talmbout
- One Fine Day
- Road to Nowhere
Once in a Lifetime (Live) | David Byrne’s American Utopia
『American Utopia』の振付は、アニー=B・パーソンによって設計されているのだが、彼女は長年Byrneと共にコラボしており、本作では「非ダンサーが踊ることのポエジー」を徹底して追求している。簡素なグレーのスーツ、裸足でステージを舞い、ダンサー兼ミュージシャンとともにリズムを身体で奏でるその姿は美しく、未来的でありながら、なぜだかとても近しいものとして迫ってくる。
どの曲も、それぞれに魅力があって、一曲を選び出すのはちょっと難しいのだが、やっぱし、この曲「Once in a Lifetime」のかっこよさときたら、特筆しても足りないぐらい、かっこいいのだ。もともと1981年の名曲で、アルバム『Remain in Light』に収録されていたものだが、一聴すると、矛盾をはらんだような歌詞が、日常と存在の境界を揺らがせるように迫ってくる。
ある日ふと気づく――これは、この人生はいったい誰が選んだのか?という目覚めの歌だ。知らぬ間に得た家、仕事、家庭。そのすべてを水の流れに委ねて生きてきた人が、ある瞬間、「自分はここにどうやって来たのか?」という問いの前に立ち止まる。『American Utopia』では、この歌に込められた「無自覚な日常」と「内なる覚醒」というテーマへと、身体と空間で可視化した導きがある。壁のないステージ、裸足の演者、同一の服に宿る差異。そして動き続ける身体は、自動操縦の生活から脱け出すための祈り(儀式)にも似ている。
「ユートピア=どこにもない場所」を、この“今ここ”に出現させるために、Byrneは問いかける。「いま、あなたはどこにいるのか?」と。その問いの余白に、私たちは思わず目をひらかれる瞬間を体験するのだと。
大好きなオリジナルバージョンのPVも載せておこう。
デイヴィッド・バーン。
いくつになっても、かっこいい人だ。





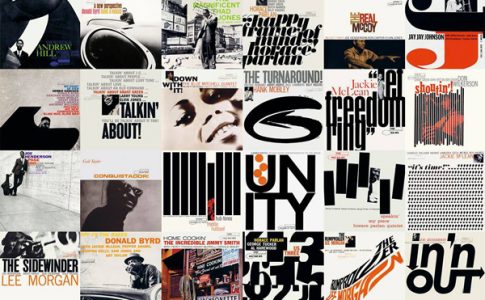


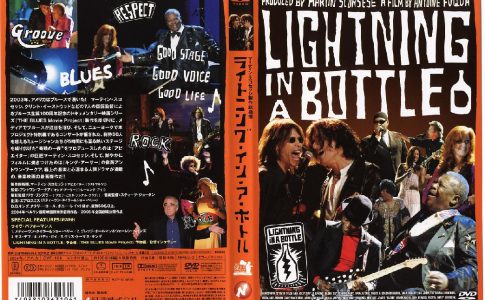

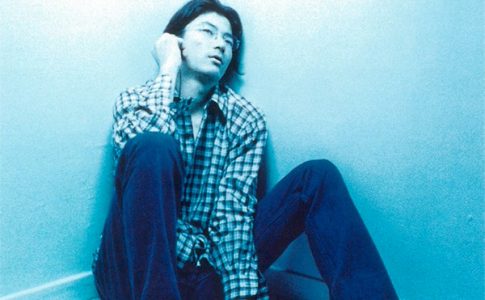


コメントを残す