忘却の彼方に番う海、そして詩
海辺で潮騒の音を聴く。
いや、ただ眺めいる、そして佇んでいる。
テクストから離れて、イマージュにおいて官能性に溺れるということ。
僕が海が見たくなるは、
ただそれだけの理由なのかもしれない。
それは、晴れていなくてもいいし、嵐でも構わない。
強いて言えば、人気のない、見知らぬ海がいい。
さらに言えば、海でなくてもいい。
海を想起させるものがあればそれでいい。
私の耳は 貝の殻 海の響を懐かしむ
ジャン・コクトーの有名な美しい詩だ。
あるいは三好達治の「郷愁」。
海よ、僕らの使ふ文字では、お前の中に母がゐる。
そして母よ、仏蘭西人の言葉では、あなたの中に海がある。(詩集『測量船』より)
母なるものへの郷愁なのか、官能性の先、
さらに遠くにある幻影がおぼろげながらに浮かび上がる。
あるいは、ランボーの『地獄の季節』からの詩、それは「永遠」。
見つかった。
何が永遠が、
海とつがった永遠。
これを引用したゴダール『気狂いピエロ』のラストシーン。
いみじくも、それは溝口の『山椒大夫』ラストシーンで
佐渡の海を見渡す場所で母と息子が再開した、
あの海をパンしたあのシーンを想起している。
海にまつわる思いはそれだけで十分感動的なのだ。
しかし、ここに、兄と妹のただならぬ近親愛がある。
デュラスの『アガタ』である。
海辺のホテル、舞台はそれだけである。
読み上げられるテクスト。
鏡にさえ映りこんだカメラがとらえるイメージの連なり。
そしてホテルの前に海が広がっている。
アガタという響きに、遠い日の兄妹の記憶があり、
同時に、二人が幼き日々を過ごした別荘の名前でもあるのだ。
ただこれだけの要素で、一つの映画たりうる。
そして、一つの物語を語りうるなどということに
人はどこまで、身を委ねられるのだろうか?
僕は、幸運にもその思いに身をまかせ、
無言で、その場に佇んでいる。
そんな記憶の海に出向いて官能性に溺れるが如く、
この不思議なテクストのような映画に身を委ねているのだ。
言葉を交わすことが、別れになる
まなざしを交わせば、崩れてしまう
この声はデュラス自身のものである。
映像にあるのは、そのフィルムにある身体性、
つまりは言葉に託された愛だけである。
ブラームスのピアノ曲を伴って妹、ビュル・オジエが、そこにいる。
そして、もうひとり、兄であるデュラスの恋人ヤン・アンドレア。
そこにいるのはこの二人しかいない。
何一つ発しない登場人物に全てを託せてしまうのだ。
これは映画だろうか? 文学なのだろうか?
なんという共犯関係なのだろうか?
テクストの快楽、映画の快楽との共鳴がそこにはある。
確かにある。
ビュル・オジエについて、
かつて僕は、そこにいるだけで、絵になる女優と書いたが
まさに、『アガタ』においては、それ以上でもそれ以下でもない。
ひとつの存在。
イメージに刻印されたひとりの存在。
時には幽霊の如く、
時には陽炎のように、
彼女はそこにいて、そこにはいない。
永遠という扉に手をかけて、
彼女はすでに、記憶のなかで忘却への誘惑に佇んでいる。
かつて、どこかで見た景観に重なるのは
沈黙そのものの物語を奏でる『インディア・ソング』だ。
『インディア・ソング』では、それはデルフィーヌ・セイリングだったが、
ここではビュル・オジエがデュラスの世界を
言葉でない、その身体性だけで繋ぎ止めている。
そして、海。
しずかに押し寄せる波の音。
空の青、砂浜、そして別荘の室内。
不毛ではない愛、忘却する愛。
手放すことへの恐れ、ゆえの沈黙がある。
私はあなたを忘れるために、愛している。
あなたが去ることでしか、
私たちは生き延びられない。
デュラスの映画は、映画であると同時に映画ではない。
むろん文学とも違うし、小説などでもない。
それは、語りという手法に映像があるのか、
語るが故に映像が立ち現れるのか、
まさに亡霊のような、幻想のような景色でありながらも
そこに、動きを止めた、超然と佇む景色をひたすら見せ続ける。
鏡はそれを記録するカメラの存在を映し出し
同時に、登場人物さえも、一体化させて、
彼らに、映画的な動作を決して要求しない。
メタ文学、メタ映画としての様式なのか、
はたまた新しい言語なのか。
いずれにせよ、見るものを伴って立ち上がる物語に実体はない。
必要などないのだ。
そして、意味もない。
あえて言葉を重ねるなら、
文学で行きつき得ない領域に手をかけるための手段であり、
もっとも映画に近い身体性を纏った詩(ポエジー)なのだ。
デュラスが文学と平行しやってきたこととは、
そうでもしなけば語り得ない愛について考えること。
どうやら、僕も永遠なるものに手をかけてしまったようだ。
愛してはならない人を、愛してしまうとき、
世界は音を失う。
言葉は遅れて届き、
視線は互いを避けるように、記憶に向かう。
Black Rain · Ayumi Tanaka Trio
このところ、気がつけば、ECMレーベルの音ばかり聴いている。マンフレート・アイヒャーが気に入ってレコーディングされたという、日本人ピアニスト田中鮎美の、2021年10月にリリースされた、ベースにクリスチャン・メアス・スヴェンセン、ドラムスのペール・オッドヴァール・ヨハンセンとのトリオで、ECMから発表された初のリーダーアルバム『Subaqueous Silence』がとくに気に入っている。音が少なくとも豊かな物語を語り、聴く者に余韻と瞑想の世界が聞こえてくるのだ。とくに、この「Black Rain」という曲での、コントラバスによるarco(弓弾き)の旋律が心に刺さる。何か喪われたものに寄り添うような距離感をひきづりながら、「過去は語られずとも、音に宿る」ことを知らしめる曲は、どこかデュラスの映像にも通じる世界がある。


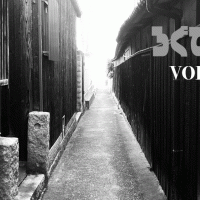



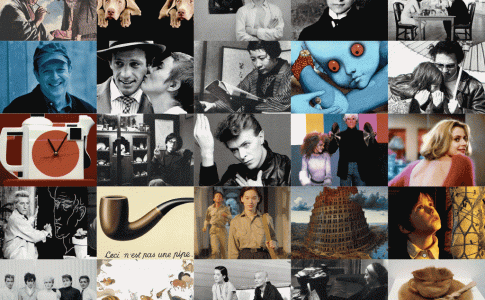






コメントを残す