「国宝」じゃないとは言わせない
歌舞伎役者は生まれながらにして血に芸を宿す、というが、
そんな神話のような言葉を、ぼくらは半ば信じつつも、
李相日の『国宝』の登場によって、ひとつ深く息を飲む機会をもった。
名跡とは呪いであり祝福であり、背負う者の人生を
まるごと飲み込んでしまう力を持つ。
そこに芸が宿り、同時にその芸を蝕む影が潜んでいる怖さを知った。
だが、もしあなたが『国宝』でその血脈の物語に胸震わせた人なら、
どうか一歩だけ時代を遡ってほしいと思う。
1939年、まだ日本映画がモノクロの光と影の中を歩いていた時代。
溝口健二という巨匠が、同じ“芸の宿命”をテーマに、
しかしより剥き出しの形式で映画に封じ込めた作品がある。
それが『残菊物語』である。
これこそは、まさに国宝級の名作であるだけでなく、
今『国宝』を観たあなただからこそ響く、
芸と愛と犠牲の“原型”のような物語がここにもあるのだと。
菊之助はいわば歌舞伎界のサラブレッドである。
血筋は確かな名門の嫡子。
だが肝心の芸が、どうにも育たない。
周囲の役者や師匠は気を遣い、誰も彼の欠点にふれない。
いや、言えないと言った方が正しいのだろう。
名跡には逆らえない。
この重力は、第三者が感じるものとは比ではない
そんな重みがあるのだと思う。
家という制度のなかで、彼は甘やかされ、守られ、
そして停滞することになるのもわからないではない。
そんな彼にただ一人、真正面から“芸の本質”を見抜いた女性がいた。
奉公人であり、身分も低い乳母のお徳だ。
ある日、彼女は正面から言う。
「あなたの芸は、お家のための芸ではありません」
それはなにも愛の告白ではない。
むしろ、残酷なまでの真実の指摘を放つ。
だがその言葉が、菊之助を初めて揺さぶる。
芸とは、血筋では育たない。
誰よりも近くで見つめ、信じる者の存在があってこそ芸を育むからだ。
その逆説が、この映画の中心にある。
『残菊物語』は、普通にみればなんとも残酷で美しい映画にみえるだろう。
だがその美しさとは、キレイな構図や照明だけで生まれるわけではない。
むしろ、溝口健二の信じられないほどの厳格さが導いた、
“真実の美”ゆえの美しさなのだ。
美しさは同時に厳しさあってこそのもの。
いわば血の滲む現場で、溝口は俳優につねにこう問い続けたという。
「反射していますか?」
これは台詞を覚えたかどうかではなく、演技をうまくこなしているかでもなく、
役の気持ちが身体に入り、
その意が自然にあたまのてっぺんから足のつま先まで
芯をともなって反射しているかどうかを問う、
役者にとってこれほど恐ろしい言葉はないのである。
だからこの映画のワンカットワンシーンには、単なる技巧ではなく
“真実の瞬間”を捉えるための魔法陣のように固唾をのむことになるのだ。
例えば、菊之助とお徳がスイカを食べるシーンがある。
お徳はかんざしを抜き、そっとスイカの種を取って彼に渡す。
台詞も説明もないが、その所作ひとつが、
彼を思う気遣いも、階級差の切なさも、
彼女の人生の控えめな献身も、すべてを雄弁に語ってしまうのである。
お徳を演じた森赫子自身が、新藤兼人のドキュメンタリーで語っていたが、
この“自然な所作”を出せる女優でなければ溝口は許さず、
赤ん坊の抱き方ひとつでさえ、経験のない俳優を容赦なく交代させたという。
彼にとって、演技の嘘は映画そのものの死に直結する。
長回しでごまかしの効かない時間の流れを捉える溝口組のカメラ。
そのなかで俳優が思わず“反射”してしまう一瞬こそ、
この映画のもっとも尊い美として刻印されるのである。
菊之助は浪速の地に赴き、次第に芸に目覚め、
二人は身分違いながらも愛を育んでゆく。
その愛は静かで、悲しくて、そのぶん深い。
だが、芸の道はかくも冷酷だ。
そのことは『「国宝』にも描き出されていたところである。
歌舞伎界のしきたりはお徳を拒絶し、
彼女は家の威厳により菊之助と離縁する道を覚悟する。
それでも彼の芸の行く末を信じ、遠くから支え続ける健気な女である。
女が男を支える映画はよくあるが
ただ溝口映画の“支え”とは少し違う。
それは、女としての恋心や尽くす喜びすらも昇華した、
どこか超越の献身であり、愛する男の人生の“影”となって、
静かにその背後に立ち続ける、いわば守護天使のような存在である。
『西鶴一代女』でお春が夜鷹に堕ちてなお美を捨てきれないように、
『近松物語』でおさんが市中引き回されながら愛の純度を保つように、
お徳もまた、絶望の中で、ひときわ美しく死んでゆく。
溝口はそんな女たちを高みに据え、
同時に過酷な運命に投げ込んだのだった。
それは、彼自身の私生活における贖罪の影すら感じさせる。
女性崇拝と女性への加虐。
その矛盾は、残酷でありながら、痛いほどの真実を突く。
それはラストシーンで全てを物語る。
菊之助はついに役者として認められ、
めでたい顔見せ興行に船で乗り込む。
華やかな提灯行脚と晴れやかな視線のなか、
芸の世界へ大きく踏み出す男の影が夜の道頓堀を流れてゆく。
その裏側で、お徳は静かに息を引き取る。
ここにあるのは、幸福と絶望の同時進行だ。
光と闇の美しい対比。
そして、男の成長が女の死によって支えられるという、
あまりに残酷な構造で幕を下ろすこの映画に
『国宝』では決して描きだされなかった無常が漂っている。
だが、その無常にこそ“芸の真実”が潜んでいるのだと思った。
芸とは誰かの犠牲の上に咲くことがある。
血筋ではなく、愛する者の祈りと献身が、
影となって役者の背中を押すことの美しさ。
だが、映画が終わると、菊之助の絶望の前に
お徳の亡き影が、静かに舞台裏からこちらを見つめているように
静かに迫ってくるものがあるのだ。
これは芸道ものでありながらも、
どこか幽玄の世界がしずかに押し寄せてくる映画でもある。
『国宝』は現代における芸の宿命を鮮やかに描いた作品として
今、リアルに人の関心をさらっている。
それを観たあなたは、きっと「芸の血脈とは何なのか」と考えたはずだ。
その問いを、より深く、より痛みを伴う真実へと導いてくれるのが、
この『残菊物語』なのだ。
溝口健二が生涯をかけて見つめたのは、
血筋を越えて芸を支える“影の存在”、
つまり“お徳のような真の人間の愛”だった。
光の表舞台で継がれていくものだけが芸ではない。
影に消えた者がいたからこそ、芸は輝くのだと。
『国宝』の余韻のあとに、この映画を観れば、
芸というものが持つ深い哀しみと美しさが、
さらに別の相を見せてくれるにちがいあるまい。
どうか、この残酷で、美しい物語にも手を伸ばしてほしい。
その瞬間、あなたの中の“芸を見る目”が、
きっとひとつ静かに反射し始めるだろう。
最後に、『国宝』への思いを少しだけ、吐露するとしよう。
世間でいう、評判とはちがって、個人的には少々物足りなかった。
溝口の『残菊物語』には、はっきり人間というものが描き出されていた。
溝口がこだわった、俳優たちの反射が、芸道を彩っていた、そう感じた。
だが、『国宝』は違った。
芸道の美しさ、芸に臨む繊細かつ、真剣な思いは十分だが、
なにかひとつ、足りないものがあったような気がした。
そこはあえて、優劣ではない。
ただ、『残菊物語』の方には、芸の道を生きる生身の人間が
より身近に思えたという意味で、
これこそが本物の国宝だと感じたまでである。
歌舞伎役者・二代目尾上菊之助の悲恋の物語を扱った『残菊物語』は1939年に溝口健二が依田義賢の脚色で撮って以来、1956年に島耕二監督、1963年に大庭秀雄監督がそれぞれ映画化し、1967年には塚田圭一がテレビ映画化しているが、原作村松梢風による小説がベースである、李相日の『国宝』は吉田修一の小説からの映画化であり別物である。
The Neighbourhood – Reflections
映画を観終えたあと、胸に残るのは物語の悲劇性よりも、もっと静かな感触である。ひとりの人間が誰かの人生を映し切り、その役割を終えて消えていく、その“後味”といっていいかもしれない。菊之助は名門の血を引きながら、芸においては半人前。彼の芸が育たなかった理由は才能の欠如ではなく、真実を映してくれる存在が周囲にいなかったからだ。乳母上がりのお徳だけが、彼の芸の未熟さを見抜き、言葉ではなく生活と沈黙によって支え続けた。だから彼女は助言者であり、母であり、恋人であり、そして何より“鏡”だった。
溝口が俳優に求めた「反射していますか?」という言葉は、この関係性を見事に言い表しているように思う。感情を演じるのではなく、相手の存在をそのまま身体に受け取り、自然に返すこと。お徳の献身は意志的な自己犠牲ではなく、反射として生じた行為そのものだ。この構造を的確に言い換えていると思えるのが、The Neighbourhoodの「Reflections」ではないかと閃いた。この曲が、誰かを愛することで自分の輪郭が曖昧になり、相手を映す鏡になっていく感覚を歌っているからだ。救済も成長の物語もないが、ただ、「映っているのは自分なのか、相手なのか分からない」という揺らぎが低く鳴り続ける。これは存在の摩耗の記録に聞こえはしまいか。
お徳はけして自分の人生を語らないし、彼女は菊之助の芸と人間の弱さまでを映し、その反射をひたすら返し続けた。そして彼が舞台に立ち、芸の世界へと渡っていく瞬間、彼女は静かに命を終えるという悲哀。成功と死が同時に描かれるあのラストは確かに無慈悲だ。だが、「Reflections」がふさわしいと思えるのは、この曲が“報われなさ”を否定しないからだ。鏡は割れ、反射は消えるが、映されていたものは確かに残る。菊之助の芸の中に、お徳の反射は生き続ける。残菊物語が残酷で美しいのは、人が誰かの人生を支え切って消える、その瞬間を否定せずに見つめる映画だからだろう。「Reflections」は、その溝口的真実を、時代も言語も超えて、同じ温度で響かせてくれるはずだ。この曲を聴きながら、再び二人を思い返すとき、芸とは血筋ではなく、誰かが差し出した“反射の時間”によって支えられているのだと、あらためて気づかされる。そのとき、この静かな音楽は、拍手の届かない場所で鳴り続ける祈りなのかもしれないのだと思えた。


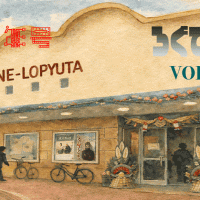










コメントを残す