黒沢清『蛇の道』をめぐって
そのセルフリメイク版は、その名のごとく、一本の直線ではなく、 くねり、迷い、絡まりながら進む不可解な道のりを辿る映画であり、 不条理なドラマである。 1998年のオリジナル版は、ジャンル映画の装いをまとった、 玉石混交のVシネの自由さと制約の狭間に 生理的な不快感をともなう構造的サスペンスを持ち込んだ。 2024年のリメイク版は、その構造さえ疑いながらも、 舞台をパリに移しての、新たな喪失と空白を埋める物語を演出している。
 映画・俳優
映画・俳優そのセルフリメイク版は、その名のごとく、一本の直線ではなく、 くねり、迷い、絡まりながら進む不可解な道のりを辿る映画であり、 不条理なドラマである。 1998年のオリジナル版は、ジャンル映画の装いをまとった、 玉石混交のVシネの自由さと制約の狭間に 生理的な不快感をともなう構造的サスペンスを持ち込んだ。 2024年のリメイク版は、その構造さえ疑いながらも、 舞台をパリに移しての、新たな喪失と空白を埋める物語を演出している。
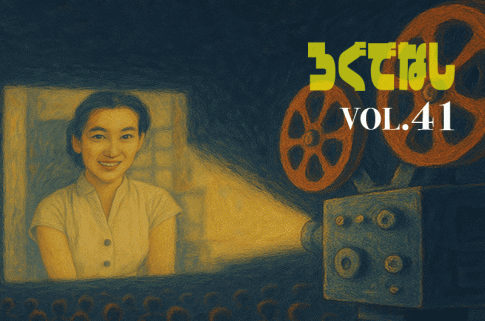 映画・俳優
映画・俳優コロナ禍においては、色々な制限が課されていたこともあり、 映画館へ足を運ぶ機会も意欲も、ずいぶん減ってはいたが、 最近では、気分的にも大きなスクリーンで集中してみる映画体験を 積極的に回帰している自分がいる。 とはいえ、映画を見たい、手軽に見たいという欲望が無くならないが故に、 ストリーミングに頼るという生活もまた、なくなる事はない。 作品を何度も見直すことができるし、 どこでもかからないような、貴重な作品さえも手が届く。 何より、映画を愛するものにとって有難いまでの仕組みが多く提供されている。 いずれにせよ、1本の映画作品の価値は、 形態や見方を変えても変わるわけではない。 その本質を見落としてしまえば、単なる時間の消費に過ぎなくってしまう。
 映画・俳優
映画・俳優カネは天下の回りもの、人の手から手へと移り行く媒体であり、 いわば、人の間をしらないうちに媒介するウィルスのようなものかもしれない。 ロベール・ブレッソンの遺作、その名も『ラルジャン』もまた 今は無き、そのブレーズ・パスカル旧500フラン紙幣にノスタルジーをそそられながら 1枚の贋金が一人の青年を狂わせることになる貨幣の寓話だ。 アンドレ・ジイドによる小説『贋金つくり』が書かれた国、 フランスのパリを舞台にした現代版の寓話には その硬質で静謐な映像の中に、人間の変質、社会の冷酷、 そして神の沈黙という大きなテーマが、ほとんど不可視の形で織り込まれている。 トルストイの短編『にせ利札』を原作としながら、 ブレッソンは、この道徳的物語を説教臭く描くことを潔く拒絶する。 ひたすら無表情なカメラと、モデルと呼ばれた素人俳優たちによって、 まるで機械が悪を運んでいくかのような、非演技的における“構造の悲劇”を描き出し まさに贋札づくりに欠かせぬ、確かで完璧な職人芸が支えるこの映画は いみじくも職人ブレッソンの「シネマトグラフ」に傑作を残し終わりをつげた。
 映画・俳優
映画・俳優『CURE』という映画の感想は 一言で言えば人間の深層を考えさせられる映画、ということである。 オカルティズムやスピリチュアリズムとは違って 人間そのものに潜む心理の綾を巡って そんじょそこらの話題性だけのホラー映画よりも はるかに怖い話が終始展開されているのだ。