ジャック・リヴェット『北の橋』をめぐって
その意味ではリヴェットによる『北の橋』は、かつて74年に撮られた傑作 『セリーヌとジュリーは舟でゆく』からの続編、 とはいわないまでも、ファンタジー性やその虚構空間においては 内容は違えど、どこか地続きの映画構造のように映るだろう。 いずれにせよ、物語に容易に収斂されえない展開ながら 本能的な自由を求める奔放さでもって 観るモノを魅了してゆくリヴェットらしい即興性に満ちた 遊び心満載の、謎解き冒険譚であることは間違いない。
 映画・俳優
映画・俳優その意味ではリヴェットによる『北の橋』は、かつて74年に撮られた傑作 『セリーヌとジュリーは舟でゆく』からの続編、 とはいわないまでも、ファンタジー性やその虚構空間においては 内容は違えど、どこか地続きの映画構造のように映るだろう。 いずれにせよ、物語に容易に収斂されえない展開ながら 本能的な自由を求める奔放さでもって 観るモノを魅了してゆくリヴェットらしい即興性に満ちた 遊び心満載の、謎解き冒険譚であることは間違いない。
 映画・俳優
映画・俳優思い返せば、『暗殺の森』では、主人公の少年時代に、 撃ち殺したと言う思い込みでトラウマを与えることになる 元牧師で男色家リーノを、 ブニュエルの『昼顔』では、見金歯の変態男マルセルといった、 その強烈な役どころが頭から離れない人物を演じている。 兎にも角にも一癖ある俳優である。
 映画・俳優
映画・俳優原作はモラヴィアの『孤独な青年』だが、 映画も小説も、原題からすれば『順応主義者』と訳されるべきところを ニュアンスに誤差が生じている。 冷静にとらえ直した際には、明らかになるわけだが 本編は『順応主義者たる孤独な青年が、森の中の暗殺に立ち会う』話であり、 ファシズムの終焉とともに、少年期のトラウマによって苦しみ行き着いた、 ファシスト足らんとするその人生の幻想が、無化されてしまうのだ。 つまりは心理的ファシズムからの解放を意味する幕切れである。
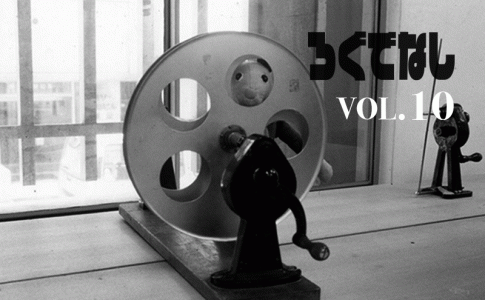 特集
特集「好きな俳優のいる映画をみて、その好きさ加減について 想いを馳せながら他愛も無いことグダグダ書く」シリーズ、 前回の邦画編に引き続き、第二弾は洋画編を書いて見たいと思う。 普段、特に、邦画洋画を意識してみることなどないのだが、 やはり、体系化した方が、何かと整理しやすい、ということだ。