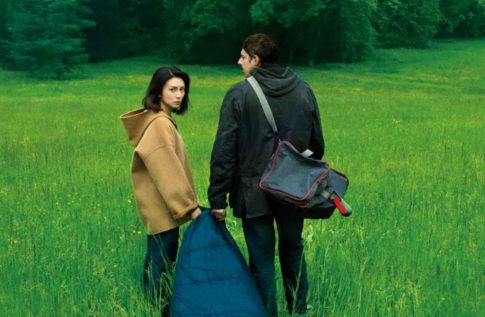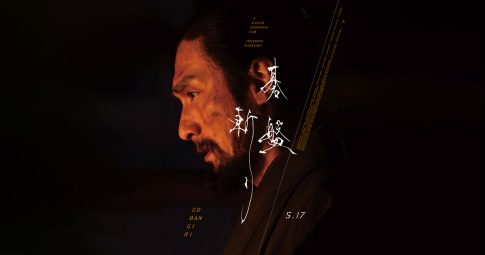マルグリット・デュラス『マルグリット・デュラスのアガタ』を視る
この声はデュラス自身のものである。 映像にあるのは、そのフィルムにある身体性、 つまりは言葉に託された愛だけである。 ブラームスのピアノ曲を伴って妹、ビュル・オジエが、そこにいる。 そして、もうひとり、兄であるデュラスの恋人ヤン・アンドレア。 そこにいるのはこの二人しかいない。 何一つ発しない登場人物に全てを託せてしまうのだ。 これは映画だろうか? 文学なのだろうか? なんという共犯関係なのだろうか? テクストの快楽、映画の快楽との共鳴がそこにはある。 確かにある。